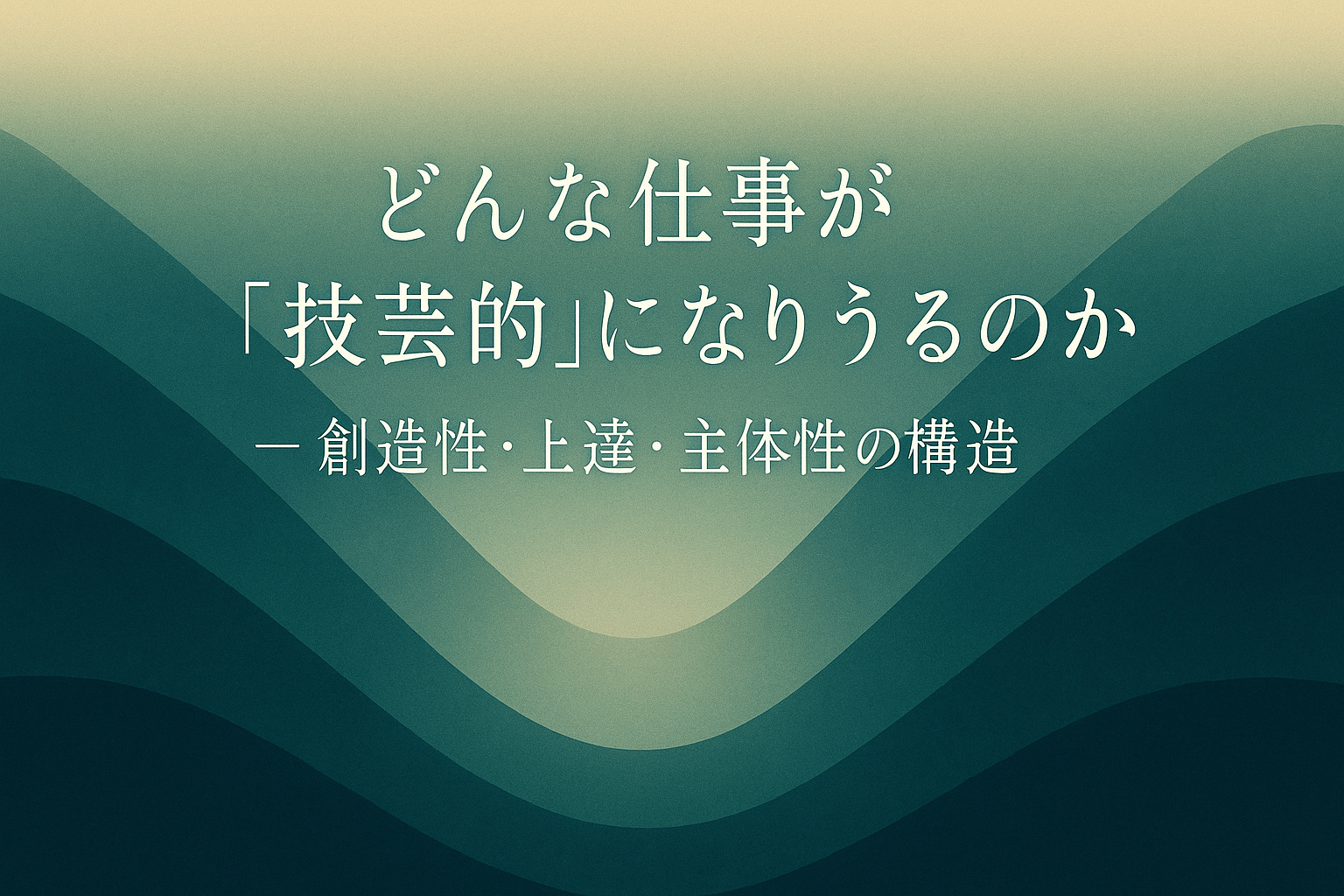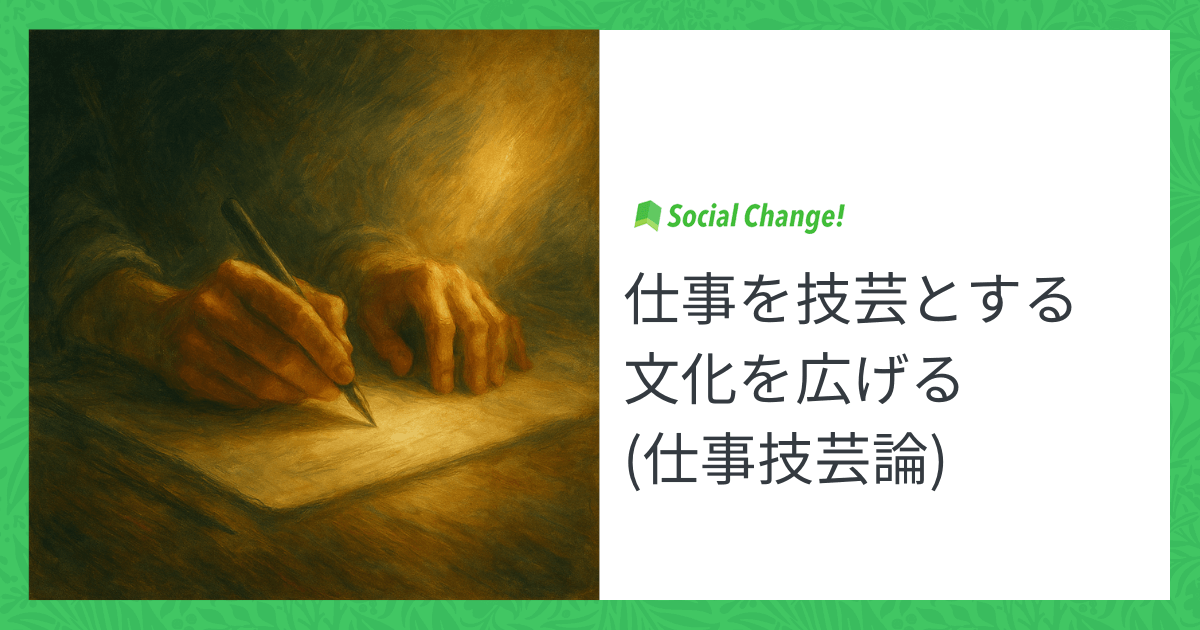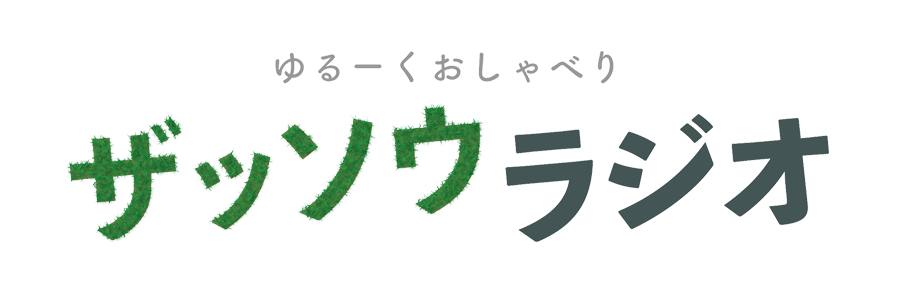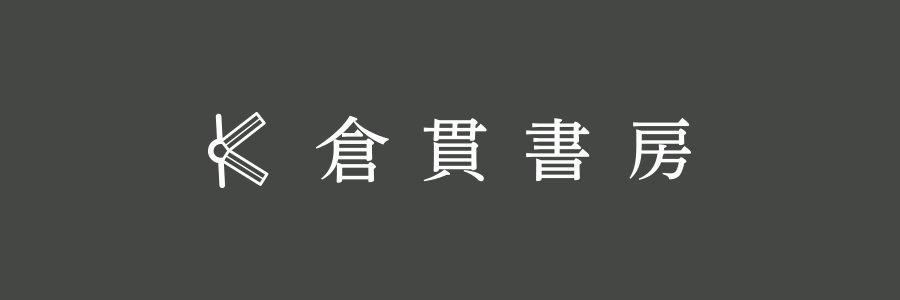なぜ今、「技術」でもなく、「芸術」でもなく、「技芸(クラフト)」という言葉に注目するのか。それは、現代の私たちが仕事に向き合う際、あまりにも極端な二項対立の狭間で、息苦しさを感じているからではないでしょうか。
一方は、効率と再現性を至上命題とし、人間を機械の代替品のように扱う冷徹な「技術(サイエンス/エンジニアリング)」の視点。もう一方は、天性の才能や説明不可能な感性のみを神聖視する、浮世離れした「芸術(アート)」の視点。
多くのビジネスパーソンは、ただの歯車(技術者)にはなりたくないが、かといって特別な才能を持ったアーティストでもない、という現実の中で葛藤しています。
私が提唱する「仕事技芸論」は、この二項対立を乗り越えるための、第三の道です。私がこの考えに至ったのは、机上の空論からではなく、私自身のキャリアにおける切実な「アンチテーゼ(反発)」としての体験があったからです。
原点:「芸術」としてのソフトウェア開発
私のキャリアの原点は、プログラミングという「遊び」でした。(参考記事)
学生時代の私にとって、ソフトウェア開発は、将来のためにスキルを身につける勉強でもなければ、お金を稼ぐための労働でもありませんでした。ただ純粋に、自分の内側から湧き上がる熱意と衝動に突き動かされて取り組む、一種の「芸術活動」だったのです。
自分が書いたコードが動く。一つの機能が出来上がる。それは、粘土で彫刻を作るように、あるいはキャンバスに絵を描くように、自分の手で「作品」を生み出す喜びそのものでした。
そこには、私が作ったのだという「Author(作者)」としての強烈な自負と誇りがありました。だからこそ、バグなどの欠点があれば許せなかったし、誰かに使ってもらい、褒められれば、天にも昇る気持ちになりました。
当時の私の取り組みは、間違いなく「技芸的」な姿勢を持っていました。しかし、それはまだ個人的な衝動の域を出ず、再現性も持続性も持たない、不安定な「芸術家の卵」みたいなものに過ぎませんでした。
衝突:「工業化」という名の絶望
大学を卒業し、社会人として大手システム会社(SIer)に就職した私は、大きな衝撃を受けることになります。そこで待っていたのは、私が愛した「作品作り」とは正反対の世界でした。
その世界で最も重要視されていたことの一つは、「属人性の排除」でした。その先にある思想は「工業化」です。
私には、ソフトウェア開発とは本来、極めてクリエイティブな営みであり、誰でも同じようにできるものではないという信念があります。初心者と熟練者では、生産性に数倍どころか数十倍の開きが出る。それがソフトウェア開発のリアルです。
しかし、当時の業界の主流だった考え方は、開発プロセスを自動車の製造ラインと同じような「工業」とみなし、人間を交換可能な「部品」として扱おうとするものでした。
ウォーターフォール型の開発プロセスのもと、工程ごとに担当者は分断され、下流とされるプログラミングの現場では、上から降りてきた仕様書通りに、ただコードを打つことが求められました。そこに、個人の創造性を発揮する余地は一切ありませんでした。
何より私を絶望させたのは、「人月」という見積もりの単位です。卓越した技能を持つベテランも、昨日今日始めたばかりの新人も、同じ「1人月」の工数として十把一絡げに計算されました。
納期が近づけば、より良いソースコードを追求することよりも、コピー&ペーストでも良いから速く大量に作ることが求められるのです。そこには、開発者としての尊厳はありませんでした。
かつて私が抱いていた「Authorとしての誇り」は、効率という名の下に踏みにじられたのです。当時の私にとって、耐えがたい現実でした。
模索:「作家性」を取り戻すための技術
この人間性を否定するようなソフトウェア開発のあり方に対する強烈な違和感と反発。それが、今思えば私の「仕事技芸論」の出発点となりました。
大量生産の工場のように扱われる開発現場に、失われた「作品を作る作家性(芸術)」を取り戻したい。作った人が銘を打つような誇りを持って仕事をしたい。それが私の切実な願いでした。
しかし、ここで一つのジレンマに直面します。
かつての学生時代のように、自分の衝動や芸術性だけに振り切ってしまえば、それは仕事として成立しなくなります。再現性もなければ持続性もなく、ただの独りよがりな道楽になってしまうからです。
さらに、仕事として一定規模のソフトウェアを作るためには、どうしても一人きりの力だけでは実現することが難しいという現実もあります。組織やチームとして、どのように成果を出すのかを考える必要があるのです。
プロフェッショナルであるためには、安定した成果を出せなければなりません。そのためには、個人の感性頼みではない、共通の基盤が必要です。開発者一人ひとりが人間らしい創造性を発揮しながら、同時に組織としての生産性も担保する。
この相反する二つを両立させる鍵となるのが「技術」であり、それを体系化した「型」です。
到達点:「技芸」と「型」の再定義
その鍵となる「技術」とは、「人間を排除するための工業化技術(テクノロジー)」ではなく、「人間の可能性を拡張するための技能(スキル/テクネー)」のことであり、それを体系化したものが「型」です。
ここで言う「型」とは、思考停止を強いるマニュアルのことではありません。武道や茶道における「型」と同じです。それは、先人たちが積み重ねてきた知恵と経験の結晶です。
かつて私自身にとって、最初の「型」となったのは「アジャイル開発(eXtreme Programming: XP)」でした。
初めて『XPエクストリーム・プログラミング入門』(通称:白本)を読んだ時、そこには私が理想とするソフトウェア開発の姿が、鮮やかな実例と共に体系化されていました。私はそれに雷に打たれたような感動を覚えました。
それからの私は、まさに「守破離」の「守」のごとく、朝会やペアプログラミングといったXPのプラクティスを徹底して真似しました。まずは型通りにやってみる。そこに自己流の解釈を挟まない。そうして身体に型を染み込ませていきました。
そして、現場での実践を繰り返す中で、少しずつ自分たちなりの工夫を加え(破)、最終的には既存のアジャイル開発という枠組みすら超えた、独自の開発スタイルを確立するに至りました(離)。
今のソニックガーデンで行っている開発は、もはや教科書通りのアジャイル開発ではありません。現場で磨き上げ、最適化した、私たちだけの「型」になっています。その型は、親方と弟子の徒弟制度という形で継承されていっています。
型がない状態で闇雲に試行錯誤を重ねるよりも、型がある上で実践を積む方が、遥かに早く、深く、その技能を身につけることができます。型があるからこそ、私たちは共通言語を持ち、仲間と共に学び合い、追求することができます。
型として「技術」が確立されているからこそ、個人としても組織としても安定した成果を出すことができ、尚且つ文化として持続していくこともできるのです。
なぜ「技芸」に注目するのか
私が「技術」でも「芸術」でもなく、「技芸」という言葉にこだわる理由はここにあります。
技芸とは、人間を部品化しようとする冷徹な「工業化の思想」に対する人間性の回復運動であり、同時に、独りよがりな「アーティスト(芸術家)」で終わらないための、仕事で価値を提供する組織としての規律でもあります。
「遊びのように作品作りに没頭する(芸術の源泉)」
「そのために必要な型を学び、自らの身体を通して技能を修練する(技術の土台)」
この二つが未分化に溶け合った状態こそが「技芸」なのです。
現代のビジネスにおいて、私たちはこれ以上、誰でも交換可能な「技術者(部品)」として消耗する必要はありません。かといって、特別な才能を待つ孤独な「芸術家」である必要もありません。
自らの仕事に誇りを持ち、人間らしい技能を磨き続け、仲間と共に独自の価値を生み出していく「クラフトパーソン(技芸家)」として生きる道が、私たちの目の前に広がっているのです。