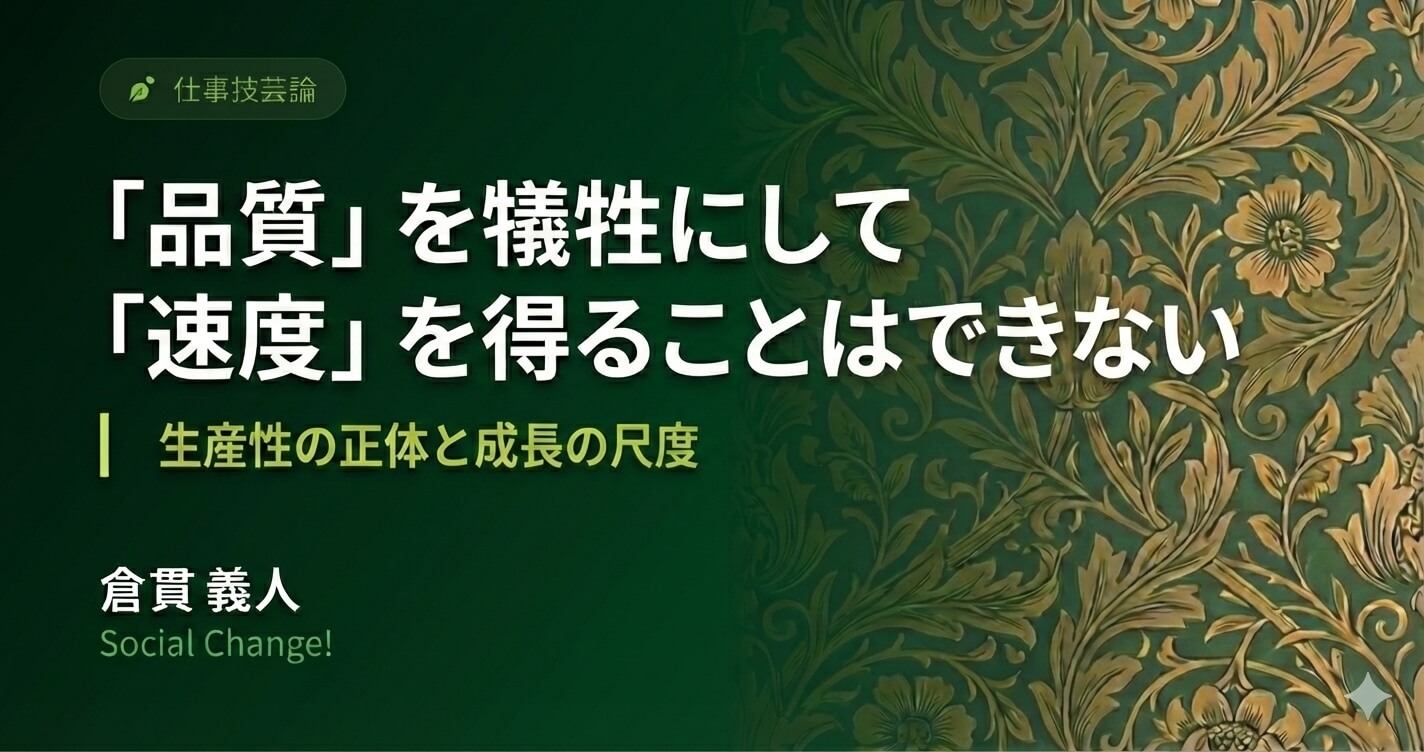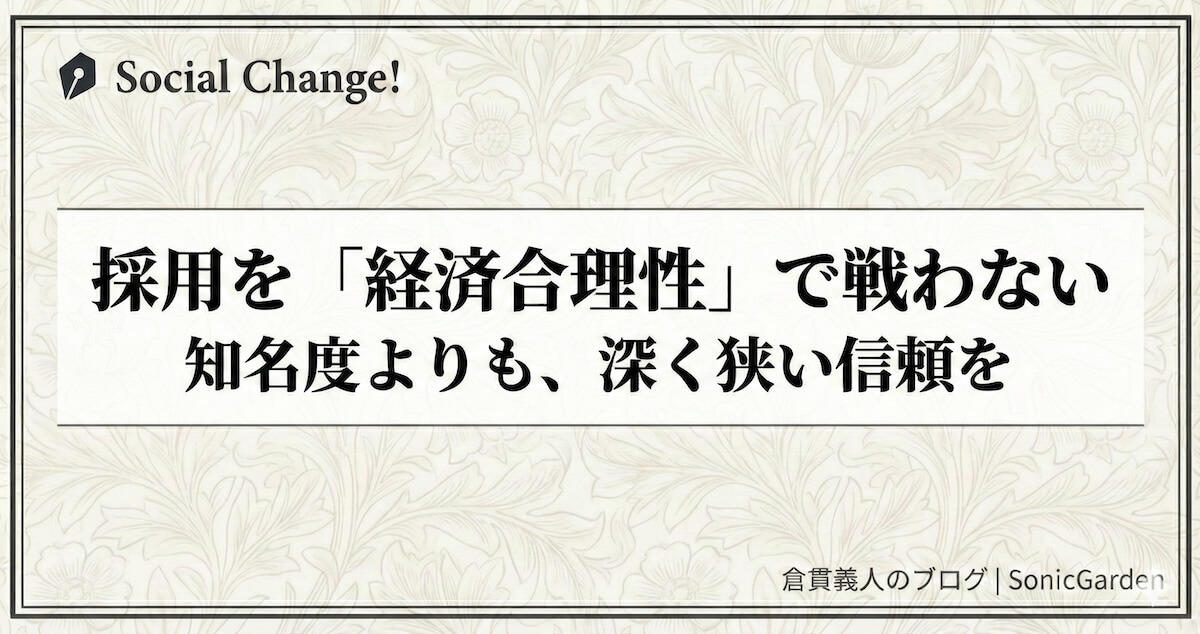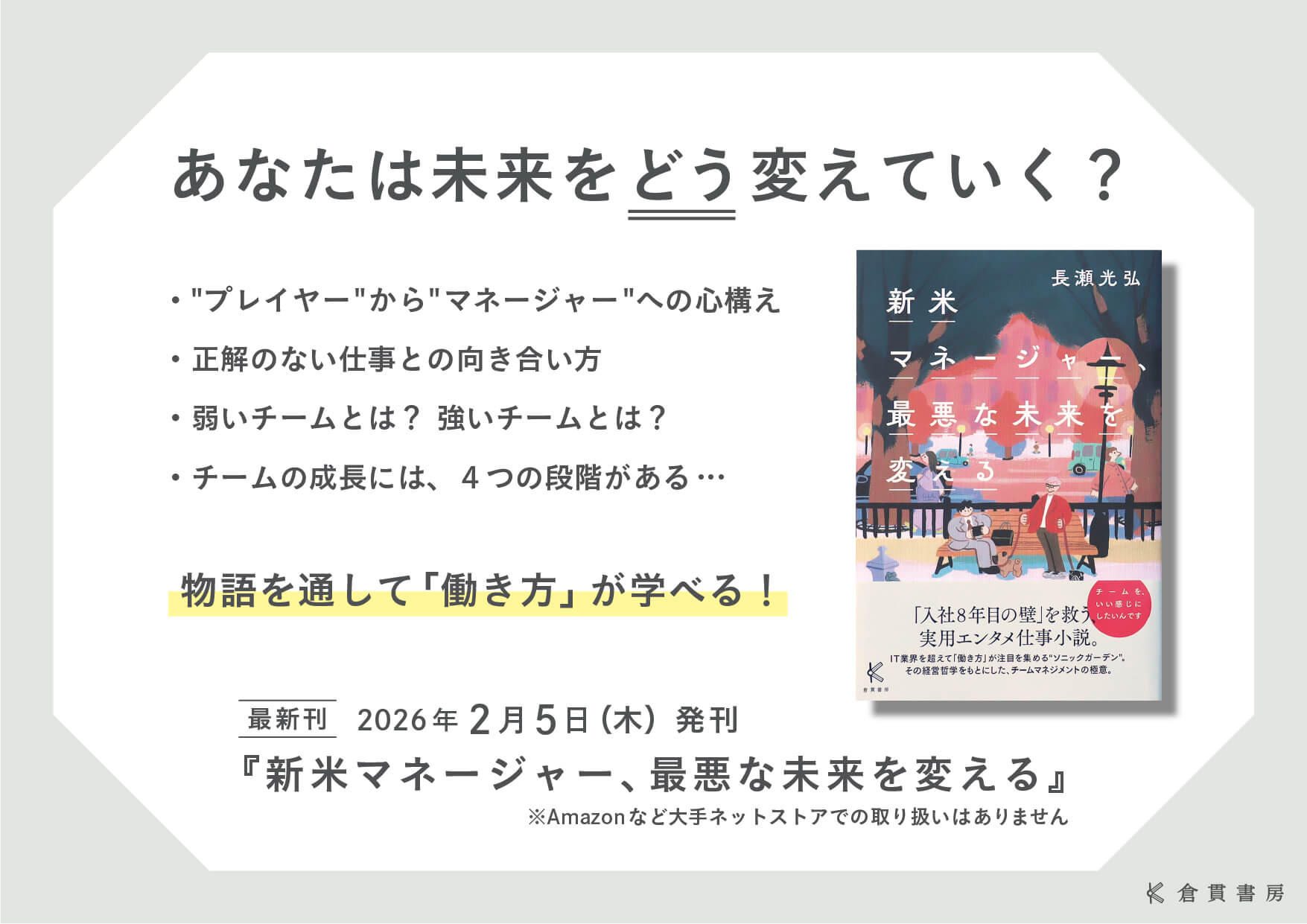【未来日記】通勤を忘れた世界
倉貫 義人
先日、山口県萩市でもリモートワークジャーニーが開催されました。そこで、未来を想像して日記を書いてシェアをする「リモートワーク未来日記」というワークショップが行われました。本記事では、私の考えた未来日記に少しアレンジを加えて紹介します。(未来日記なので勿論フィクションです。)
通勤のない世界
天気の良かったその日、いつものように家で仕事をしても良かったけれど、僕たちは外で仕事をしようと出かけることにした。呼び出した自動運転の車に乗り込んで、彼女が持っていた端末を操作すると車は静かに走り出した。
「こういうの昔の人は”通勤”って言ったんでしょう?」
「いや、違うんじゃないかな。毎日、同じビルに集まることだったはずだよ。」
「わざわざ仕事をするのに1箇所に集まる訳?」
「きっと、その方が効率的だったんだろうね。それに人は集まらないとアイデアが出ない、イノベーションが生まれないなんて迷信もあったらしいし。」
彼女の祖父の時代には、毎日同じ服装をして、同じ場所に行かなければ仕事が出来なかったらしい。らしい、と言っても今も存命で、非常に元気で仕事もしている。医療技術の進歩は、着実に人の寿命を延ばしている。
「それに一斉に電車に乗るもんだから、もう大変だったって。確か通勤地獄って言ってたかな。」
「地獄って、ちょっと大袈裟じゃない?」
「でも、怪我する人が出るほど車両に詰め込まれるんだよ。」
「本当に?たとえ話じゃなくて?・・・うーん、そんなバカなことするのかな。されるがままに詰め込まれるなんてさ。ちょっと考えられない。」
「確かに人間らしくないよね。でも、それが常識だったみたいだよ。」
ふーん、と興味なさそうに彼女は窓の外を眺めた。窓から見える景色はスムースに流れていく。空は明るい。車の中はとても静かで、景色を見ていないと移動していることさえ忘れてしまう。
世の中の常識が変わると、それまでの習慣が非合理に思えるようになってしまうことは、人類の歴史上いくらでもあった。チョンマゲなんてヘアスタイルにとても合理性は感じられないけれど、江戸時代まではそれが当たり前だった訳だ。
だから、”通勤”という仕事のために苦しい思いやリスクを負ってでも移動をする習慣も、今となっては合理的とは思えないけれど、あの当時なら誰も疑問に思わなかったとしても不思議ではない。
彼女はもう外の景色に飽きたのか端末を取り出して眺めている。僕の方も、自分の端末を取り出してオフィスにつなぐ。まだ少し朝早いこの時間から働いているメンバーもいるはずだ。この移動の時間を利用して僕も少し出社しておくことにした。
オフィスに接続してスクリーンが映し出されると、既に数人が働いていた。実際に彼らがどこにいるか、それはわからない。リアルな世界でバラバラな場所にいても、仕事中はオフィスに繋がっているから問題はない。
「おはよう、今日も早いね。」メンバーの一人に話しかけた。
「おはようございます。あれ、今日はいつもと背景が違いますね。車ですか?」
「うん、出かけてるんだ。天気が良いから、江ノ島でも行こうと思って。」
「良いですね。こちらは珍しく雨ですよ。あ、昨日、言っていた契約書のチェックなんですけど・・・」
そうして、マレーシアのどこかの島に住んでいるらしい彼と仕事をしているうちに、車は目的地に到着する。ではまた後ほど、と伝えて僕はオフィスを出て、端末をしまう。車から降りようかと彼女の方を見ると、まだ端末に向かって話をしている。相手は人間だろうか、それとも人工知能(AI)か。
AIを使って仕事をすることも当たり前になった。雑用や調整、予定のリマインダ、調査に資料の仕上げといった、昔で言えば秘書のような仕事は全てAIがやってくれる。もちろん、人間の秘書よりも正確で速い。ある程度の材料と意思を伝えておけば、あとは適宜進めてくれる。
人は人間らしい仕事だけに集中すればいい。もっとも、何が人間らしい仕事なのか、それは僕にはわからないのだけれど。人工知能によるシンギュラリティが起きようとも、人間社会の制度や生き方は、テクノロジーの進化ほどドラスティックに変化するものではなかったようだ。
「お待たせ」彼女は端末を閉じて、一緒に車から降りる。ドアを閉めると車は自動でパーキングに向かって行った。
「潮風が気持ちいいね」こんな感覚は、VR(仮想現実)では感じられない。そのためにこそ、僕らは移動をする。
移動をするのはコストもかかるし、ずっと家にいるよりも安全面で多少のリスクだってある。だから仕事のために移動なんかはしない。けれど、身体で感じられることのために、つまりは娯楽のためなら移動をしても良い。身体的な体験には、それだけの価値がある。VRが普及することによって、実体験の価値は相対的に向上した訳だ。
もはや人にとってプライベートな目的以外では移動などしない。ただし仕事なら、どこにいたって出来るんだから、家に閉じこもって仕事をする必要はない。今日のように、好きな場所に行って、娯楽の合間に仕事をすれば良いのだ。
「じゃあ、あっちの方に行ってみようよ、お爺ちゃん!」ああ、と僕は返事をして少し先を歩く彼女に追いつく。
彼女たちの世代になると”通勤”なんて知らない。海岸沿いを二人で歩きながら、こんな風に自由に好きな場所で働けることが当たり前になるなんて、本当に良い時代になったんだな、と思った。