ブログ「Social Change!」をリニューアルしました〜「仕事を技芸とする」文化を広げるために

サイトをリニューアルしました。新テーマは「仕事を技芸(Arts and Crafts)にする」。創造的な働き方の拠点へ。
働くことを、つくることに。
効率よりも、手と頭で考えながらつくる喜びを大切にする。
そんな仕事のあり方を、文化として根づかせていきたい。
その思想を伝えるメディアが、Social Change! です。
思っていたよりできた、あるいはできなかった、ということではなく、想定したとおりにできること。想定したとおりの反応が返ってくること。そこに安心感があり、それが信頼の本質ではないかと考えました。
できないことや、少し苦手なところがあっても、それを理解している相手のほうが信頼できます。
末永く読んでいただける本を、必要としている人に届けられるように。
変化に合わせて、無駄を見直し、つくること・届けることに全力で向き合う出版事業です。
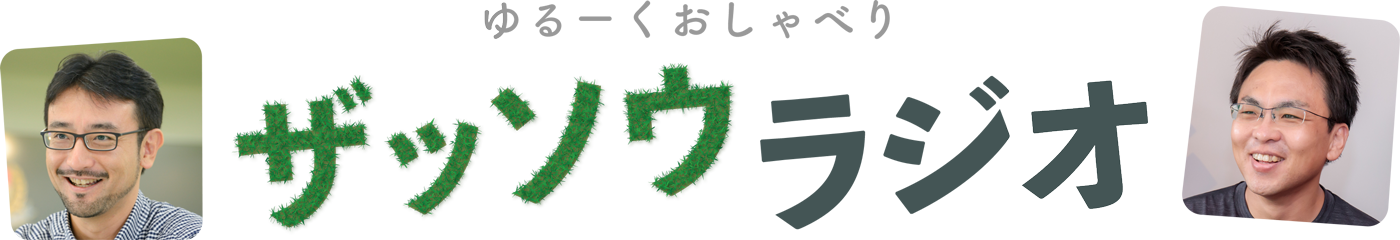
ザッソウラジオは、倉貫と「がくちょ」こと仲山さんで、僕たちの知り合いをゲストにお呼びして、雑談と相談のザッソウをしながら、ゆるくおしゃべりしていくポッドキャストです。










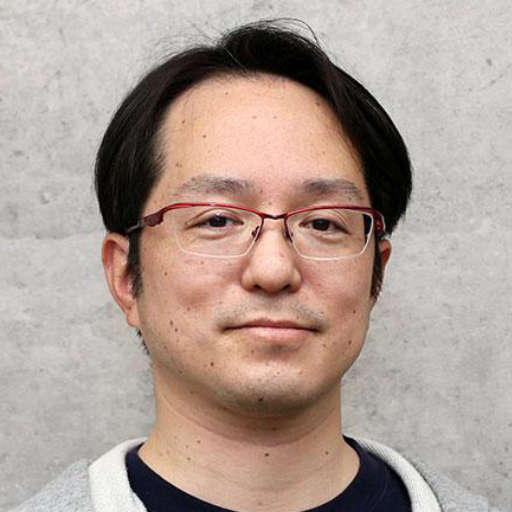



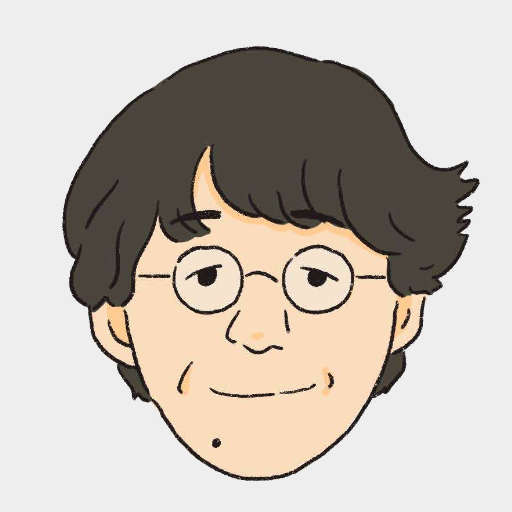










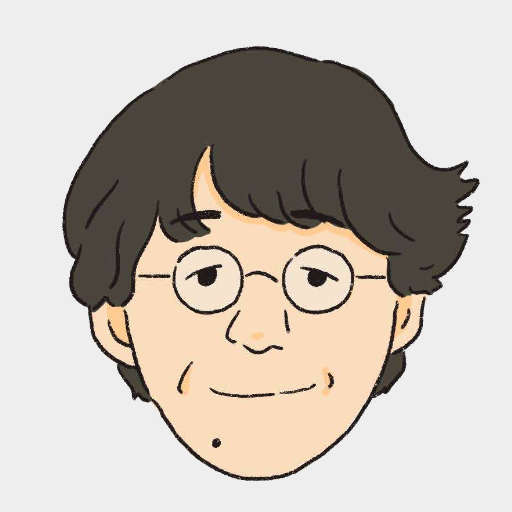













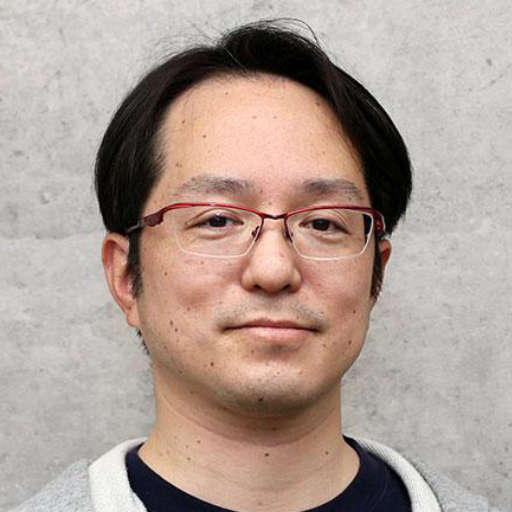










「遅れてるなら人を増やそう」がなぜダメなのか? すべてがソフトウェアになる時代の生産性の常識
ユーザー数が伸びるにつれて多くの要望が出てきても、新しい機能をスピーディーに追加できなくなってきた。
ちょっとした修正のはずなのに、ものすごく時間がかかる。
――そのようなことが起こる原因は、ソフトウェアが変化に適応できないから。
プログラミングを学んでも理解できないソフトウェアの本質を、プログラマーとして12年、経営者として12年の経験を持つ著者の集大成。
これからの事業の成長に欠かせない思考法がわかる。
●「ホウレンソウ」だけではチームは回らない
仕事をする上で、「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」は大切です。
こまめな報告があれば安心でき、
連絡が行き届くことで無駄もなくなり、
相談があることでいち早く問題を解決することができます。
ホウレンソウは社会人にとっての基礎スキルといえます。
ただ、ホウレンソウだけでは、
チームのコミュニケーションが機能しなくなってきています。
近年、チーム間で(とくに、上司と部下の間で)個人的な話がしにくくなっています。
働き方改革によって残業が減り、飲みニケーションや喫煙所での会話も少なくなりました。
ハラスメントに注意しすぎて仕事以外の話もしにくく、
つねに成果を求められているため、短期的な仕事の話が中心になっています。
こうしたコミュニケーションだけでは、
人を、成果を出すための道具としてしか見られなくなり、
やがてチームのモチベーションは下がっていってしまいます。
人としてコミュニケーションがとれる場を、
チームとして継続的に設けることが必要なのです。
●チームを活性化させる「ザッソウ」
具体的にいうと、それはチームにおけるコミュニケーションのあり方を
「ホウレンソウ」のステージから「ザッソウ(雑談・相談)」に上げる、ということです。
ザッソウを通して、メンバー同士が何を考え、
何を感じているのかを共有し、言いたいことを言い合える信頼関係をつくる。
それはチームに心理的安全をもたらし、メンバーのやる気を高めることにもつながります。
それに普段から雑談をしていれば、本当に困ったときに相談しやすくなります。
旧来のホウレンソウだけの状態では、信頼関係ができていないわけですから、
たとえ「いつでも相談していい」と言われていても、なかなか声をかけにくいものです。
つまり話しかける心理的ハードルを下げるためにも、ザッソウは有効なのです。
それだけではありません。新しいアイデアが出ない、専門的な知識がなくて困っている……
そんな問題を解決したいとき、ザッソウでコミュニケーションをとるうちに
価値が生まれることがあります。
ザッソウは、イノベーションにつながるアイデアが生まれ、
チームの生産性を高めることにもつながるのです。
人生の100%を楽しめる組織を作る"究極のマネジメント"とは
「上司なし・決裁なし」
「経費は承認なく使える」
「休暇は取り放題」
「給与は一律、賞与は山分け、評価制度なし」
「売上目標やノルマはなし」
「働く時間も場所も縛りなし」
「副業OK」
最高に自由に働いて成果を出し続ける会社の実体験に基づくメソッドや考え方を
「生産的に働く」「自律的に働く」「独創的に働く」の3つのステップに体系化。
「組織として成果を出すこと」
「個人が楽しく働くこと」
をだれでも両立させる方法がわかる!
●自己組織化された組織に変える3つのステップとは
1生産的で楽に成果を出せるように仕事の進め方を「見直す」
→ やり方・生産性・タスク・やる気・信頼関係・会議・雑談・社内業務・価値
2自律的に自ら働くようにマネジメントから管理を「なくす」
→ 管理・組織の階層・評価・数字・組織の壁・人の急募・教育・制度・通勤
3独創的な強みを手に入れるために慣習に従うのを「やめる」
→ 既存のビジネスモデル・説得する営業・新規事業・規模の追求・会社らしさ
●成果のあがる組織に変えるメソッド・考え方の実例が満載
◎オフィスに通勤しなくても働くことのできる「リモートワーク」。
企業に所属することで得られる安定と、自分の好きな場所で働く自由を両立できる新しいワークスタイルとして注目を集めている。
◎著者は、IT業界で「納品のない受託開発」という新しいビジネスモデル(前著『「納品」をなくせばうまくいく』に詳しい)を創案し実践する中から、
一時期もてはやされた「テレワーク」「在宅勤務」や、フリーランスで仕事を請け負う外注の「クラウドソーシング」等の欠点を克服する新しいマネジメント手法にたどり着く。
それが、離れた場所にいる社員同士がチームで仕事をして成果を出す「リモートチーム」である。
◎本書は、著者の経営する企業でリモートワークを導入し、試行錯誤を重ねながらさまざまな工夫とツールを用いて
問題解決して、社員のワーク・ライフ・バランスと組織のパフォーマンス双方の向上を実現する「リモートチーム」をつくり上げる過程を描く。
◎「リモート飲み会」「リモート会議」「チャット」「論理出勤、物理出勤」「社長ラジオ」などのユニークな取り組みの数々は、
座学や机上の理論にはない、リアルな説得力をもつ。と同時に、社員間のコミュニケーションに対する鋭い問いかけを含み、
あらゆる組織、チームのマネジメントと個々人の働き方を考えるヒントとなる。経営者、従業員を問わず、すべてのビジネスパーソン必読の一冊。
◆一括請負による「納品」に縛られた従来のビジネスモデル
情報システムやソフトウェア開発の一括請負は限られた予算と人員、納期(一括納品)遵守の制約のなかで、
エンジニアのスキル不足と常態化する過重労働(デスマーチ)によって疲弊しがちである。
顧客(ユーザー企業)にとってもいたずらに料金がかさむ割に満足度の低いビジネスモデルである。
◆ソフトウェア業界の常識をくつがえす「納品のない受託開発」というビジネスモデル
こうした業界の通弊を解決すべく考え出されたのが「納品のない受託開発」。これはユーザー企業と顧問契約を結ぶことによって月額定額を受け取り、
納期を廃するソフトウェア開発における常識破りとも言うべき画期的なビジネスモデルである。
◆ユーザー企業にもエンジニアにもメリットの大きい「納品のない受託開発」
本書はユーザー企業にとってもエンジニアにとってもメリットの多い、ソフトウェア開発のビジネスモデル(納品のない受託開発)を、
考案者にして実践者が自ら解説する初めての書。
IT業界、ソフトウェア開発が長年抱えてきた構造的な問題に切り込み、新たなソリューションを提示する。
読者対象は開発企業、エンジニアはもちろん、IT関連ビジネスの経営層、現場担当者、就職学生のほか、起業家、新規事業担当者など。