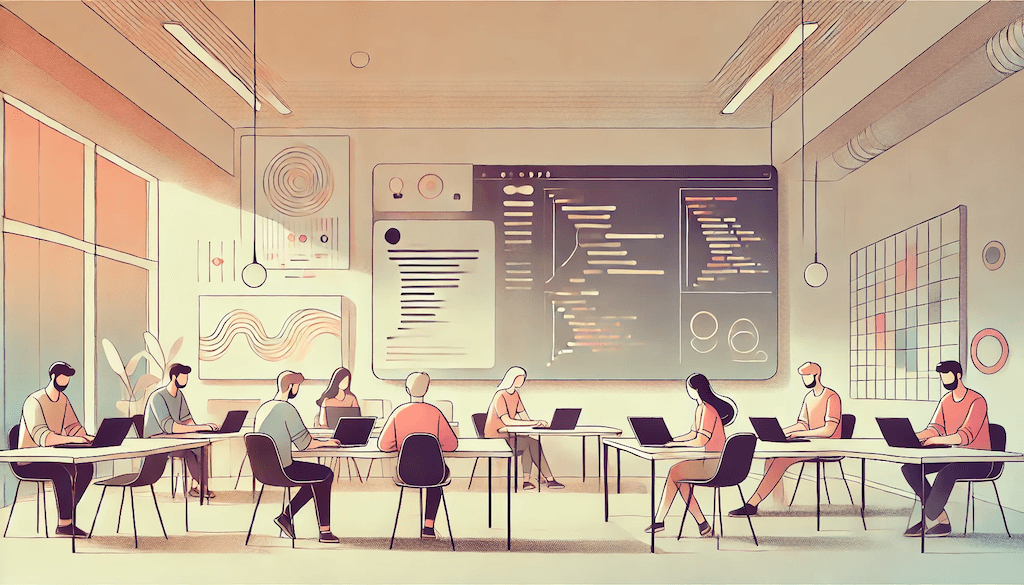
遊びから始まるプログラミング 〜 ハッカソンが育む文化と成長
倉貫 義人
ソニックガーデンでは、「遊び」としてのハッカソンを定期的に開催しています。ハッカソンとは、短期間でアイデアを形にし、技術や創造性を競う開発イベントのことです。
私たちのハッカソンは、業務のためにやるのではなく、純粋にプログラミングを楽しむ機会として実施しています。このような事業に直結しない取り組みは、一般的な経営の視点からすると奇抜に思えるかもしれません。しかし、私たちにとってこの「遊び」の取り組みこそが重要だと考えています。
とりわけ徒弟制度を導入してからは、その弟子たちによるハッカソンを毎月実施してきました。なぜこのようなハッカソンを続けているのか?それは「遊び」こそが成長につながる向上心を生み出す源泉になるのではないか、と考えているからです。
「遊び」は目的と手段を超える
先日、三鷹で開催された「中高生国際Rubyプログラミングコンテスト」に参加して、プログラミングを楽しむ中高生たちの姿に大いに刺激を受けました。ソニックガーデンもここ数年は、スポンサーとして支援しており、入賞者を招いた交流会も実施しています。
そこで感じたのは、彼らがプログラミングそのものを純粋に楽しんでいたこと。特にゲーム部門に参加している中高生たちは、「ゲームを作ること」を目的にしていましたが、その過程自体を「遊び」として存分に楽しんでいました。
思い返せば、私自身もプログラミングを始めたきっかけは遊びでした。子どもの頃、自分で遊ぶためのゲームを打ち込んでいるうちに、段々と色々なことを覚えて、作ること自体に夢中になり、結果それなりにプログラミングができるようになってました。
「遊び」から始まる成長のプロセス
現代では、多くの人が就職や転職を目的にプログラミングを学びます。しかし、こうした目的的な学びでは、効率や結果に意識が向きがちです。修得は課程に過ぎなくなります。一方で、もしプログラミングそのものを「遊び」として楽しめれば、苦労に耐えるのではなく、自然と続けることができます。
「遊び」とは何か。著名な幼児教育学者の方によると、以下の3点で定義されるそうです。
- 自発性があること(自分から始める)
- 自己完結性があること(自分が満足するまで続ける)
- 自己報酬性があること(自分が面白いからやる)
プログラミングが上記に示すような「遊び」になれば、いつまでも続けることができて、いくらでも横道に逸れて、無駄なことは何もなくなります。なにより夢中になることで、上達のスピードは格段に上がるでしょう。
「遊び」が向上心の源泉になる
ソニックガーデンでは、徒弟制度を取り入れています。この制度では「守破離」の中でも「守」を特に重視しており、親方の指導を忠実に実践することから始めます。プログラミングの上達には、スポーツやアートと同じように、まずは師匠の型を身につけ、それに基づいたフィードバックが欠かせないからです。
時に厳しいフィードバックもありますが、弟子たちは真摯に受け入れて、上達していきます。その根底にあるのは「もっとうまくなりたい」という気持ちです。向上心があるから、素直に親方からの教えを請うことができるし、親方もフィードバックのしがいがあります。
では向上心は、どこから生まれるのでしょうか。その源泉は「遊び」ではないかと考えています。為末大さんの著書『熟達論』では、熟達のプロセスを「遊」「型」「観」「心」「空」の5段階としています。これは私も同感で、最初は遊びから向上心が芽生えるように思います。
そのため、ソニックガーデンに新卒で入社した社員には、弟子になる前にプログラミングで遊ぶ時間を確保しています。このプロセスを経ず徒弟制度に進んでも、厳しさに耐えるだけになり長続きしません。また、たとえ一人前になっても、プログラミングを突き詰める姿勢は変わらないため、一時的な努力や忍耐だと考えているうちは入門できないのです。
ハッカソンで自主性と創造力を育む
ソニックガーデンでは、弟子たちが参加する「弟子ハッカソン」を毎月開催しています。この弟子ハッカソンでは、普段の業務から離れ、1日かけてテーマに沿ったプログラムを作り、その日の夕方にデモ発表を行います。優勝者には次回のテーマを決める権利が与えられるだけで、特別な報酬はありません。それでも一生懸命に取り組んでいます。
この取り組みの意義は、自主性や創造力を養うことです。普段の業務では、ゼロから何かを作る機会や、自分だけで設計方針や品質を決める機会は多くありませんが、ハッカソンではそうした経験の場となります。どうすれば面白くなるか企画を考え、作りながら試行錯誤を繰り返し、新しく学んだことが、結果的に仕事の成果にもつながります。
とはいえ、あくまで順番はプログラミングを面白がれることが先です。仕事につながらなくても楽しめたら良いのです。むしろ、学びや成果を求めずに取り組むようにしたいし、そうした文化をつくるためにも、会社としては売上につながる時間を減らしてでも、プログラミングで遊ぶハッカソンに取り組んでいます。
ハッカソンを通じて築く新しいプログラミング文化
私たちは、一般の方々に向けて「作って遊ぶハッカソン(ツクアソ)」や、仲間と一緒に開発できるソニックガーデンキャンプを開催することで、「遊び」のハッカソンを通じてプログラミングの楽しさを知ってもらう活動も行っています。
世の中としては事業創造や社会貢献としてのハッカソンが増えています。それはそれで意義深いものですが、私たちはプログラミングそのものを楽しむ「遊び」のハッカソンを続けることで、プログラミング自体を一つの文化にしていくことができるのではないかと考えています。
これからも、ハッカソンを通じて『遊び』としてのプログラミング文化を育みたいと思います。それは、プログラミングを楽しみながら成長できる人を増やし、やがてプログラミング自体が多くの人にとって身近なものとなる未来につながると信じているからです。


