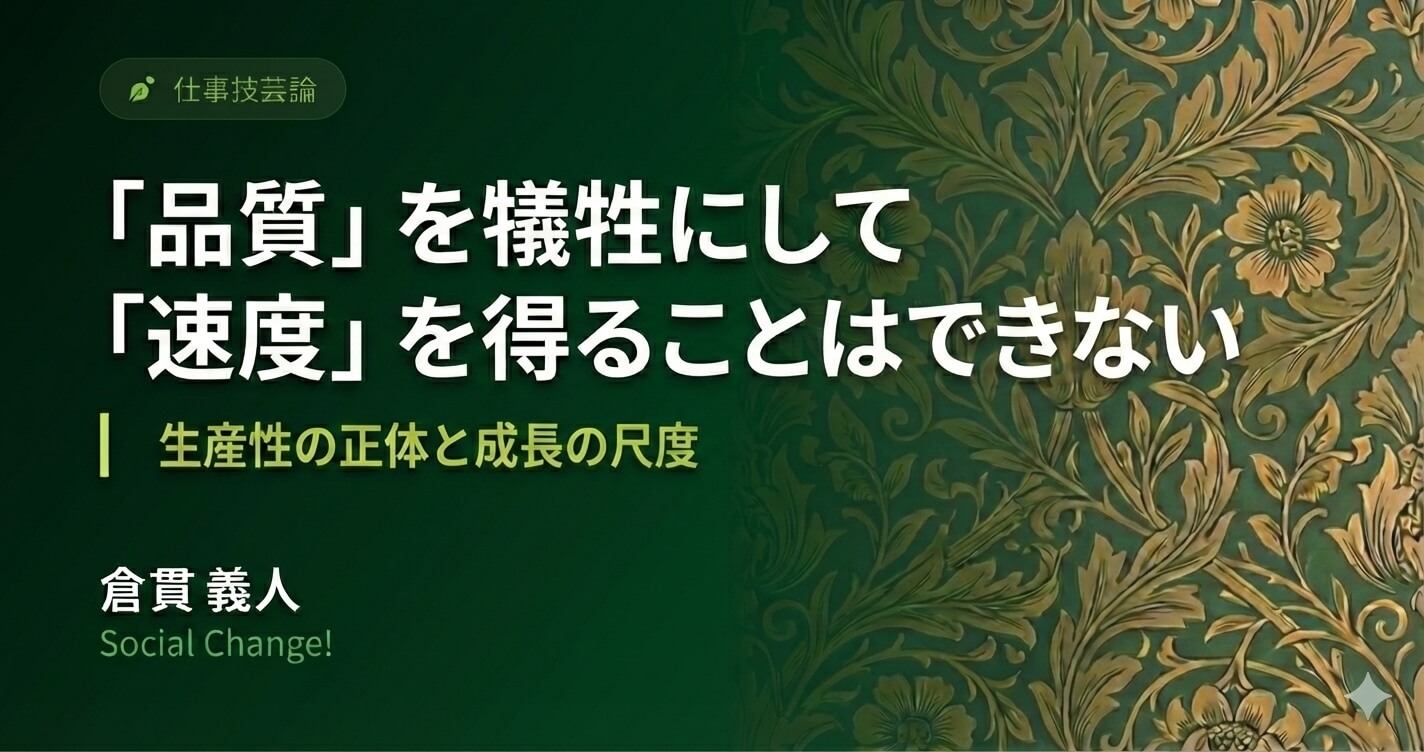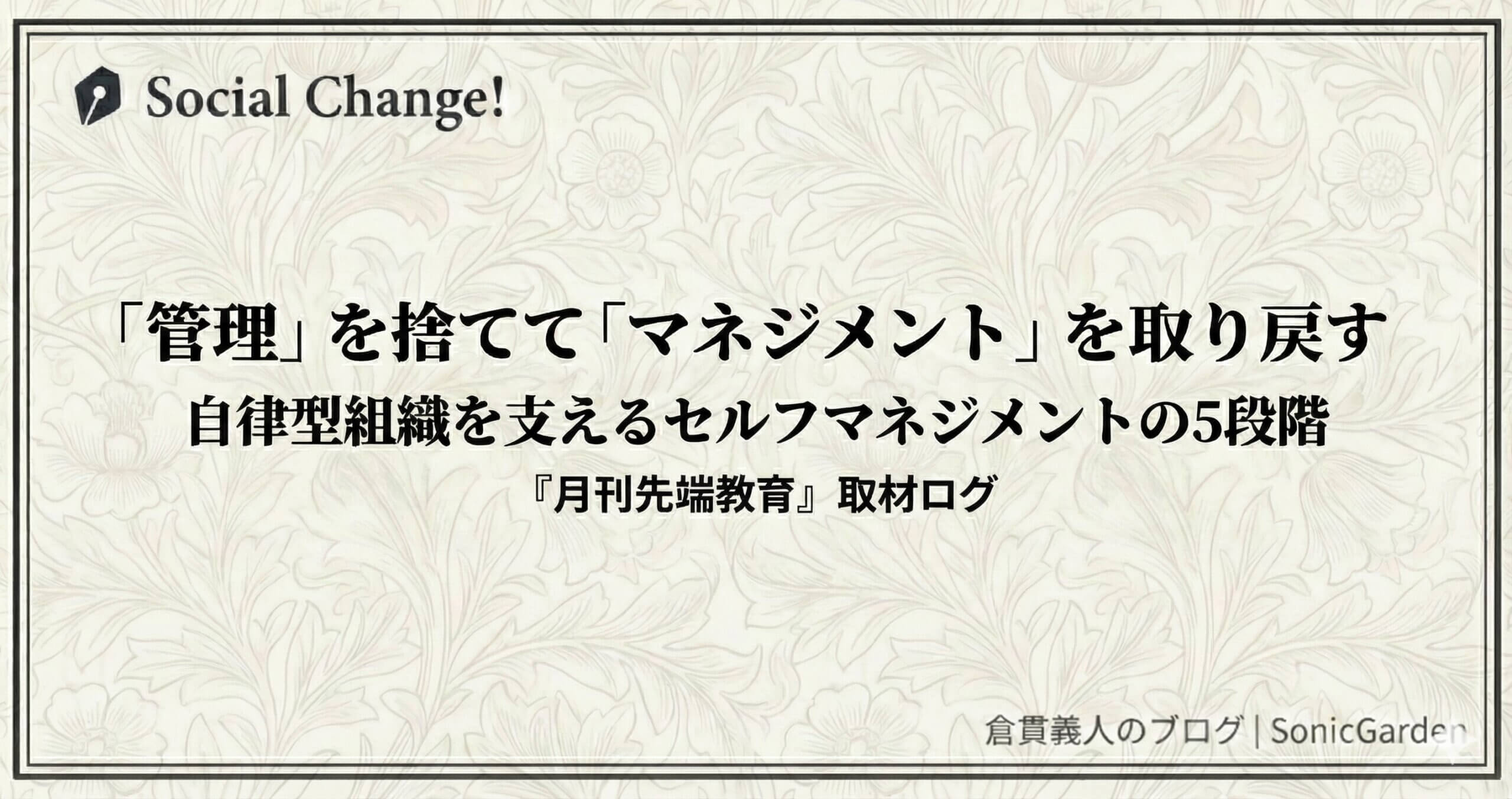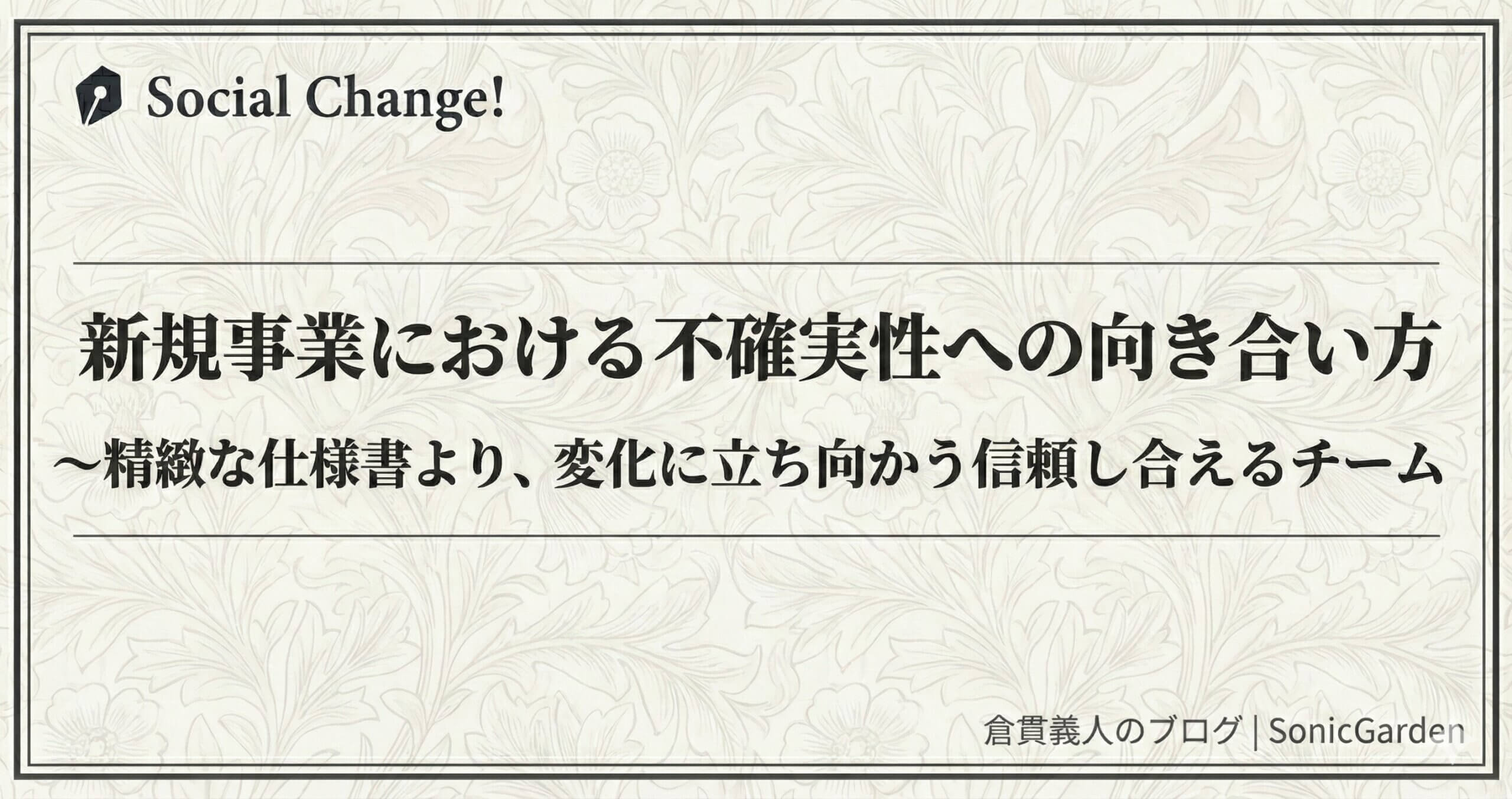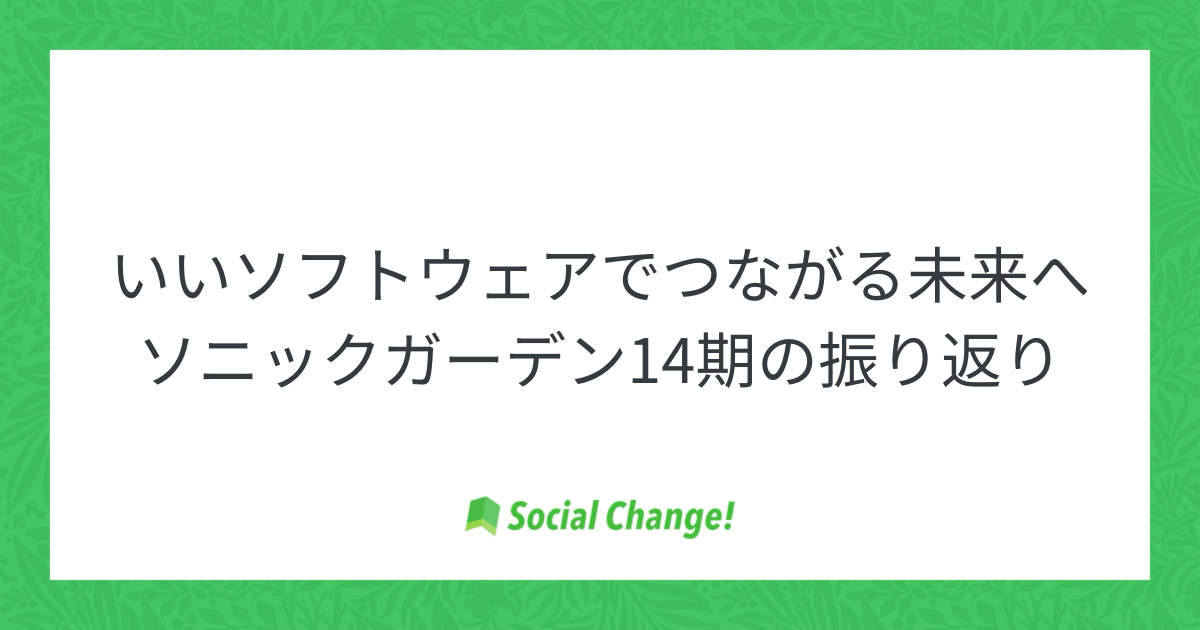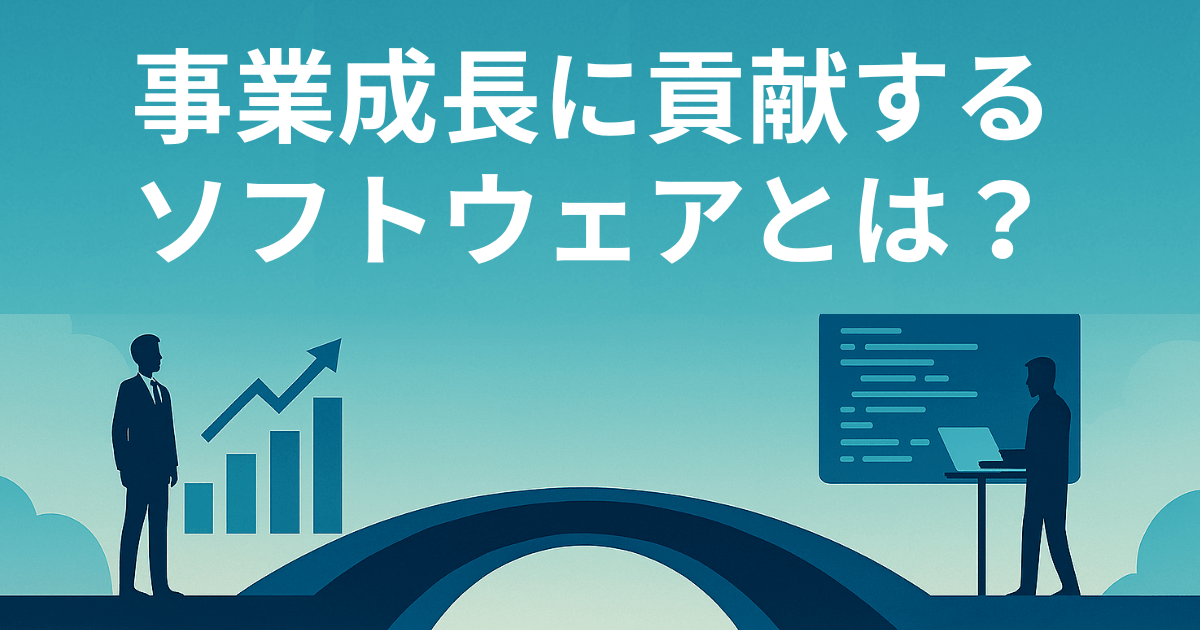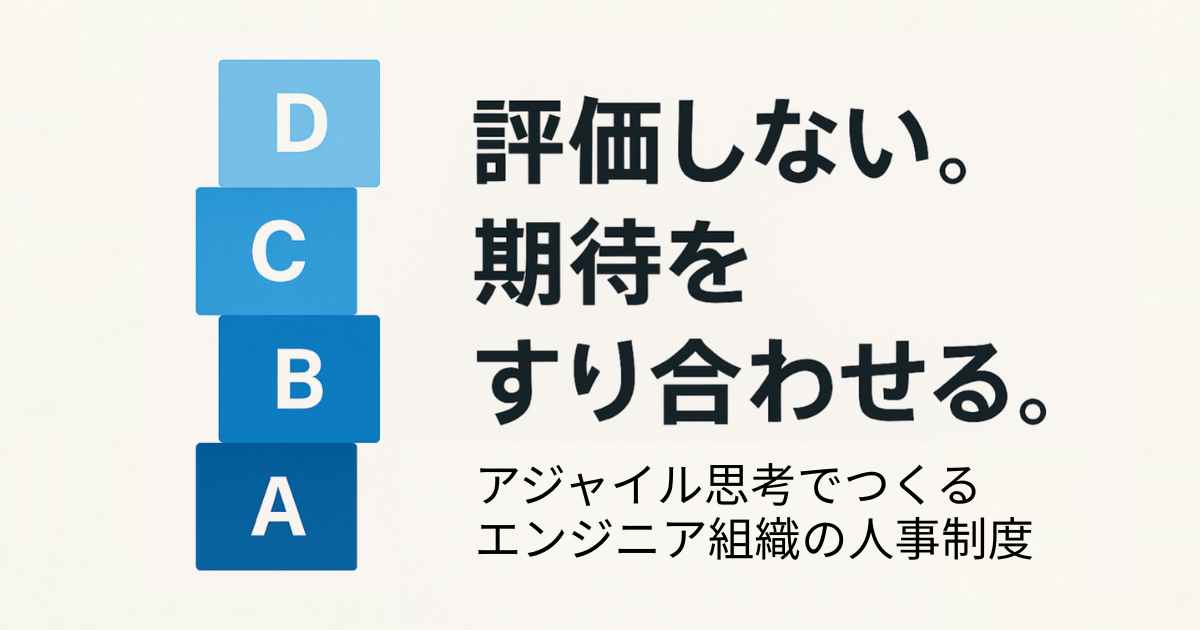
アジャイル思考でつくるエンジニア組織の人事制度〜「評価」から「期待のすり合わせ」へ
倉貫 義人
エンジニアが増えて組織になってくると、人事評価は避けて通れません。とはいえ、昔ながらの目標管理による評価方法は、「不確実性の高い領域」や「知的創造が求められる職種」とは極めて相性が悪いものです。エンジニア組織がその典型でしょう。
本稿では、そうしたエンジニア組織における人事評価について、私たちソニックガーデンでの実践をもとに考察します。エンジニアに限らず、クリエイティブな組織をマネジメントされる方にとって、参考になれば幸いです。
なぜ目標管理がエンジニアに合わないのか
一般的な人事評価制度では、半年〜1年のスパンで目標を立て、その達成度合いで評価を行う「目標管理」の仕組みが多く見られます。ところが、エンジニアという職種においては、そもそもこのやり方がうまく機能しません。
理由は大きく4つあります。
- 技術や環境の変化が激しく、仕事内容が変わることも多いため、半年〜1年の目標設定が難しい
- 成果が個人単位で明確に分けづらく、チームで達成する性質が強いため、個人評価と相性が悪い
- 仕事の成果が売上には直結しづらく、品質の良いコードを書いたとして、短期で効果測定が困難
- 技術的負債の解消やメンタリング、試行錯誤や技術的チャレンジなど定量化しにくい貢献が多い
つまり、エンジニアの仕事は、事前に計画された目標に向かって進めるタイプのものではなく、変化に対応しながら最適解を探っていく営みなのです。そこに、事前に固定的な目標を設定して評価するような仕組みは合いません。
目標管理とウォーターフォールの共通点
このように考えていくと、目標管理型の人事評価制度は、ウォーターフォール型の開発手法とよく似ています。事前にすべてを決めて、進捗を管理し、最終的に納品して完了とする。そのプロセスは一括請負型のビジネスモデルを前提としています。
しかし、私たちが取り組んでいるような「納品のない受託開発」では、要件を事前に決めず、変化に応じて優先順位を変えながら、継続的に価値を届けていきます。これはまさにアジャイル開発を体現するためのビジネスモデルなのです。
そうであるならば、このアジャイル開発の考え方を人事評価にも転用できるのではないかと考えました。目標を定めて進捗をチェックするのではなく、今ある現実を見つめ、柔軟に対応していく。そうした思考で評価に向き合うことで、エンジニア組織にふさわしい形が見えてきます。
アジャイル思考に基づく評価の3つのポイント
アジャイル思考を評価に応用するうえで、大切にするのは次の3点だと考えています。
- その人の今の状態を把握し、存在そのものを認める
- 今できることをベースにすり合わせ、伸び代への期待は含めない
- ギャップを埋めることを求めるのではなく、各自がベストを尽くせる環境をつくる
まず大事なのは、「今の状態を見ること」です。単に成果物を見るのではなく、マネジメントコスト──たとえば、仕事を振る手間や、心配する負荷、トラブル対応の頻度──も含めて観察する。そして、そのうえで「今できていること」にきちんと目を向けて、認めることから始めます。
次に、「伸び代」への期待を評価に含めないことです。ピーターの法則にもあるように、できたから昇進という仕組みでは、いつか能力を超える仕事を任され、本人が苦しむ結果になってしまいます。だからこそ、今できていることを、今後の期待として明示的にすり合わせていくのです。
当初の期待を大きく超えて、伸び代を実際に伸ばせて安定した成果がだせているのなら、そうなってから次の段階に進むのです。あくまで実態が先で、見合う責任と報酬の大きさは後で合わせていくのです。
最後に、キャリアアップを前提とした次のキャリアとの「ギャップを埋める」ことをゴールとするのではなく、「それぞれが今できるベストを尽くせる状況を整える」ことこそがマネジメントの役割だと捉えます。
従来の「ギャップを埋める」目標管理型の人事制度では、常に「まだ足りない」「できていない」という状態が続きがちです。毎日「足りない」と感じながら過ごすのは、本人にとっても、マネジメント側にとっても精神的に負担がかかるからです。そうではなく、できることを少しずつ増やし、伸ばしていくことだけに集中するのが積み上げ型であり、アジャイルであるということになります。
期待をすり合わせる「キャリブレーション」
こうした考え方に基づいて、私たちソニックガーデンでは「キャリブレーション」という人事評価の仕組みを導入しています。
キャリブレーションは、もともとは私が取締役CTOを務めるクラシコムで生まれた仕組みです。「評価」ではなく「すり合わせ」によって期待を調整していく、そんな発想から生まれました。
参考記事:
“評価”ではなく“期待”をする 目標管理をしないクラシコムの「キャリブレーション」
実際の運用では、各人の現在地を観察したうえで、次の半年〜1年間に「何を期待できるか」をすり合わせます。無理に高い目標を置くことはせず、「できていること」に目を向け、それを続けてもらうというメッセージを明確に伝えます。
例えば、成長段階を「A・B・C・D」としたときに、ある人が「B」のレベルの仕事を安定して担えているのであれば、次の期間も引き続き「B」の役割を期待します。無理に「C」の仕事を求めてしまうと、常に「できていない」という評価になってしまい、本人にとっても不健全です。
一方で、挑戦の機会があれば「C」や「D」に取り組むことは歓迎されます。重要なのは、それを安定してこなせるようになったと確認できたときに、初めて次の段階として期待を更新するということです。
期待に応えてくれたら、まずは感謝する。それ以上の成果が見られ、「今の仕事では物足りなさを感じている」段階になったら、次のステップを用意する。そうやって無理のない成長を支えていきます。
私たちが目指しているのは、誰もが100点満点を取ることではなく、それぞれが自分の100%を発揮できる状態をつくることです。 評価というより、そうした状態づくりを支えるための対話の仕組みがキャリブレーションです。
組織の変化と評価の必要性
かつてのソニックガーデンは、評価制度も給与差もないフラットな組織でした。全員が即戦力で、セルフマネジメントができる前提があったからです。
しかし、徒弟制度の導入により、若手メンバーが加わるようになりました。彼らはまだ成長途中であり、同じ給与体系では不公平になる。そこで「果たせる責務の大きさ」に応じた報酬が必要になりました。
キャリブレーションは、そうした組織の変化に応じて導入された仕組みであり、同時に私たちが大切にしてきた「フラットな関係性」を保つための工夫でもあります。
キャリアは直線でなく、探索的であっていい
ソニックガーデンの弟子たちには「一人前のエンジニア」を目指してほしいと思っていますが、その道のりは一本道ではありません。一人前の定義自体も、時代や組織の状況によって変わります。
用意されたチェックリストをこなして昇格していくのではなく、回り道をしたり、失敗したり、さまざまな経験を通じて育っていくほうが、結果として強く、しなやかなエンジニアになる。
「成長の遅い木ほど、もっとも堅い木になる。」
焦らず、着実に経験を積んでいくこと。それこそが、ソニックガーデンの若手に伝えたいことであり、私自身が経営において大切にしている姿勢です。
信頼関係の文化が、制度を超える
人事制度は「制度」としての仕組み以上に、それがどんな文化を支えるかが重要です。
制度に頼って人をマネジメントするのではなく、文化として「信頼しあい、対話し、期待をすり合わせていく」関係性を育てること。キャリブレーションという取り組みは、そのための実践でもあります。
私たちはこれからも、制度ではなく文化として、メンバーの成長と向き合っていきたいと思っています。