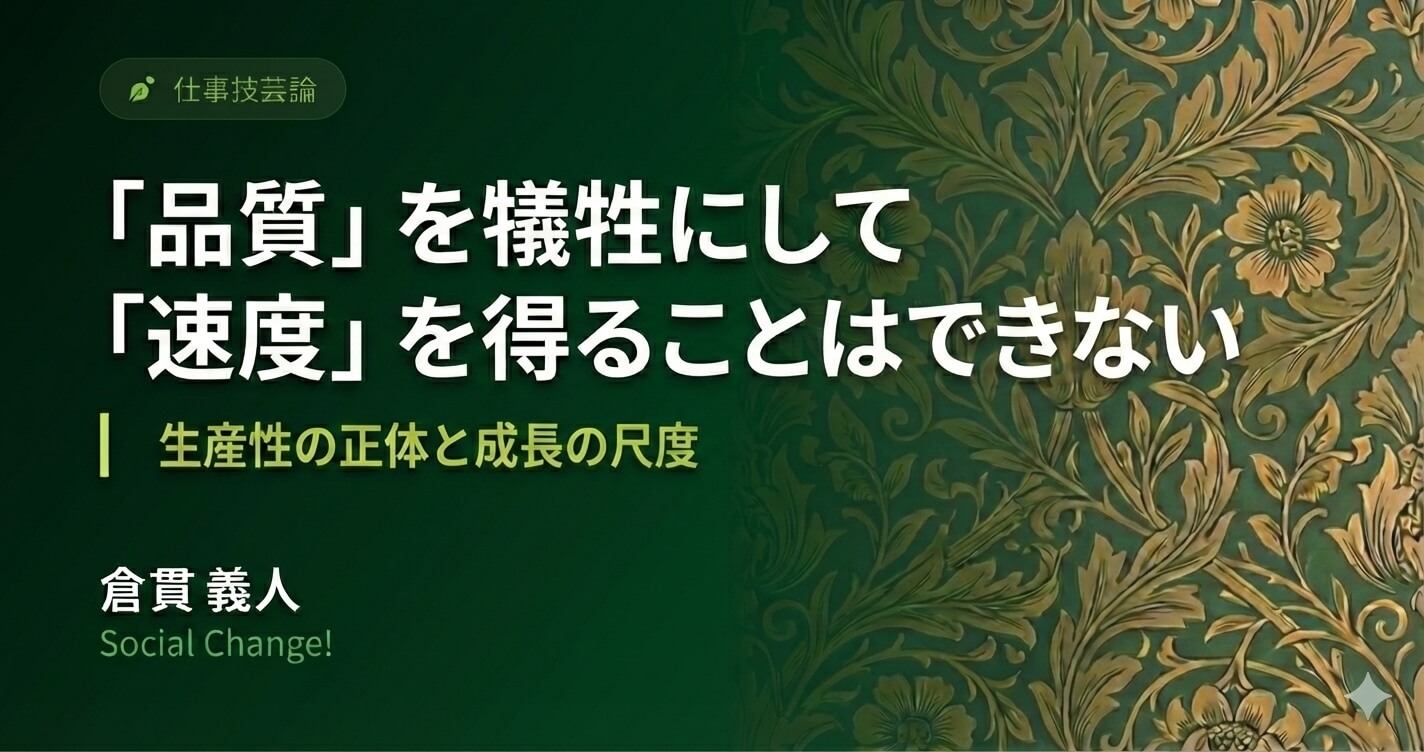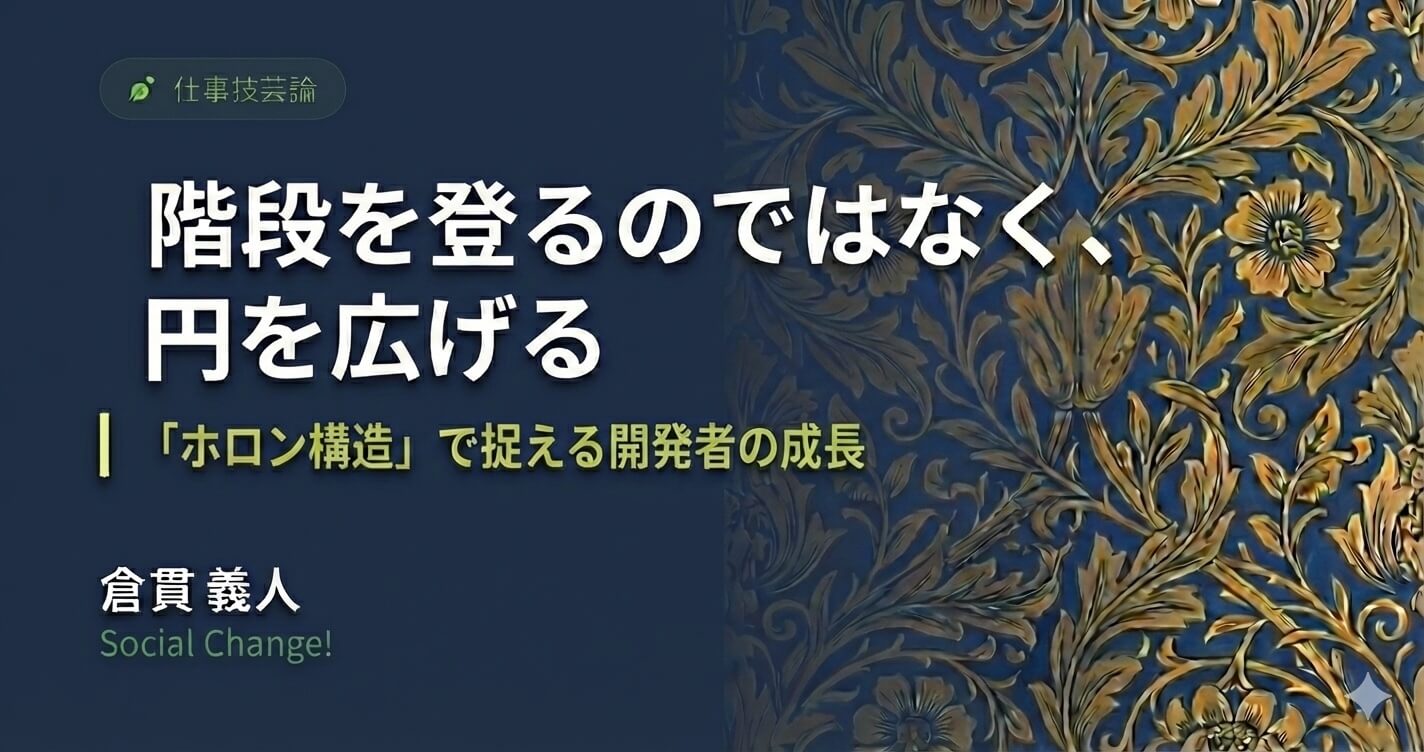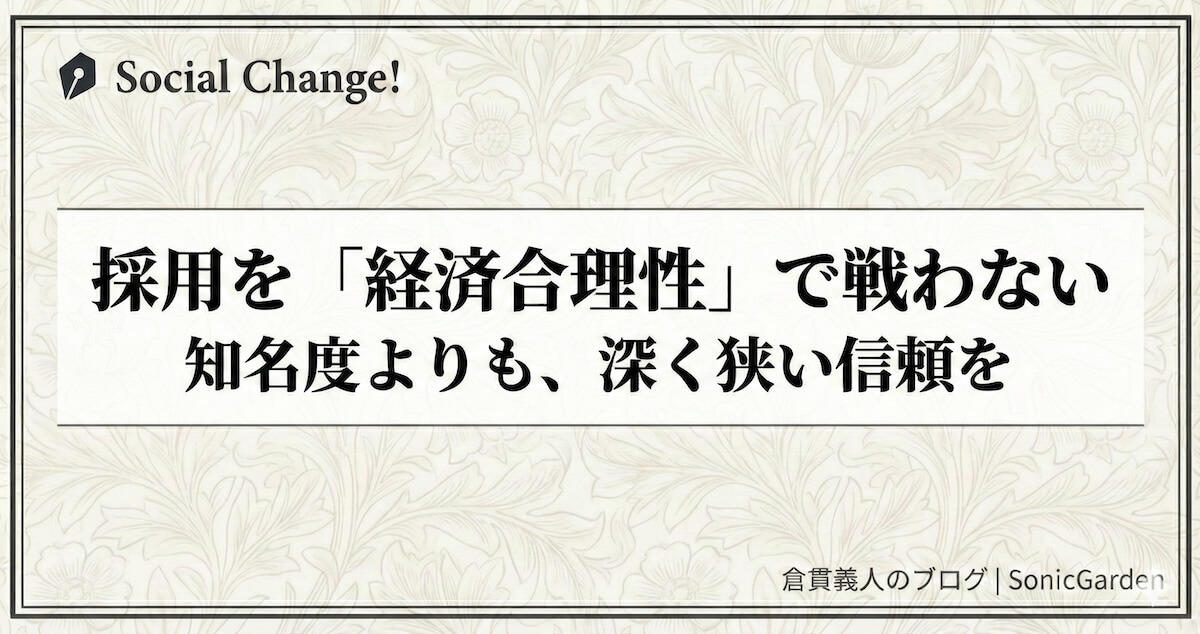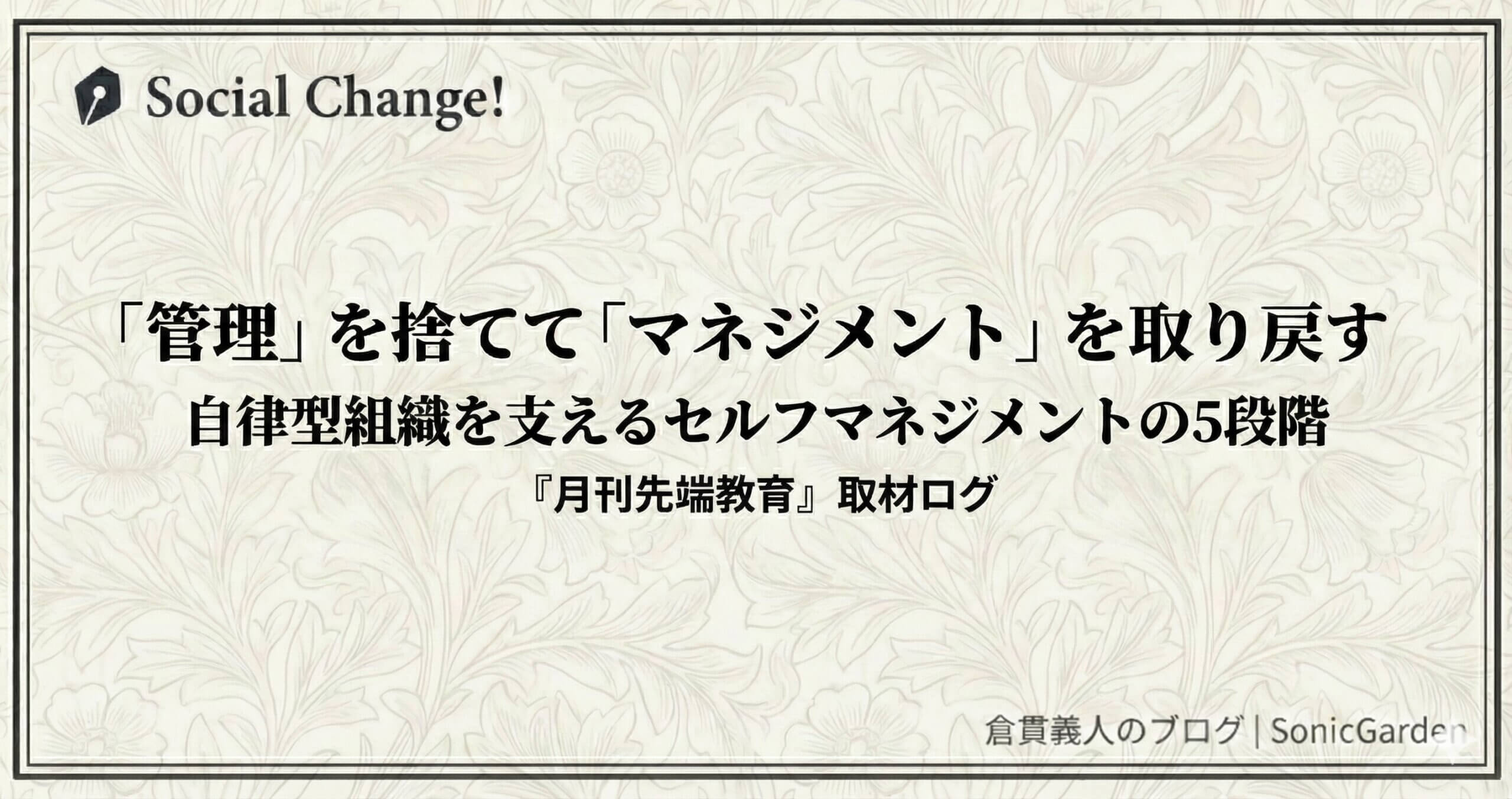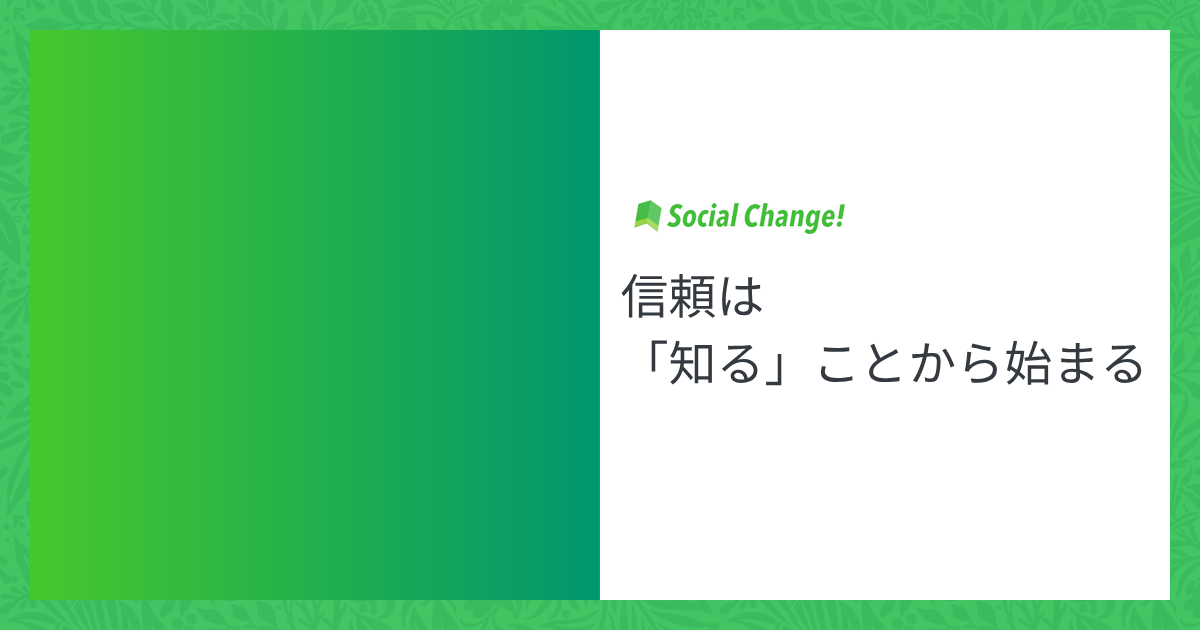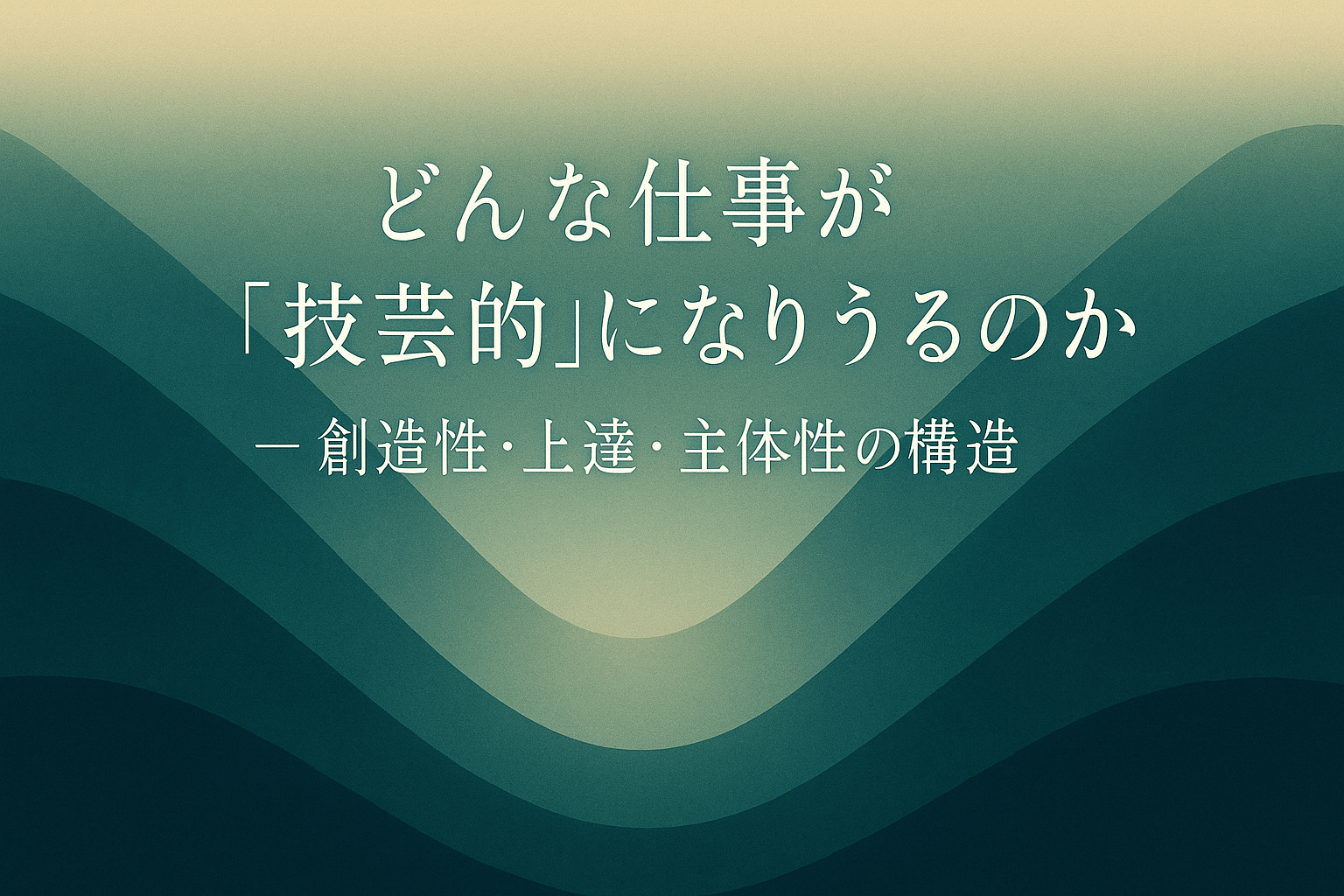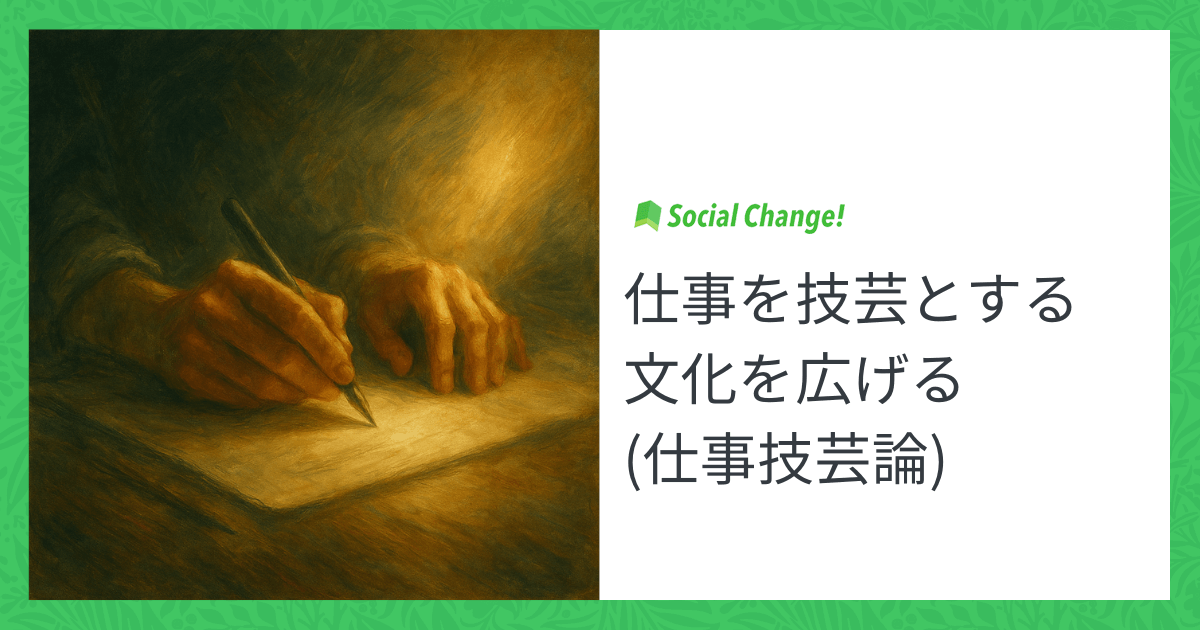
仕事を技芸とする文化を広げる(仕事技芸論)
倉貫 義人
ここ最近、徒弟制度についてお話しする中で、私たちがソフトウェア開発(プログラミング)をスポーツやアートのようなものだと捉えているという点に、業界や職種を超えて少なくない方々が共感してくださいました。
私も含めて、その人たちは、仕事を通じて学び、工夫し、上達していくことに喜びを見出しています。そんな私たちに共通しているのは「仕事を技芸とする」思想ではないかという仮説を得ました。
そして改めて「仕事とは何か」という問いに向き合うようになりました。そこから、仕事を労働として見る世界観と、技芸として見る世界観の違いが見えてきたのです。
仕事は労働なのか
私たちは、普段「仕事」という言葉を、ほとんどの場合「労働」と同義で使っています。仕事とは報酬を得るための行為であり、時間を提供して金銭を得るもの。生活のために働くという考え方が、社会の大部分を占めているのが現実です。
その世界観では、仕事は苦役であり、できれば楽をして早く終わらせたい。多くの人にとって、仕事とは「やらなければならないこと」であり、生きるための義務のように位置付けられています。
効率よく成果を出すことが良しとされ、成長や挑戦はむしろコストやリスクと見なされる。そこに仕事の楽しさを見出す余地はありません。
しかし、現代社会では、そうした「労働」としての仕事では説明しきれない働き方が増えています。
創造性が求められる再現性のない仕事が増える中で、新しいものを生み出し、より良くしようと工夫を重ねる。そのような仕事は、働く人にとって喜びを得られる行為にもなり得ます。
同じ「仕事」でも、苦役と捉えるのか、喜びを感じるのか。その違いはどこにあるのか。私は、それは仕事を「労働」として見るか、「技芸」として見るかの違いにあるのではないかと考えています。
技芸とは何か──技術と芸術のあいだにあるもの
仕事を技芸として捉えるとは、どういうことなのか。労働と技芸の違いは、単に「楽しさ」の有無ではありません。技芸とは、成果よりも「過程」に価値を置き、人が上達していく営みです。
技芸とは、文字通り「技」と「芸」のあいだにあります。技術は精密さと再現性を重んじ、芸術は感性と自由を求めます。技芸はその中間にあり、再現性を大切にしながらも、単なる再生産では終わらない。型を磨き、工夫を加え、自分の表現へと昇華していく。
エンジニアリングとアートを架橋するもの、それが技芸です。
技芸には「型」と「上達」という二つの構造があります。型は、受け継がれてきた知恵や美意識の結晶です。初心者は型を学び、やがて自分なりの型をつくり、型を超えていく。その繋がりが文化となります。
そしてもう一つが上達です。技芸の世界では、熟達を目指して終わりのない成長があります。他者と競うのではなく、過去の自分と比べて進歩しているかを問うのが技芸の道です。
どんな技芸も最初は遊びから始まります。そこから修練を重ね、価値を生み出し、やがて再び遊びに戻っていく。上達するほどに、自由に扱えるようになり、自由自在になるほど面白さは増していくのです。
仕事を技芸として捉えるということ
私たちソニックガーデンでは、以前からソフトウェア開発を「技芸」として捉えてきました。なぜなら、マニュアル通りに進めれば終わる仕事ではなく、自ら考えた創意工夫と実践経験が求められる仕事だからです。
プログラミングを通じて試行錯誤を重ね、自らの思考力や設計力を鍛え、チームとともにより良いものをつくる。この過程はまさに修練であり、一方で遊びのような没頭の時間でもあります。
そんな私たちの仕事には絶対にトレーニングが必要で、より早い上達のために先輩から学び、仲間と磨き合いながら成長していく。通底しているのは「仕事を技芸とする文化」です。
技芸であれば、徒弟制度で人を育てることも自然なことに思えます。高卒採用で若いうちから取り組めるようにすることも、働く前から学ぶことができるトレセンがあることにも繋がります。
技芸とは、成果だけでなく、つくる過程そのものにも意味がある世界です。結果さえ出せば良いわけではなく、作り方やプロセスにもポリシーがあり、守るべき型があります。正射必中の精神が求められます。
そして、会社の中だけのキャリアと違い、技芸としての上達には終わりがありません。どこまでも追求できるものに仕事が変わります。仕事を技芸として捉えることは、働くことを単なる生産行為から、学びと成長の営みに変えることなのです。
上達で得られる喜び
仕事を技芸とする考え方ができるようになると、仕事そのものが喜びに変わります。仕事はもはや苦役ではなく、自らを高めていく取り組みになります。それが報酬にもつながる。これほど幸せなことはありません。
仕事を技芸とする文化には、大きく二つの要素があると考えています。ひとつは「仕事を通じた成長」、もうひとつは「仕事で遊ぶ体験」です。まず、成長について考えてみます。
仕事を労働として捉える世界観では、成長することは目的になりません。むしろ、同じ仕事をより早く、より楽に終わらせることが評価されます。コストパフォーマンスだけを考えるなら、成長など目指す必要はありません。
しかし、技芸の世界では逆です。経験を積むほどに上達し、上達するほどに難しい仕事に挑戦できる。そこにこそ喜びがあります。そして上達によって結果が出るようになれば、自然と報酬も高まることもあるでしょう。
心理学者チクセントミハイの提唱する「フロー」の状態も、上達の過程で訪れます。上達の喜びは、成果以上に内面的な充足をもたらします。誰かが与えるものではなく、自らの鍛錬の結果として得られるものです。
仕事で遊ぶということ
もうひとつ、「仕事で遊ぶ体験」というのも、技芸的な仕事ならではの感覚です。仕事を通じて仲間を作って、チームワークを発揮し、それで大きな成果を出せることは、真剣に取り組む遊びみたいなものと言えます。
私たちソニックガーデンでは「遊ぶように働く」という言葉を大切にしています。誤解のないように言うと、これはサーフィンや旅をしながら仕事をすることでもなければ、まして適当な感じで働くという意味でもありません。
私たちの言う「遊ぶように働く」とは、本人たちは真剣に仕事に取り組んでいるのに、周りの人から見ると、まるで遊んでいるかのように楽しそうに見える、という状態を指しています。
仕事を技芸として捉えることで、仕事の中に成長の喜びを見出し、没頭できる。だからこそ、「遊ぶように働く」が実現できるのです。
真剣に働くことと、楽しんで働くことは矛盾しません。むしろ、技芸的な仕事ほど、その二つが一致するのだと思います。
仕事を技芸とする文化が広がる社会へ
仕事を技芸として捉える考え方は、個人の働き方の範囲にとどまりません。成長と没頭の喜びを軸にした働き方が広がれば、社会そのものが変わっていくはずです。
仕事を労働とする時代には、成果と効率がすべてでした。しかし、技芸の時代には、学びと創造が価値になります。
働きながら成長し、上達し、喜びを得る。それは組織よりも個人の幸せに繋がる仕事観ですが、それが結果として大きな成果にも繋がって、社会を豊かにしていくはずです。
私は、仕事を技芸とする文化を広げることが、仕事が好きで一生懸命に働きたい人にとっての福音となり、その人の人生の充足やウェルビーイングにつながると信じています。
仕事を通じて人が育ち、学び合い、互いに良い影響を与え合う。そんな文化を育てていきたい。仕事は苦役ではなく、生きる上での喜びになる。そんな世界が、少しずつでも広がっていくことを願って、これからも私にとっての仕事を続けていきたいと思います。