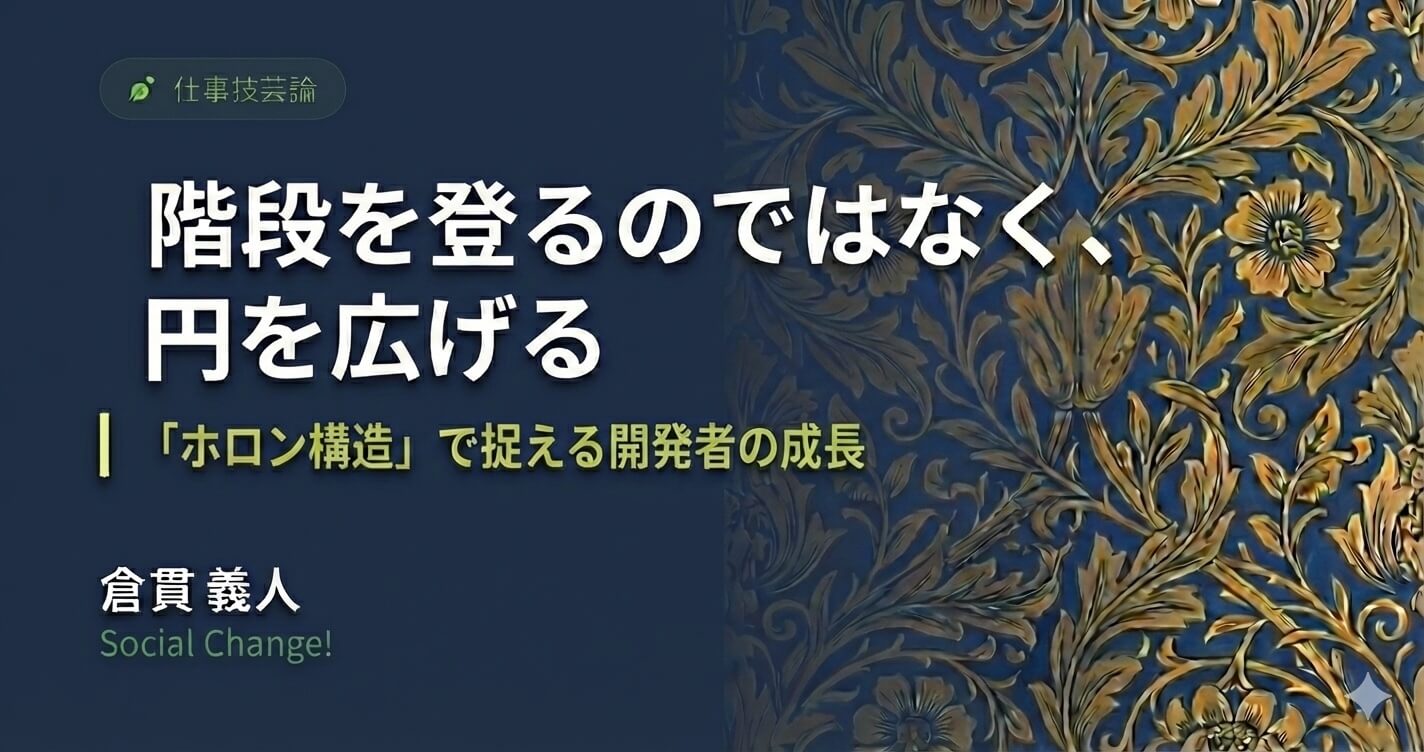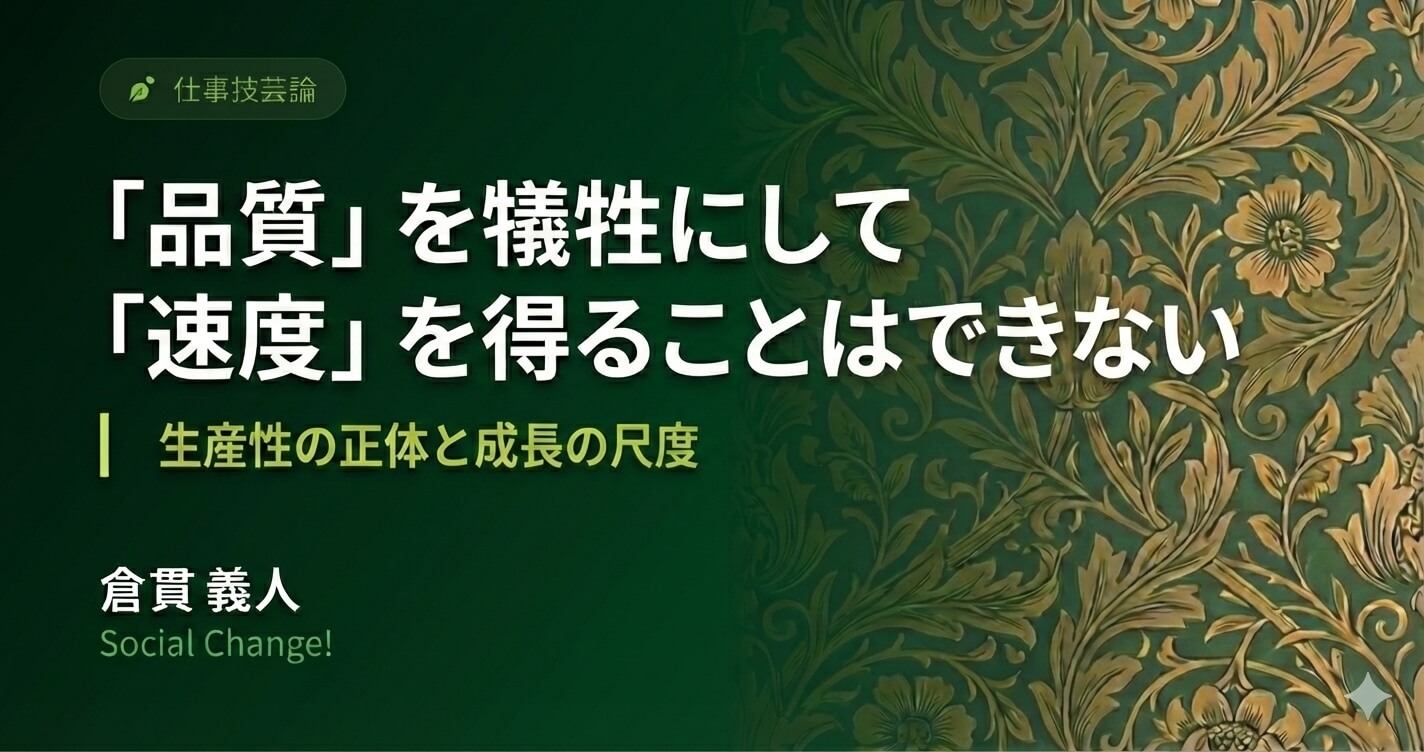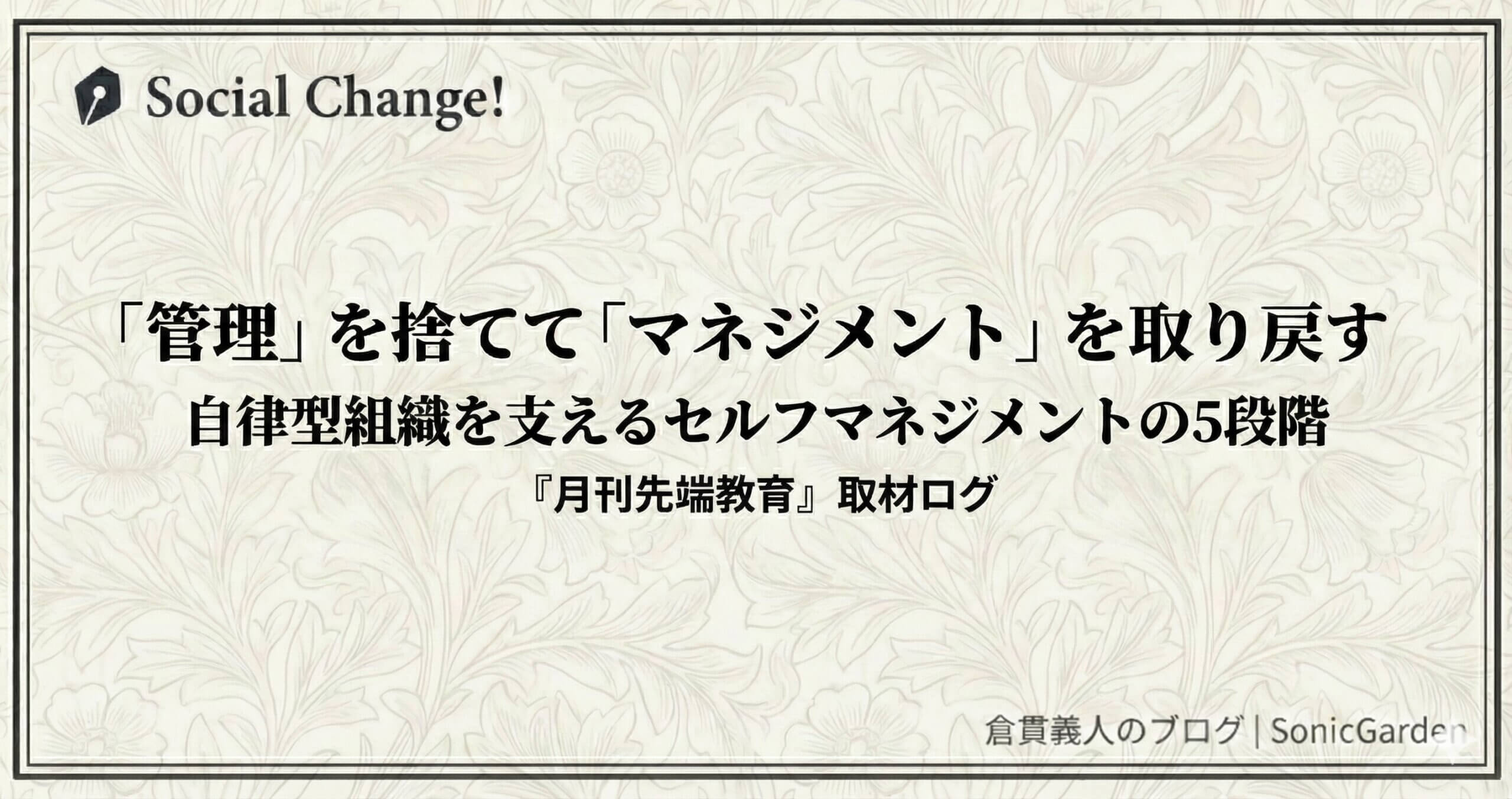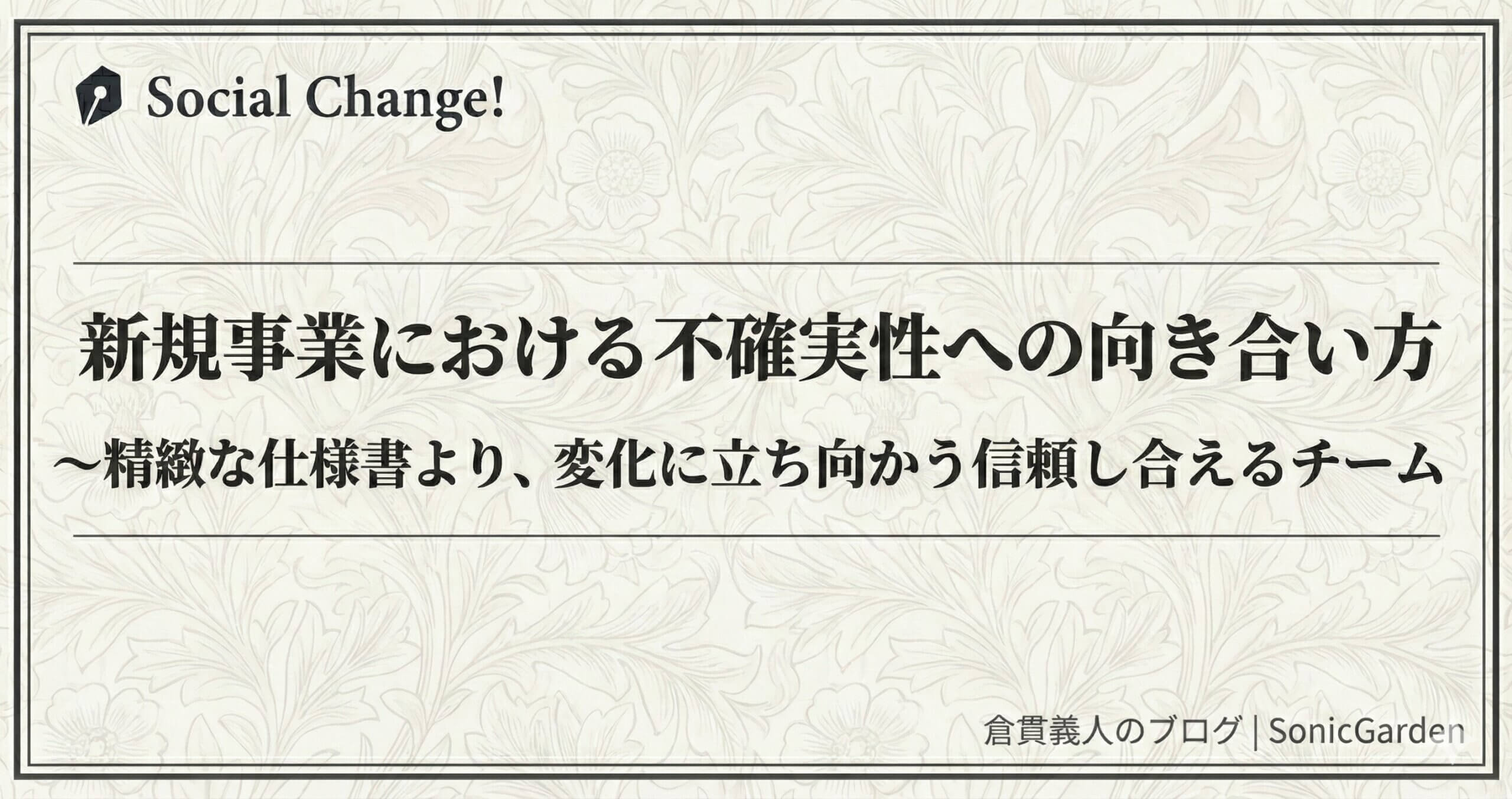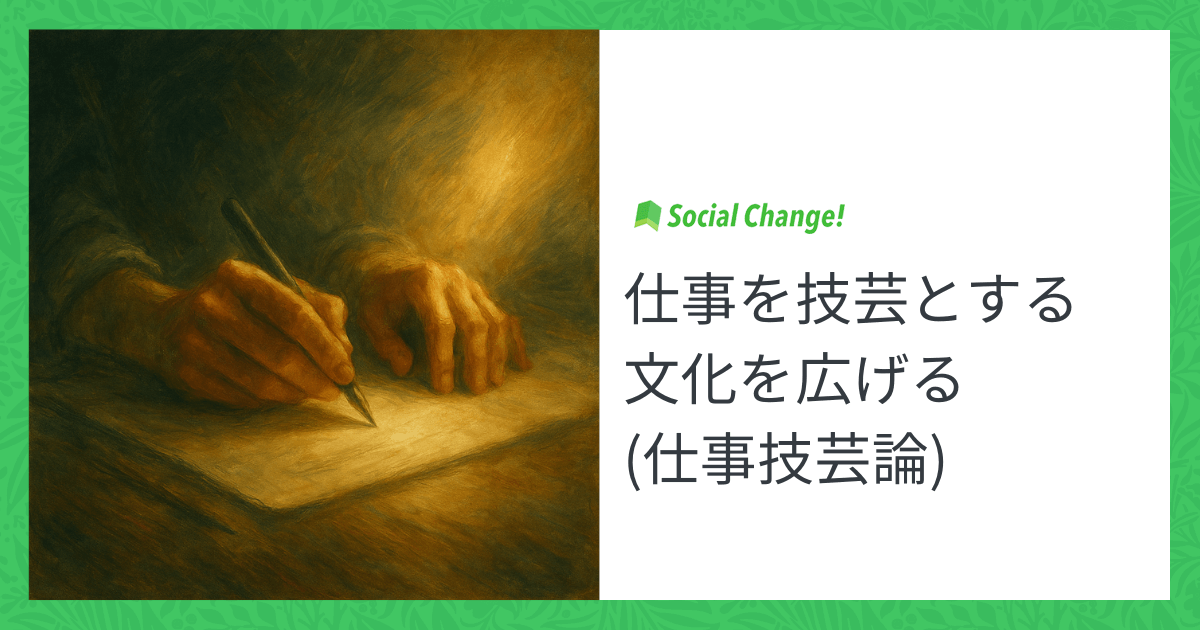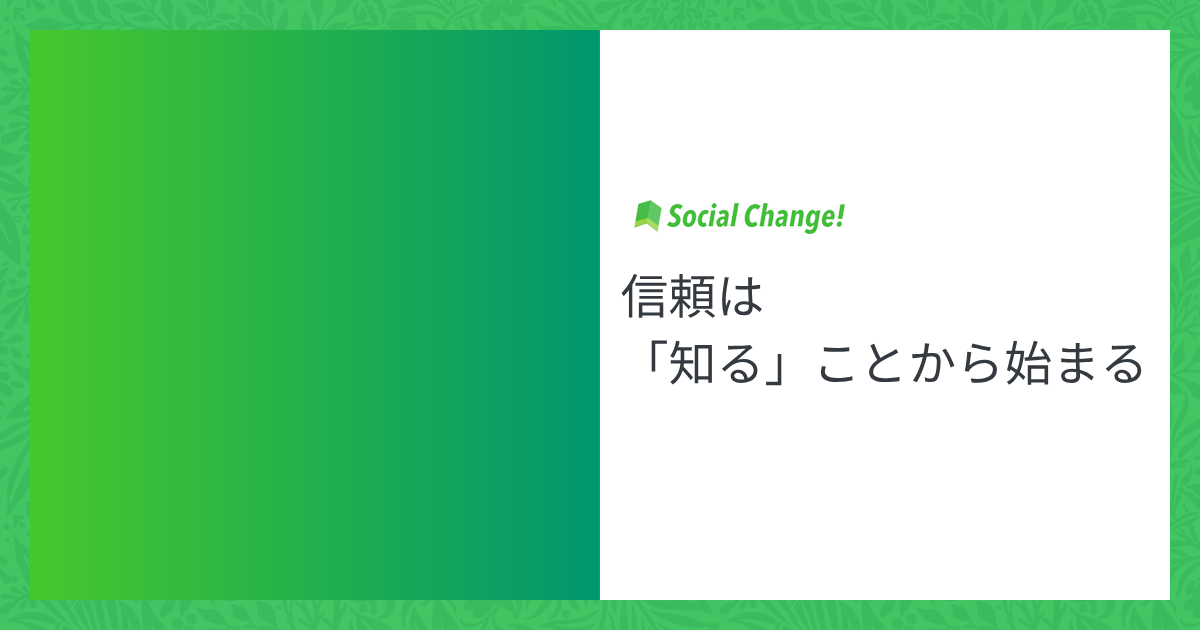
信頼は「知る」ことから始まる
倉貫 義人
信頼関係の築き方について、最近よく考える機会がありました。
クラシコムではマネージャとメンバー、ソニックガーデンでは親方と弟子──それぞれの関係を通じて、信頼とは何かを改めて考えました。
信頼とは、「すごい実力があること」ではなく、「想定どおりであること」なのではないか、ということです。
思っていたよりできた、あるいはできなかった、ということではなく、想定したとおりにできること。想定したとおりの反応が返ってくること。そこに安心感があり、それが信頼の本質ではないかと考えました。
できないことや、少し苦手なところがあっても、それを理解している相手のほうが信頼できます。
だからこそ、全国どこでも同じ品質を保つチェーン店は信頼できる。期待より高すぎても低すぎても、不安定だとしたら信頼とは言えません。
予測可能性が高い、とも言い換えることができます。予測とは違うことをすると、信頼を裏切られたと感じる。予測可能性が高い状態を作ることが信頼に繋がるのではないか、と考えています。
だから、毎日決まった時間に出社するとか、そんな小さな約束を守る回数を増やす方が、1回の大きな嬉しいサプライズよりも信頼を貯めることができるのです。
メンバーや弟子から信頼されるマネージャや親方には、判断の軸があることが求められます。たとえ言うことが変わることがあっても、根っこの部分を知っていれば、安心できる。あるいは、その根幹の部分を理解できていれば、多少の変化にも揺らがない信頼が生まれます。
そう考えると信頼とは、つまり「知る」ということに立脚しているのだと思い至ります。予測や想定の前提には知ることがあります。
よく知っていれば、それは信頼に足る。毎日顔を合わせることで信頼が深まるのも、お互いのことをより知る時間が増えるからです。だからこそ、親方と弟子は近くで働くほうが良いと再確認できます。
親方によく言うのは、まずは観察から始めてほしいということです。見えていないと、仕事の負荷も難易度も調整できない。弟子にとって、ちょうど良い仕事を渡すことが一番の成長につながるが、そのために必要なことが観察だからです。それも「知る」ことです。
そして親方が弟子を信頼するには、最初は半信半疑から始まります。
疑いつつも、半分は信じて任せてみる。そして、近くで仕事ぶりを見ながら、できること・できないことを知っていく。そうして、少しずつ信頼が積み重なっていきます。信頼できるようになれば、細かく見なくても安心して任せられるようになります。
その信頼を維持するうえで大切なのが「相談」です。弟子は自分だけでは判断が難しいときに相談することで、親方は弟子の考えや状況を知ることで信頼を深めることができます。
一方で、相談したときにきちんと一緒に考えてくれる相手だと分かれば、相談する側の信頼も増します。「相談に乗ってくれる人だ」と知ることが、安心感につながります。
また、マネージャや親方は、自分の考えを言葉で伝えることで信頼を得ます。「背中を見て学べ」だけでは、尊敬はされても信頼までは生まれません。マネジメントにおいて言語化が求められるのは、そのためではないでしょうか。「知らせる」ことも大事なのです。
以前、クラシコムの青木さんから「しらす」という統治スタイルを教わりましたが、「知る・知らせる」を続けることで信頼関係が築かれるのだとすれば、それこそが「信頼によるマネジメント」と言えるのかもしれません。