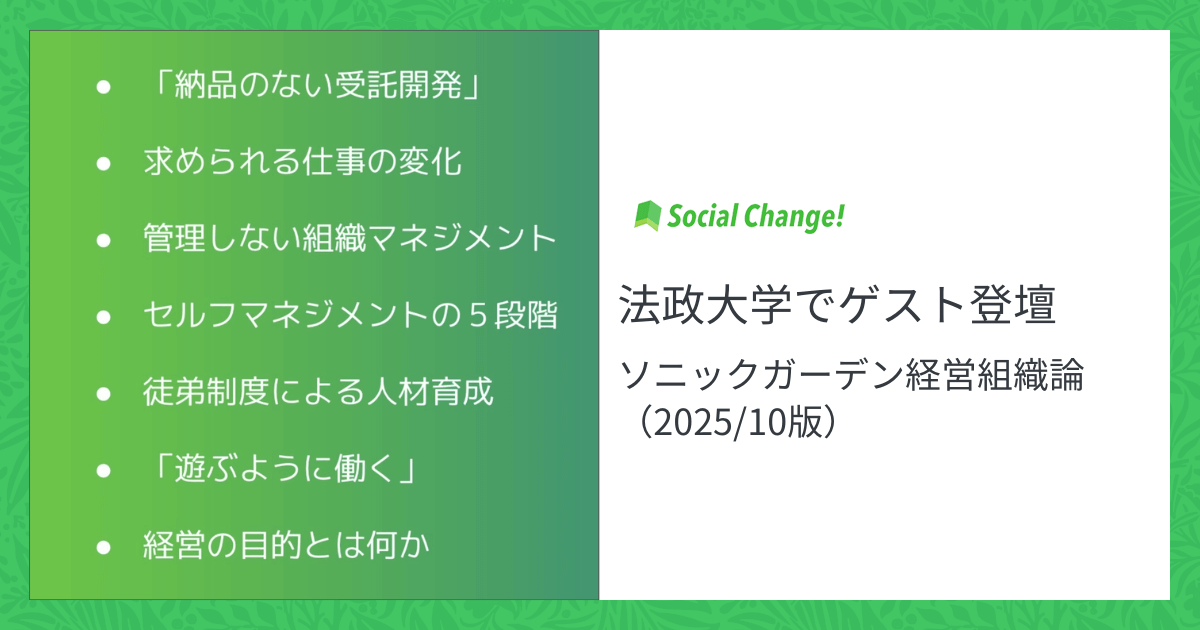採用は『点』から『線』へ──採用と育成を分断しないトレーニングセンター
倉貫 義人
採用活動は、多くの企業にとって難しいテーマです。特に新卒採用では、数回の面接や試験といった「点」で候補者を判断せざるを得ません。
本当に合うのかどうか入社して働いて見るまで分からず、結果としてミスマッチが生じてしまうことも起きてしまいます。これでは企業と応募者の双方にとって、ギャンブルのようなものです。
私たちソニックガーデンも、新卒採用においては同じ課題を抱えていました。これまでベテランの採用にはもともと時間をかけて入社前後のギャップを無くすようにしていたのですが、新卒採用では時間をかけるのが難しく、どうしても「点」での判断になりがちでした。
しかし、本質的には新卒採用であっても時間をかけて判断したい。そのためには、採用と育成を分断しない発想に辿り着きました。それによって「点」ではなく「線」で見ることができるのではないかと考えました。
面接の限界──「点」の判断はミスマッチを招く
入社した後は、日々の業務を通じたフィードバックで育成をしていくことになります。それは定期的に行われる訳ではなく、普段から一緒に過ごす中で機会を与えて、結果ではなくプロセスを見ていくことです。
つまり、入社後は「点」ではなく「線」で見ていることになります。
それなのに新卒採用の段階では、短時間の面接や筆記試験といった「点」での判断にならざるを得ませんでした。そこに矛盾があります。
特定の瞬間だけだと、自分を取り繕うこともできるし、短時間なら我慢もできるでしょう。しかし、仕事が始まれば、1日は長く、それがずっと続いていくので、自然体でいられなければ、続けることはできません。
応募者にとっても、無理しないでいられる会社を選ぶ方が良いのですが、無理しても面接や試験をクリアすれば良いと考えてしまいがちです。このように、従来の採用プロセスには構造上の問題があると考えています。
問題の本質──「やってみないと分からない」
そうした問題の解決のために「インターン(職業体験)」と呼ばれる仕組みがありますが、これは職種によっては良い解決策にはなり得ません。
半日や1日の会社見学みたいなものでは表面的にしか知り得ません。また、それでは会社のことは知れても、自分自身が会社や職業に向いているのかどうかまではわかりません。
また、実際の業務を伴うインターンもありますが、例えば私たちのようなソフトウェア開発の場合、本来は未経験に近い人間が担当できるような仕事は無いのです。
かといって誰でもできる雑用があるかと言えば、それはAIや自動化を駆使することによってほぼ存在していません。それに、そもそも雑用に従事しても、本当の職業体験にはならないでしょう。
では、やってみないと分からないことに対して、何をすれば良いのだろうか。私たちにとっては、それが訓練による育成なのだと考えました。
発想の転換──採用を「線」で捉える
私たちソニックガーデンの場合はソフトウェア開発ですが、こうした再現性の無い仕事は技芸のようなものであり、マニュアルや座学で学べる「研修」だけでは身につきません。
技芸だとすれば必要なのは、実際に手を動かしながら身につけていく「訓練」です。そして仕事として一定以上の価値を出すためには、それだけの訓練をしていなければならないのです。
そのために、最初に取り組むのは「訓練」であり「練習」です。
実際に入社しても、いきなり業務ができないので訓練を受けてもらいます。研修ではなく、Railsアプリを何度も開発するような訓練です。その期間は、数日や数週間でなく、もっと長い期間がかかります。
であれば、採用段階から訓練に取り組むことで、その人と一緒にやっていけるかわかるようになるはずです。そして、これは「線」で見る採用プロセスになります。試験や面接よりも、応募者側にしてもやってみてわかることがあるでしょう。
何よりも、その仕事が自分に向いているかどうかは、実際にやってみて判断ができます。その際のポイントは、没頭できるか、続けられるか、の2点です。それが、ソフトウェア開発の職人となるための適性です。
この採用と育成を同時に進める職人養成機関を「トレーニングセンター(トレセン)」と呼ぶことにしました。
採用と育成を統合した「トレセン」
トレセンは、採用プロセスであると同時に、育成プロセスでもあります。一方で、研修ではないので、講師がいて教材があり学んでいくようなものではありません。課題を元に解決していく形です。
以下の特徴があります。
1)実践課題への取り組み。トレセンに参加する訓練生は、課題を与えられて、解決していきます。解決するために必要な学習は、自ら学びます。これは、現実のソフトウェア開発の仕事に近い形です。
2)自学自習とトレーナー。基本的には、訓練生には自走していくことが求められます。その前提の上で、現役のプログラマがトレーナーとしてついて、レビューしたり、相談に対応します。
3)関係構築のプロセス。応募者でもある訓練生は、トレーナーとの関係構築を通じて、会社や仕事のことを理解していくことになります。それによって、文化を伝えていくことができます。
私たちにとっては、働くことは「お金を稼ぐ」だけではなく「トレーニングする」ことも含まれているのです。入社直後は誰もがトレーニングから始まります。ならば入社前に訓練を積むことも、働くことの一部と考えられるはずです。
なぜいきなり徒弟制度ではないのか
ソニックガーデンには「徒弟制度」という仕組みがあります。親方と弟子という関係の中で、案件を通じて学んでいく制度です。
しかし、いきなり新卒を徒弟制度に入れるのは難しいのが現実です。
徒弟制度は会社にとっても大きなコストをかける仕組みですし、弟子になる当人には「一生やっていく」くらいの強い覚悟が求められます。
さらに、徒弟制度は案件を通じて学ぶことが前提です。そのためには、最低限案件で役に立てる程度の技術力が必要です。ところが、多くの新卒はその基準を満たしていません。
その徒弟制度に入るための段階が、トレセンになります。よって、トレセンのゴールは、徒弟制度に入れるくらいの技術力を身につけることです。
そして、そのためには何度も繰り返し開発を続けていくしかありません。
応募者にコストをかけてもらう理由
一般的には「応募者に負担をかけない」のが採用の常識です。
しかし私たちは逆に、トレセンへの参加という形で候補者にも大きなコストをかけてもらうことを前提としています。もちろん、こちらも現役社員をトレーナーにつける以上、大きなコストを負担します。
そのように、お互いが投資し合うからこそ、本気の判断ができると考えています。
また、採用は会社が見極めて判断を下すものだと思われていますが、本来は、相互に良いかどうか見極めるべきものです。私たちは、トレセンに進めるかどうかは判断するので内定は出しますが、その後は応募者本人の努力と意思で決まります。
そんな大変なことをせず、コスパ重視で早く内定だけが欲しいという人には、この形式は向きません。
ただ、これも本人の考え方次第ですが、早く内定をもらう理由に安心を求めているのだとしたら、それは本当の安心とは言えないのではないか、と考えています。むしろ時間をかけてでも、成長できた方が本当に安心できるのではないか、と。
しっかり成長することができれば、たとえ時間がかかっても、どのような会社からも選んでもらえる存在になれるはずです。
採用と育成を分断しないで得られること
従来の新卒採用は「点」での評価に頼らざるを得ず、育成とは切り離されていました。あくまで入社前は「点」であり、入社後になってから「線」になります。
私たちソニックガーデンのトレセンでは、この分断をなくして、採用と育成を一本の線で接続する仕組みです。
候補者は、訓練を通じて自らの適性を確認することができるため、徒弟制度に入っていく際のミスマッチを防ぐことができるのではないかと期待しています。大事なことは、会社が見極めるよりも、本人が自分と向き合う機会と時間を用意して、自ら決めることです。トレセンは、その機会になります。
こうした取り組みができるのも、私たちには採用ノルマがなく、たとえ採用人数が0人でも良いとしているからなので、容易に再現は難しいかもしれませんが参考になれば幸いです。