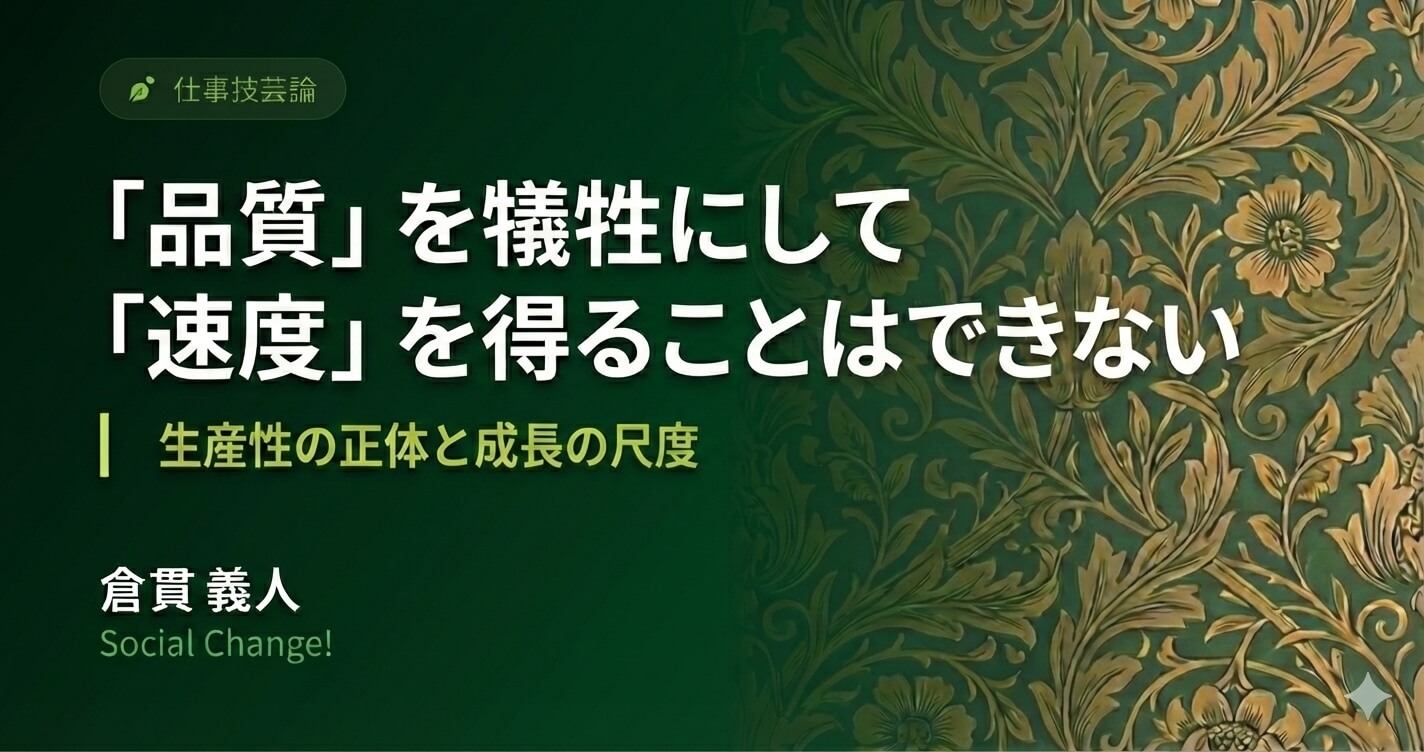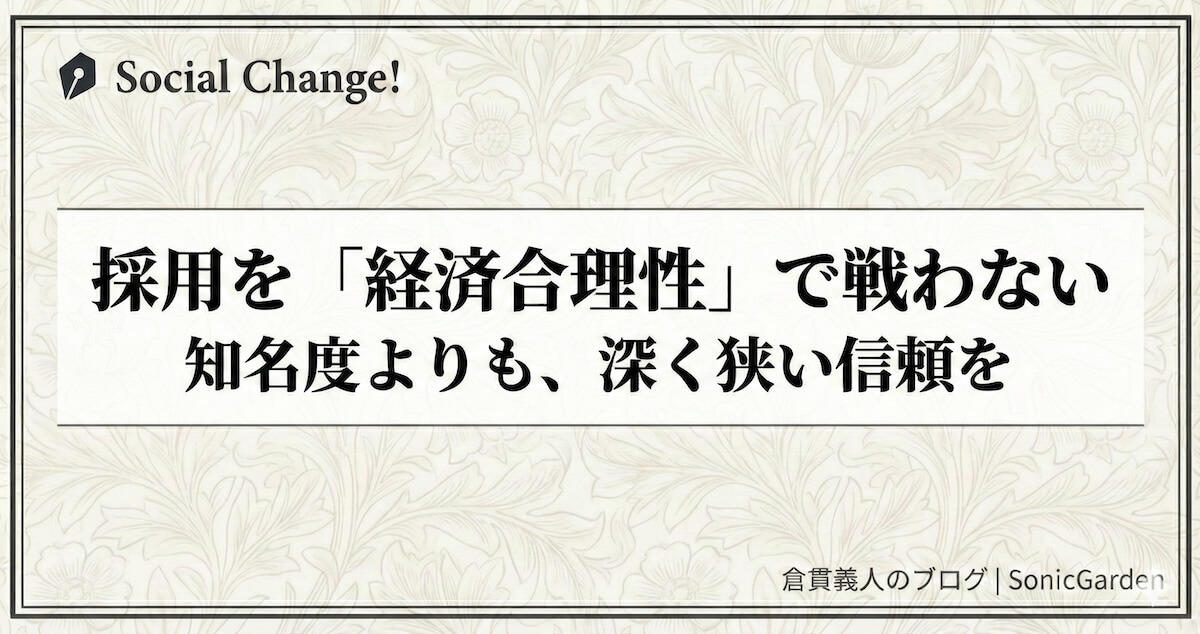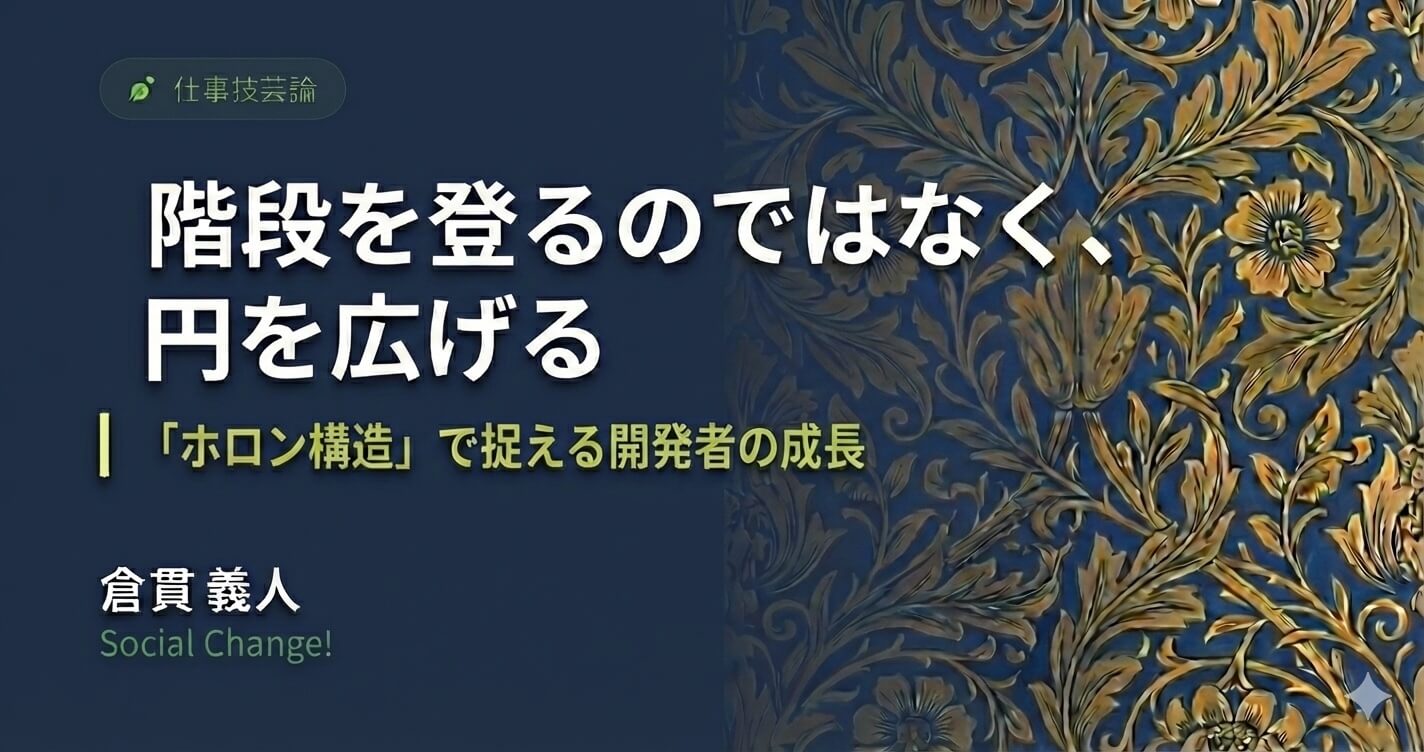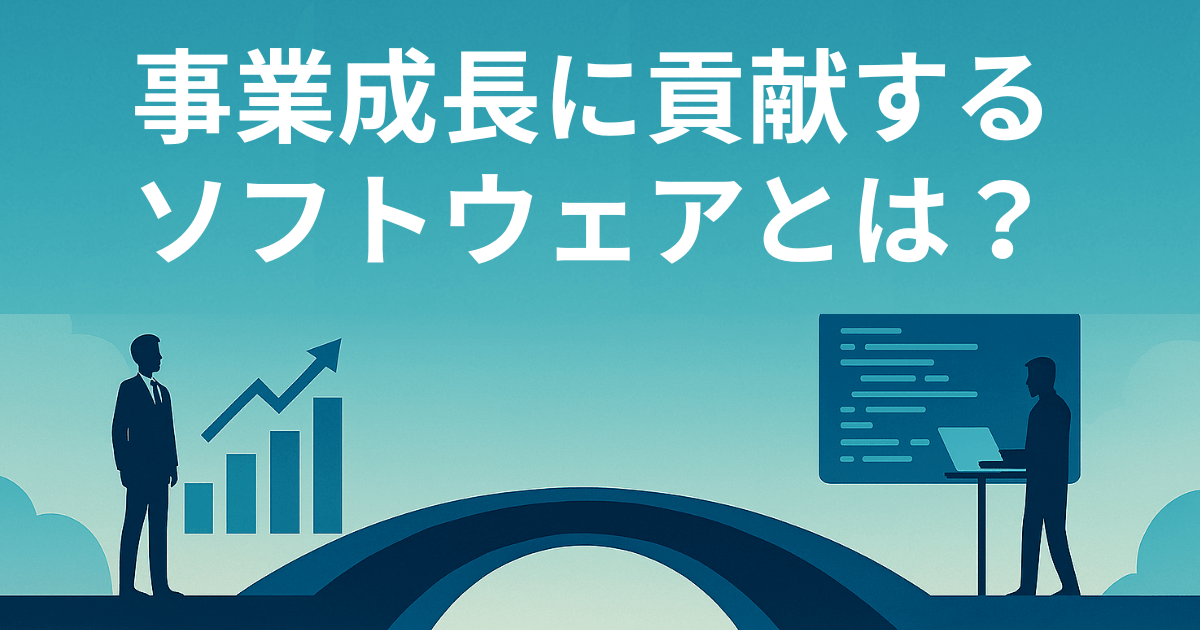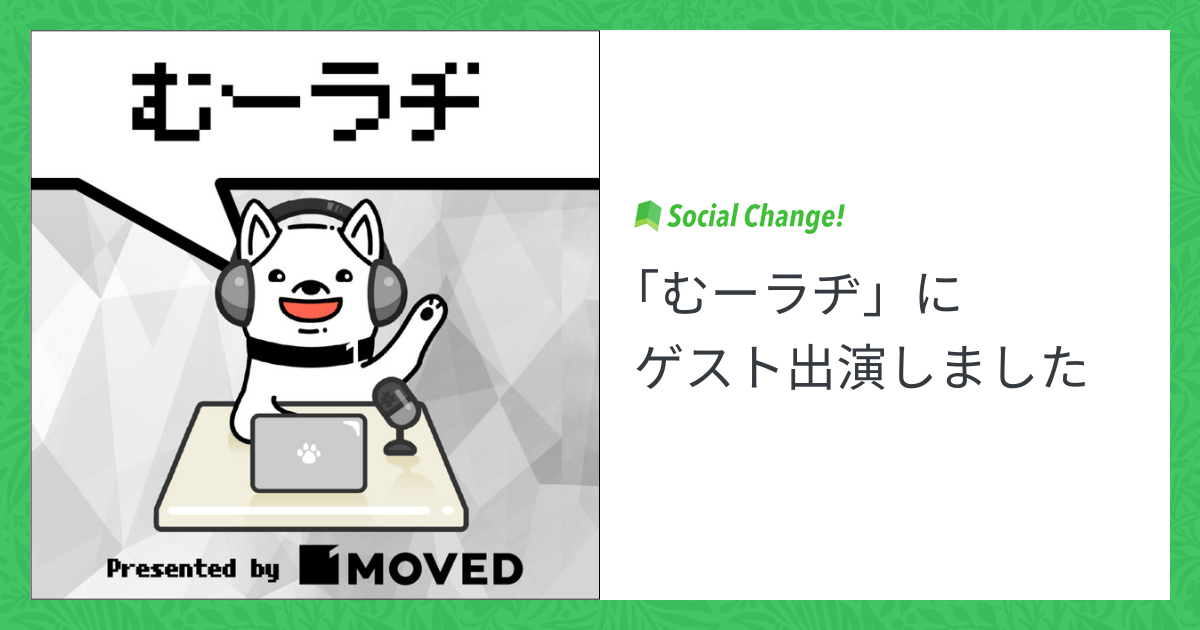育成に必要なのは「観察」と「自己決定」〜人が自ら育つために、育てる側ができる本質的なこと
倉貫 義人
育成において肝となるのは、「育ちたいという本人の意思」と「育てる側の丁寧な観察」だと考えています。教え込むのではなく、伸びていこうとする力の方向を整えていくことで、人はのびのびと育つことができます。
本稿では、私たちソニックガーデンがエンジニア育成を実践してきた経験から、自己決定と観察の重要性について得られた気づきを記します。
育成は強制できない──自己決定の重要性
育つ気のない人をその気にさせるのは基本的には困難です。本質的には、成長は「成長したい」と本人が決めることからしか始まりません。
周囲がどれだけ手を尽くしても、育成の出発点に立つかどうかは、本人の意思にかかっています。まさしく「馬を水辺に連れて行くことはできても、水を飲ませることはできない」のです。
多くのマネージャが、どのようにヤル気を出してもらえば良いのか、話を聞いてもらうにはどうすれば良いのか、と悩むことが多いのですが、それは前提が揃っていないことが原因です。
よって、まずは自分の意思で決めることが大事です。自己決定せず、誰かが決めたことなら、どこかで誰かのせいにしてやめてしまうかもしれません。自分で決めたことなら、その決めたことを正解にするために頑張るでしょう。そうなれば、誰かがお膳立てしなくても、自力で成長していきます。
なぜ「観察」が育成において不可欠なのか
自力で育つ前提が揃いさえすれば、育てる側の仕事は、伸びていこうとする力の“方向”を整えることに集中できます。そのための手段が、本人による実践と育てる側からのフィードバックですが、適切な実践をさせること、それに対して効果的なフィードバックを行うには、観察が欠かせません。
プロセスの観察が第一
観察すべき最も大事なものがプロセスです。たとえば、タスクの進め方、調べ方、質問の仕方、迷ったときの反応、試行錯誤の痕跡なども観察の対象になります。これらを見ることで、理解度や思考の傾向が自然と見えてきます。
人を育てようとする時、結果だけを見てフィードバックしようとしても、うまくはいきません。例えばアスリートの育成で、記録だけを見て、もっと良い記録を出せ、というフィードバックはありえないでしょう。フォームや練習方法を見て、それを改善していくことで上達していくはずです。それと同じことで、結果に至るプロセスを見ていくことは育成には欠かせません。
難易度調整に観察が必要
また、同じことを繰り返しているだけでは、人は育ちません。育成では、少しずつ難しい課題に取り組ませる必要があります。その難易度を適切に設定するには、今の実力やコンディションを正しく把握できるように、観察しておかなければなりません。
いわゆる「フロー状態」と呼ばれる夢中になっている瞬間は、自分の実力と取り組む課題の難易度がちょうどよいところにいることがポイントと言われています。つぶさに観察していることで、フロー状態に導ける課題を出すことができます。
失敗を許容する環境づくり
失敗したからこそ、身をもって大事なことに気付くことができることも多くあります。しっかり観察するのは良いけれど、失敗する前にフォローしすぎると、本当の強さは身につきません。チャレンジがあるから成功体験がある。たとえ失敗しても、何度も試行錯誤を繰り返すことで成功につながる。そうなると失敗ではなく、良い経験といえます。
そこでも観察が重要です。観察していれば、取り返しのつかない失敗にはならないからです。たった一つの正解の方法しか知らないよりも、試行錯誤して身につけた答えの方が、将来に役に立ちます。
浮き沈みに寄り添う
そして人である以上、常に安定しているわけではありません。ときに調子を崩したり、集中できなかったりすることもあります。観察していれば、その浮き沈みに気づき、必要なサポートやフォローを入れることができます。
モダン徒弟制度という育成の実践事例
私たちソニックガーデンでは、エンジニア育成を徒弟制度という形で行っています。ただし、昔ながらの徒弟制度と違い、親方と弟子と言う関係ではあるけれど、現代的なアプローチを導入しています。これを「モダン徒弟制度」と言っても良いかもしれません。
モダン徒弟制度は、以下の3つの原則を軸にしています。
1. 自己決定から始まる関係性
2. 共に働くことで築く信頼と観察
3. プロセスを見せて伝える育成スタイル(守破離)
ソニックガーデンにおいて弟子入りは、あくまで本人の自己決定によって始まります。もしそうした環境を望まないのであれば、弟子にはなりません。これにより、親方と弟子の関係は、前提が揃った状態で始めることができます。
そして、モダン徒弟制度において親方に求められるのが「観察」です。入門後の一定期間は、親方と同じ場所で一緒に働くことを基本としています。信頼関係が築かれるまではリモートワークは行いません。それは、親方が弟子を観察しやすくするためでもあります。
親方は観察を行って、その弟子にとって少しだけ難しい課題を出して、そのプロセスを見守って、一定の失敗も許容しながら、フィードバックをしていきます。中でも、大事なことはプロセスへのフィードバックです。
たとえばコードレビューにおいても、GitHub上でプルリクエストにコメントを残すだけでは、本当に良いコードが書けるようにはなりません。結果だけにフィードバックしても、弟子はどのように直せばよいのか、どう考えればいいのかが分からず、やみくもな修正を繰り返すことになります。それでは良いプログラマには育ちません。
だからこそ、やり方に対してフィードバックを行い、ときにはお手本を見せることが重要です。究極的には、ペアプログラミングを通じてプロセスを直接共有するのが最も効果的です。弟子の初期段階は「守破離」でいう“守”の段階です。自己流に走る前に、まずは親方の型を身につける方が、後々の成長につながると考えています。
正射必中──プロセスにこそ本質がある
私たちは弓道における「正射必中」という考え方を参考にしています。正しく射れば、結果として的に当たる。逆に、的に当たったかどうかだけを見ていても、本質的な上達は望めません。
プログラミングにおいても、ただ動けばいいのではなく、良いプロセスで書かれた良いコードこそが良いソフトウェアにつながります。だからこそ、プロセスを観察し、それにフィードバックすることが育成には不可欠なのです。
このように、育成は「教える」ことよりも、「整える」こと。「管理する」ことよりも、「見守る」こと。自己決定と観察によって、人は本当に育っていくと私たちは考えています。
育成とは、ただ道を示すことだけではなく、共に歩きながら、歩き方を見守ることなのかもしれません。
お知らせ:
ソニックガーデンでの徒弟制度の、弟子たちの実態をまとめた記事を公開しました。