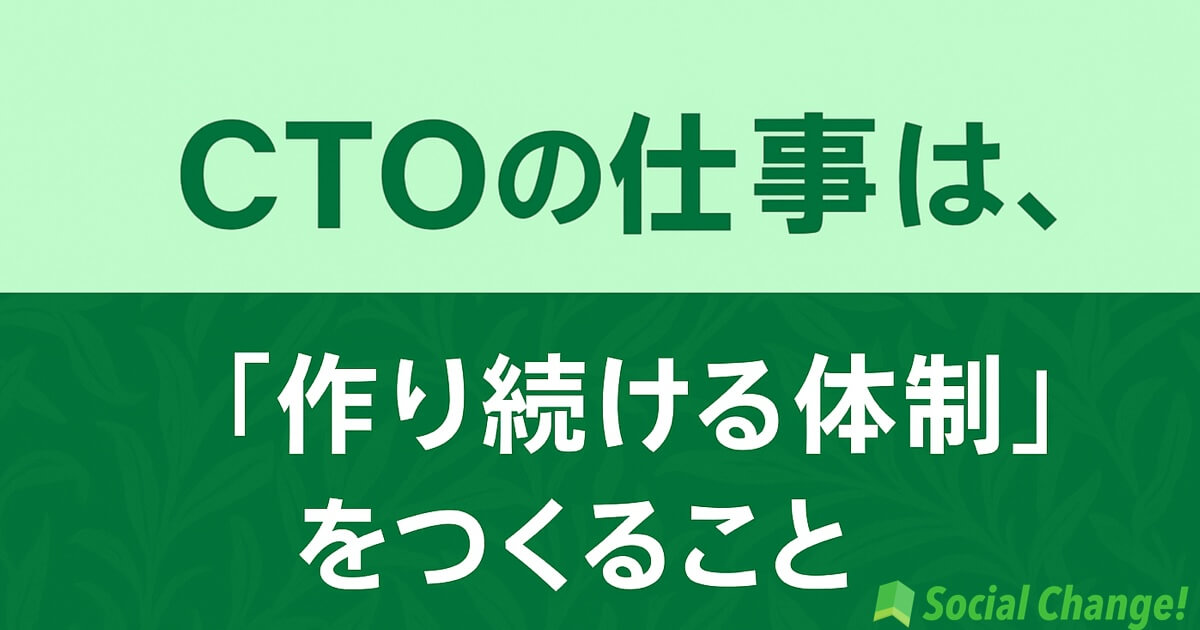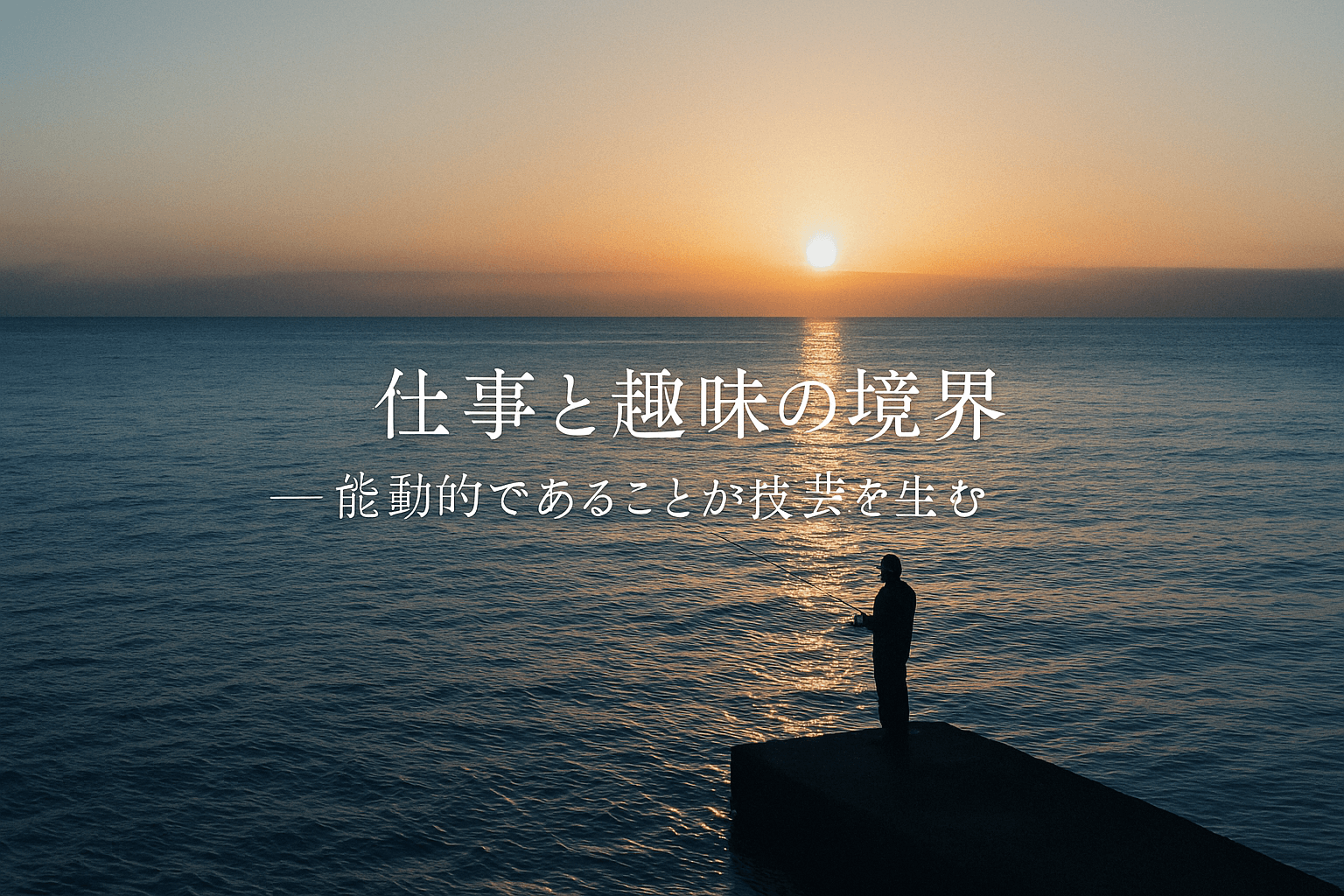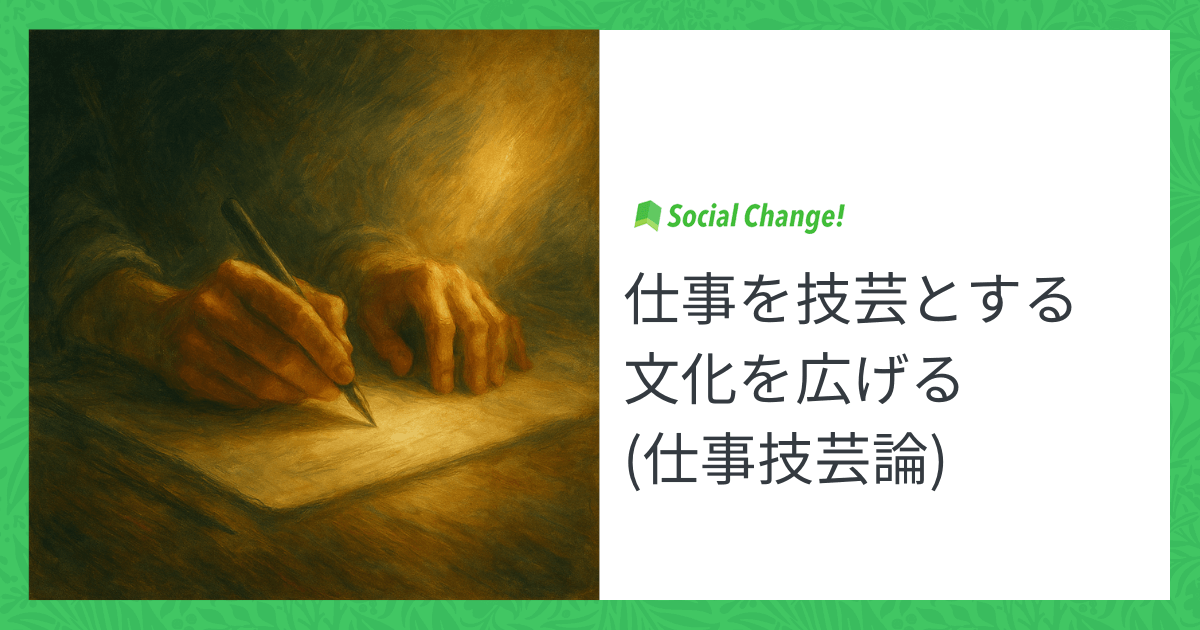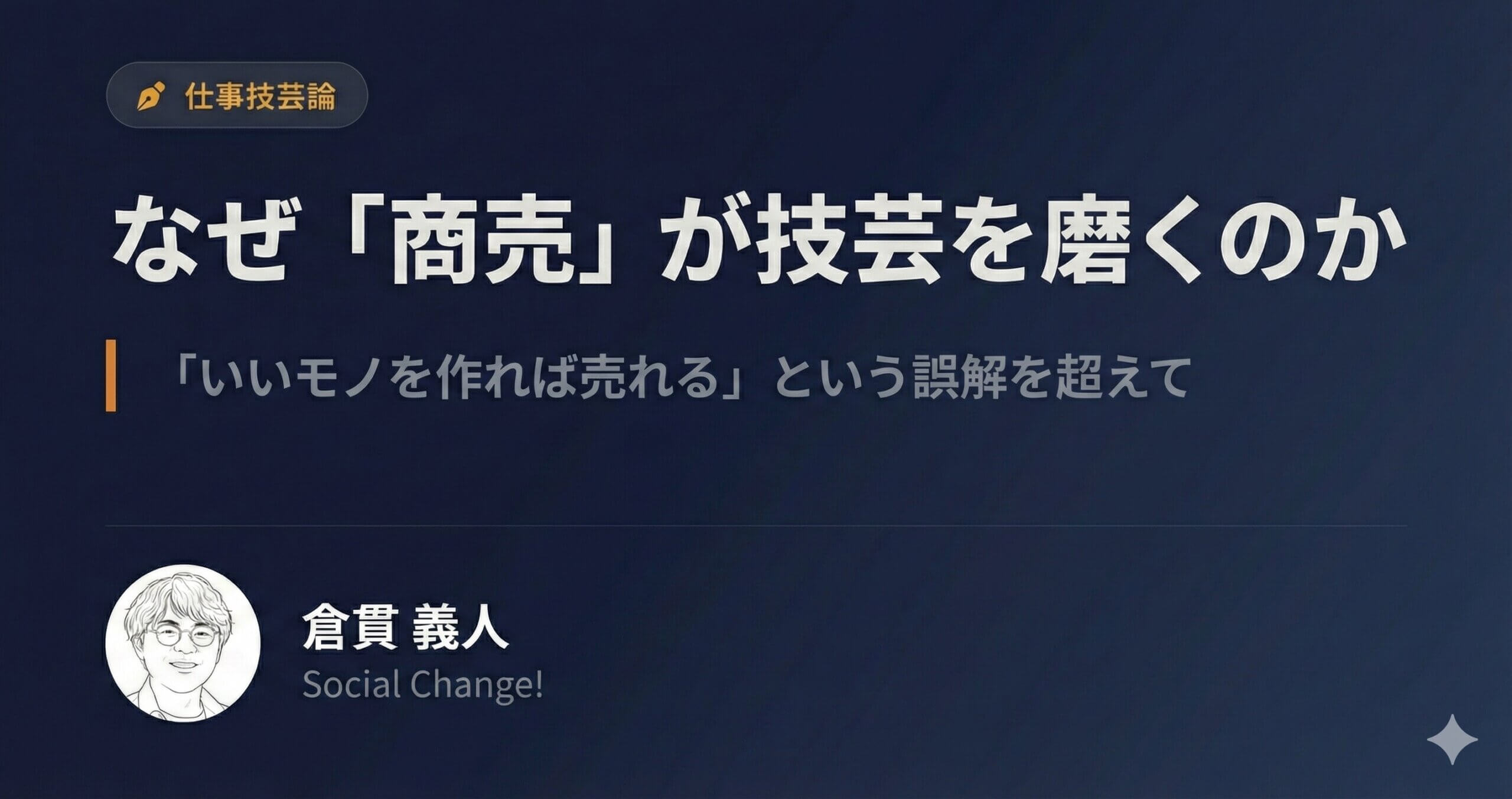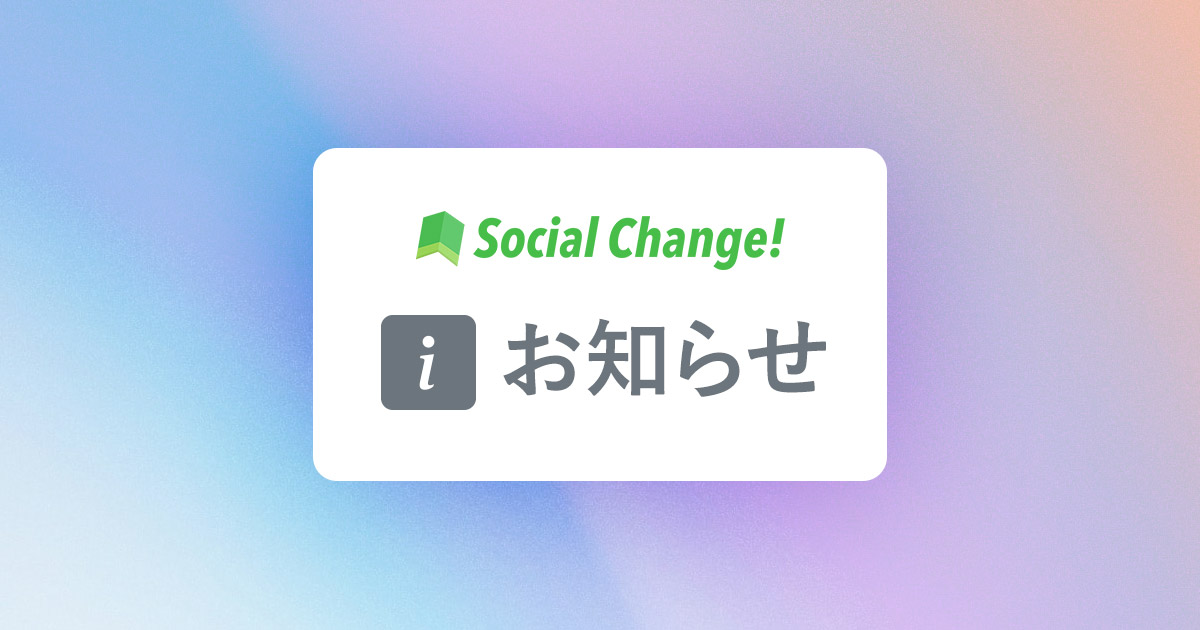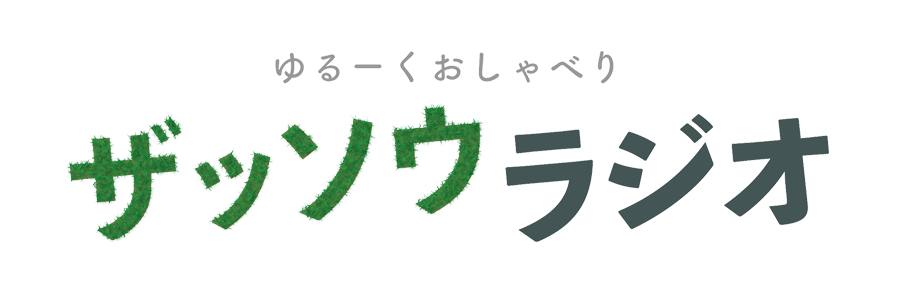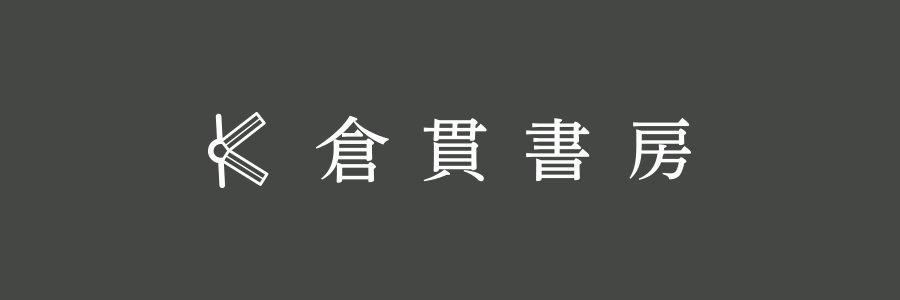クラシコムのCTOとして取り組んできた基幹システムのリプレースが一つ山場を超えたので、そのふりかえりをクラシコムの執行役員たちと実施しました。
「北欧、暮らしの道具店」を支えるシステムは、約10年近く前に当時のエンジニアが一人で作り上げたものを、使い続けてきました。もちろん、少しずつ保守と改修を重ね、セキュリティの不安がない状態に維持してきたからこそ、ここまで使ってこれました。
そこには、内製のエンジニアチームの弛まぬ努力があってこそ。数人の内製チームだけで、上場まで果たせたので立派なものです。
クラシコムのシステムは、ECを担うウェブ部分と、受発注・在庫管理まで担う部分を分割せず、統合されたものとして開発されました。それも業務用のフレームワークやパッケージを使わずに、フルスクラッチで開発して運用してきました。
それによって、メディア展開や商品カテゴリの広がりなど、変化し続けてきたクラシコムの取り組みに対応することができたのだと思います。一方で、複雑化したデータ構造など、未来に向けて更なる改良を重ねていくための課題はありました。
そこで、ついに昨年から基幹システムのリプレースに取り掛かることにしたのですが、その際に開発パートナーとして選んだのが、私が代表を務めるソニックガーデンでした。クラシコムに関わって7年目にして、満を持して。
ソニックガーデンの提供する「納品のない受託開発」は、事業を支えるソフトウェアを作り「続ける」ために、その開発体制も維持し「続ける」サービスです。
これは、事業会社のCTOとして考えたときに、(自分が経営する会社のサービスということを差っ引いても)理想的な開発サービスなのです。
なぜなら、CTOとして欲しいのは、ただ動くシステムがあれば良いのではなく、事業成長に合わせて改修し続けられる開発体制だからです。「ソフトウェア+開発チーム」が、CTOの管掌範囲なのです。
その場合の開発チームは必ずしも社員だけで構成しなくても、持続的に関係を続けてくれるのであれば、法人でも構わない。むしろ、雇用契約よりも場合によっては安定性は高い可能性すらあります。
開発チームの構成を、社内・社外の垣根をなくしつつ、一方で、ただ一つにまとめるのではなく、連携しながら並行で走りつつ、一人当たりの認知負荷を高めすぎない形のプロジェクトの連帯を作っていくこと。
そこには、ソニックガーデンの「納品のない受託開発」を採用すると同時に、クラシコム側での、現場の社員たちの協力や、上場企業としてのシステム統制、内製エンジニアチームとの連携といった高度なプロジェクトマネジメントが必要でした。
今回の振り返りでは、そのプロジェクトマネジメントを推進してくれた二人の執行役員たちと、クラシコムのCTOの立場で話をしてきました。事業会社でプロダクト開発に取り組まれてる方に参考になれば幸いです。
ぜひ、ご覧ください。
システムが事業成長をリードする未来に向けて──創業から育てた自社製基盤リプレイスの挑戦