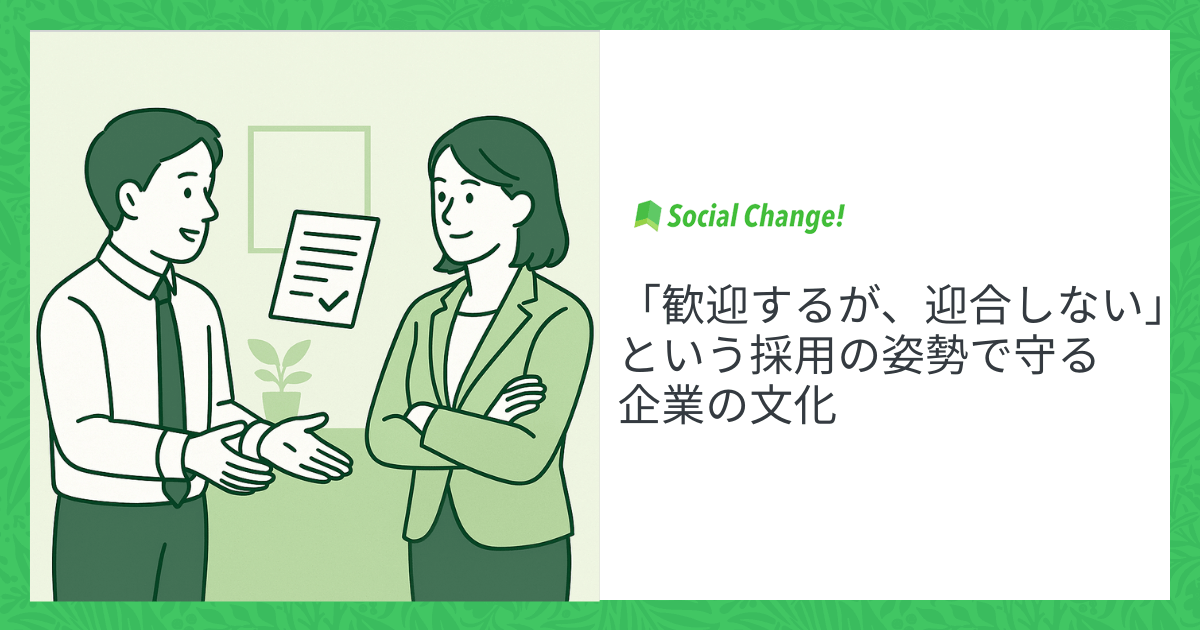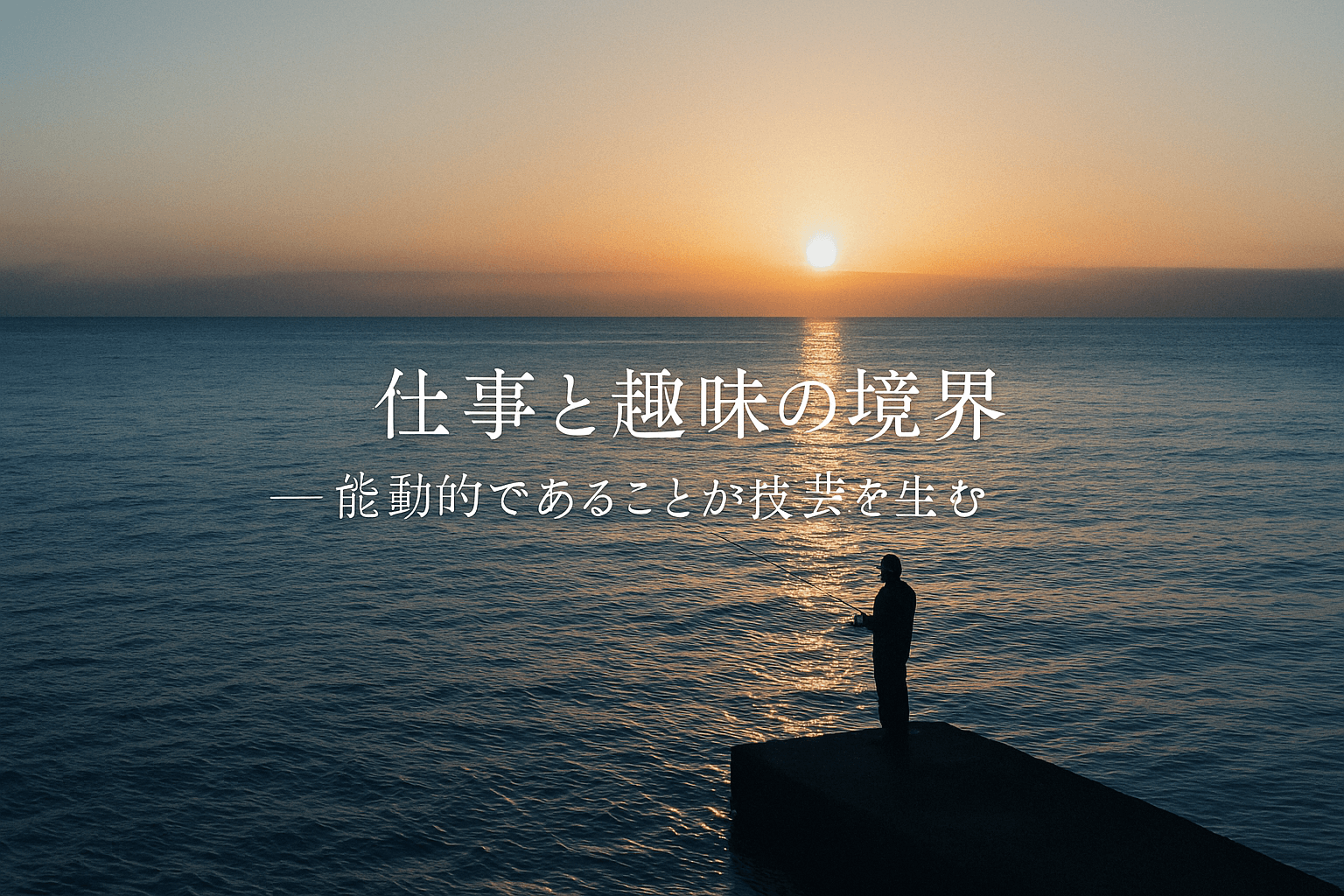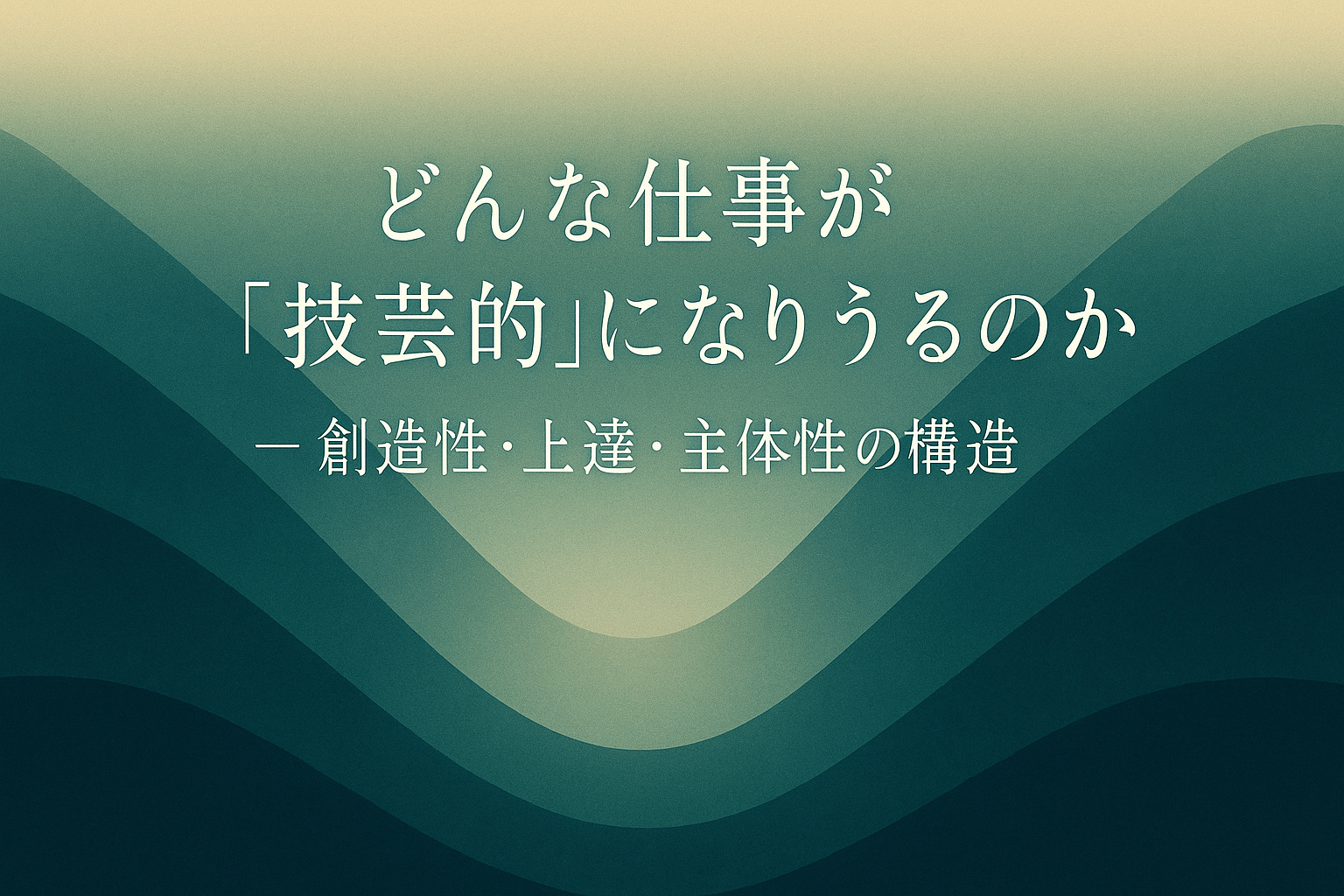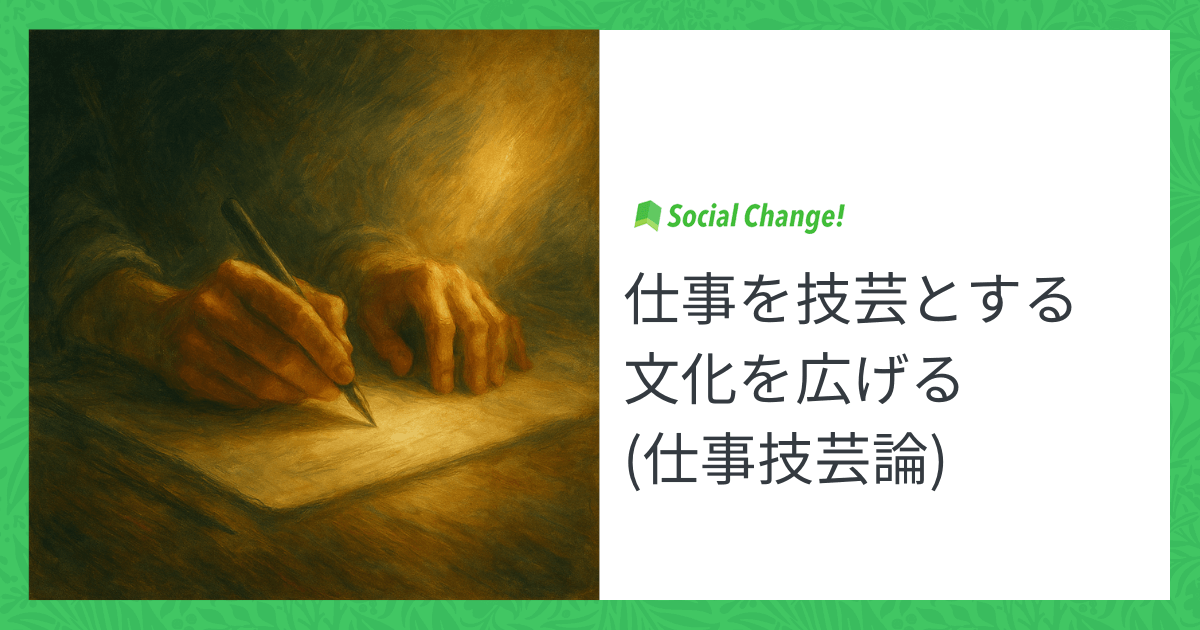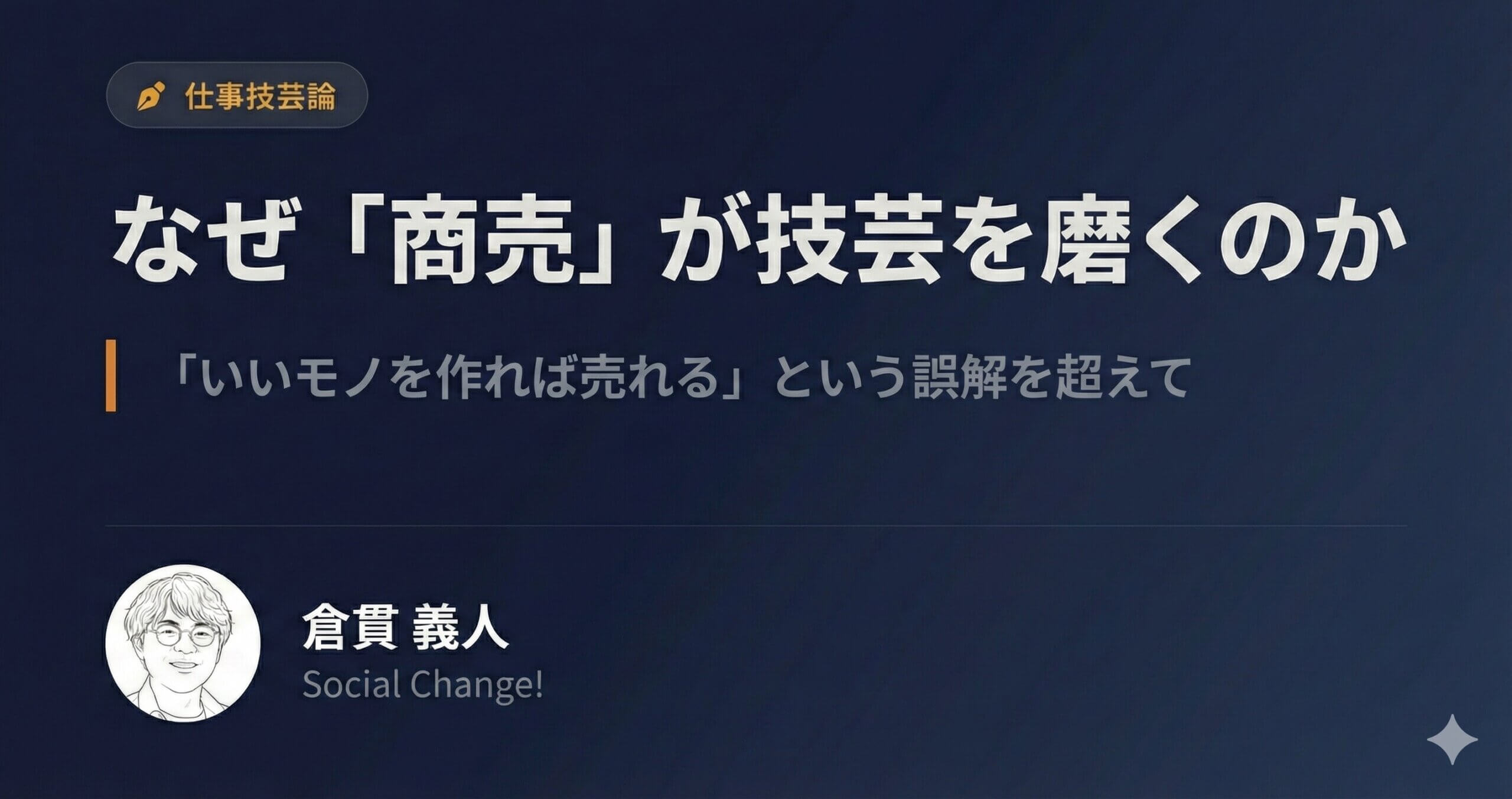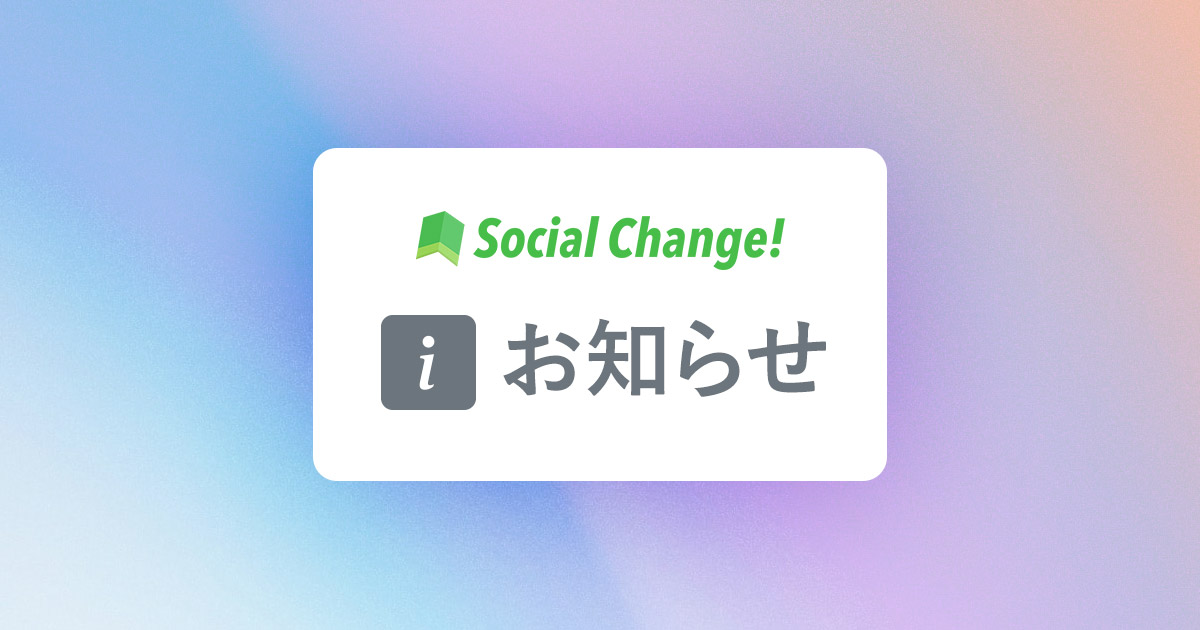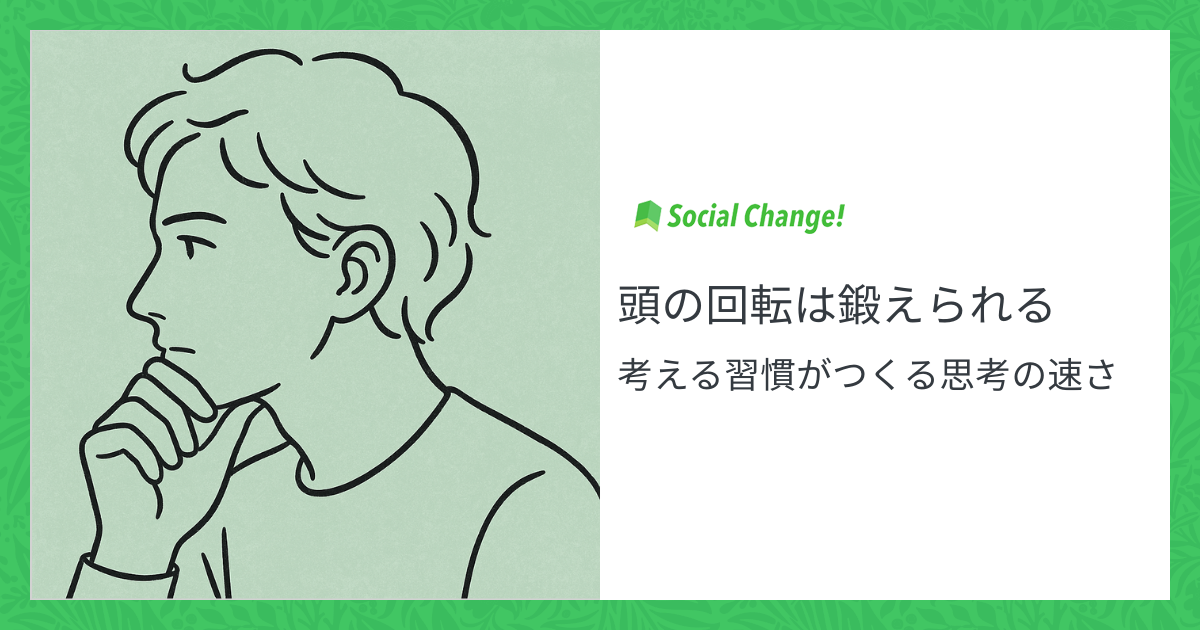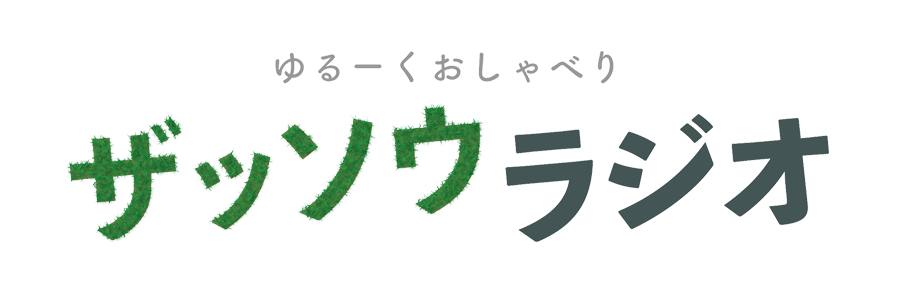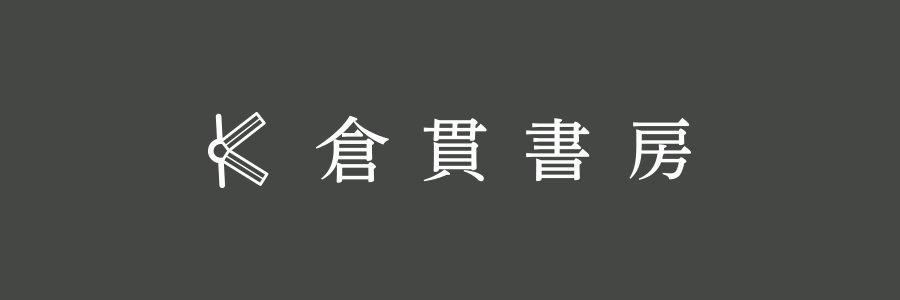採用競争が激しくなる中で、企業は「来てくれるなら誰でも」という気持ちになりやすい。しかし、それでは長く続く関係は築けません。採用は人を集めることではなく、仲間を迎えることだったはずです。
私たちは、その姿勢を「歓迎するが、迎合しない」という言葉で表しています。歓迎は相手を尊重する行為ですが、迎合は自分たちを曲げてまで相手に合わせることです。
迎合が生まれる構造と、防ぐ方法
採用を分業化しすぎると、その目標達成のために、判断基準が甘くなってしまうことが起きてしまいます。それは短期的な成果になっても、長期的な関係づくりにおいては悪手です。
最も良くないのが迎合してしまうことです。相手に合わせて制度や基準を変えてしまうと、組織から「らしさ」やフェアさが失われていき、いずれ組織を弱くする要因となります。
もし、相手に合わせることで自分たちが変わる覚悟があるなら、それは新しい進化の一歩になるでしょう。けれど、覚悟がないまま迎合してしまえば、必ずどこかで摩擦が生まれます。
迎合しないとは、変わらないことではなく、何を守り、何を変えるかを自覚的に選ぶことです。迎合を防ぐためには、その時々の感情だけで判断せず、ロジックを構築することが肝要です。
歓迎することは、関係を作ること
仲間を迎え入れる採用において重要なことは、応募者と会社が対等の関係で、互いに確かめ合うことだと、私は考えています。歓迎するということは、その上で良い関係を築こうとする姿勢なのです。
迎合しないので、求める技術力やカルチャーフィットといった判断基準を曲げることはしませんが、それを一方的に判断するのではなく、クリアできるような支援はしていきたいのです。
「入社して一緒に働く」というテーマに対して、応募者だけの問題とせず、私たちにとっても共通の問題とすることで、採用プロセスが関係構築のアクティビティになります。
その取り組みを通じて、互いのことを知ることもできます。採用の構図を「応募者 vs 会社」ではなく「問題 vs 私たち」に変えること、それが歓迎するということなのです。
歩み寄りはするが、交渉はしない
「問題 vs 私たち」で入社に向けて取り組むと、徐々にチームになっていきます。チームになれば、互いの事情や状況に合わせて、助け合いをしていくことは自然なことです。
応募者の方が、うまく時間を作れないなら相談には乗るし、家庭の事情があればできる限りの支援もする。迎合しないからといって、頑なに突っぱねるのではなく、対話を重ねて柔軟に対応していきます。
一方で時には、応募者の中には交渉をしてくる人もいますが、それには応じません。交渉とは、関係を取引に変えてしまう行為です。条件で折り合うような関係は、いずれ条件で別れることになります。
たとえ能力に魅力があっても、私たちの場合は採用しないことにしています。私たちが探しているのは、交渉相手ではなく、共に問題に立ち向かう仲間だからです。
時間をかけて信頼を築くプロセス
「歓迎するが、迎合しない」スタイルで、これまで私たちソニックガーデンは採用に取り組んできました。
中途採用の場合は、高い技術力と生産性が求められるのでハードルを下げることはできませんが、メンターをつけて越えるためのサポートを行なっています。
ほとんどが半年以上の時間をかけることになりますが、それもまたチームビルディングの時間になり、カルチャーフィットと信頼関係の醸成に効果がありました。
若手採用では、中途のように時間をかけることが難しいという課題がありました。そこで、入社前から文化や価値観を共有できる「トレーニングセンター(トレセン)」を始めることにしたのです。
採用は文化を守る経営の意思決定
採用は、会社の未来を形づくる経営の意思決定です。誰を迎えるかによって、文化や空気は少しずつ変わっていく。どんなに人が足りなくても、文化を守る線は譲れません。その線を守ることが、結果的に組織にとってフェアであり、応募者にとっても誠実であると信じています。
私たちソニックガーデンでは、採用のスタンスとして「その方の人生がより良いものになるかどうか」を常に考えています。もしソニックガーデンがその答えであれば、一緒に取り組んでいくことができます。
歓迎することと迎合しないこと。その両立は簡単ではありませんが、そこにこそ採用の本質があります。出会ったすべての人を歓迎しながら、自分たちの文化を守る。それが、私たちが大切にしている採用の姿勢です。