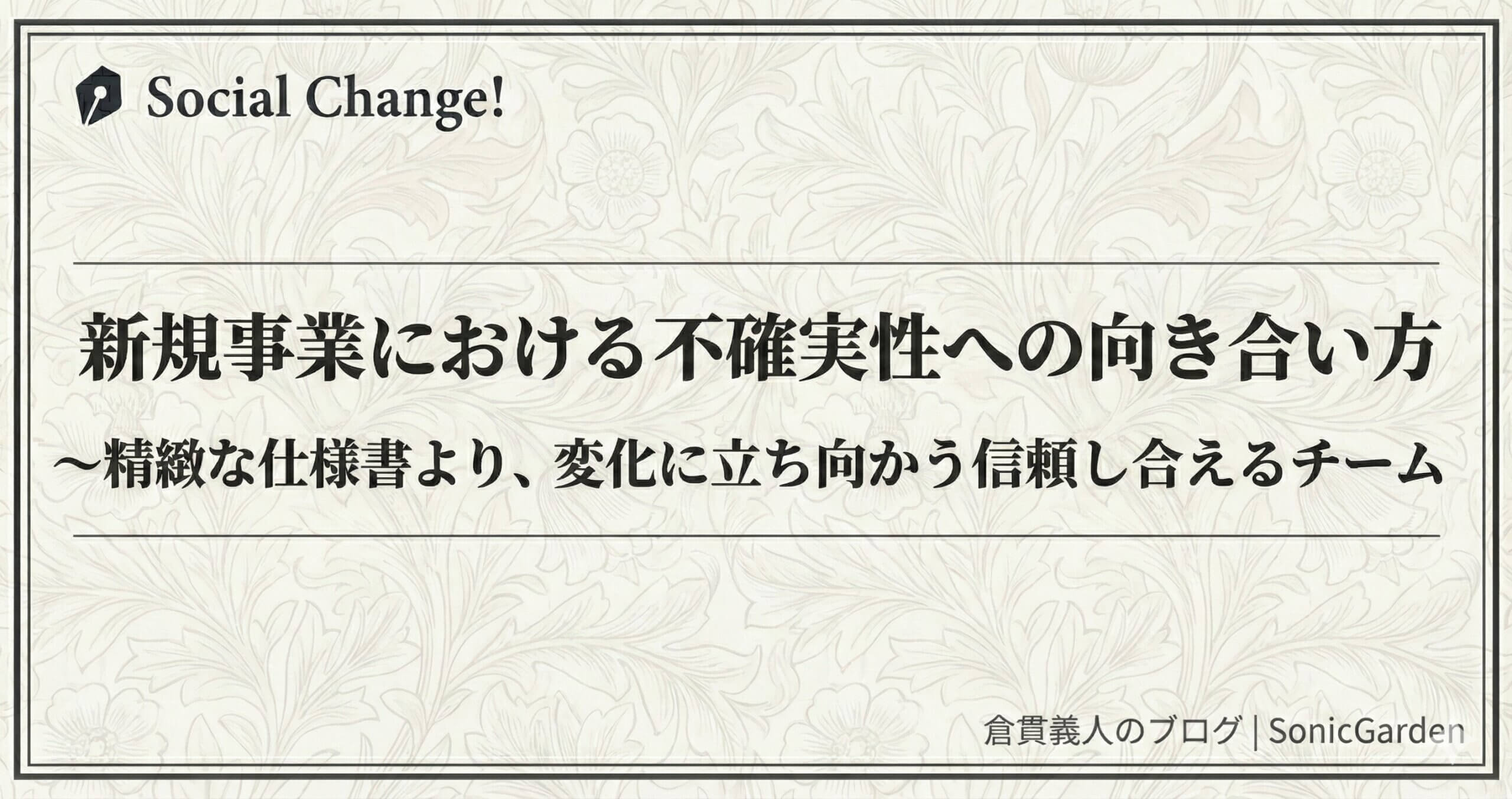会社の人数が増えてきたこともあり、来月からの11期に向けて、人事制度の再整備をしているけれど、とても難しいパズルを解いているような気分。この半年ずっと考えて、ようやく解けそう。
私たちの会社の制度づくりで気をつけていることは、実際に起きている事象を分析して、適切な名前を付けて制度にしていくこと。間違っても制度から導入することがないようにしている。
なので、制度ができても現場レベルでは変わらないことが多い。もちろん伝え方に細心の工夫をして、出来てるかどうかはさておき、制度の導入に伴うハレーションや混乱が起きないよう努力してる。
新しい制度を考えるキッカケも、現場を観察して気付いたこと、社員との1on1で出てきた要望、トラブルやリスクへの対応などがトリガーになる。なので、常に歪みがないか現場を観察している。
全社員リモートワークということもあり、人もデータもデジタル上に存在しているから、時間も越えて見聞きできるし、広範に目配りができる。おそらくオフィスだったら難しかったかもしれない。
実態ありきで制度を作る順にしているのは、制度にした瞬間からレガシーになって、必ず実態の方が未来にいってるからなのと、制度にすると1/0(デジタル)になるけど、実態はアナログだから。
人数が50人を越えて事業も広がった中で、実態からの制度を作るとなると、分析・整理するのも骨が折れる。ただソフトウェア開発でいえば、データモデリングみたいなものでハマると気持ち良い。
特に人事制度は、ゲームデザインをしている気分になる。自由度と制約のバランスが悪いとクソゲーになるけど、うまく作れば、気持ちよく働きつつ個人も成長もできて、フロー状態に入ってもらえる。
ゲームデザインって考えると、自社のビジネスモデルが何なのか、シューティングかRPGか理解せずに、他社の事例や目新しいコンセプトなどを参考にして作ってもうまくいかないのは当然なんだな。