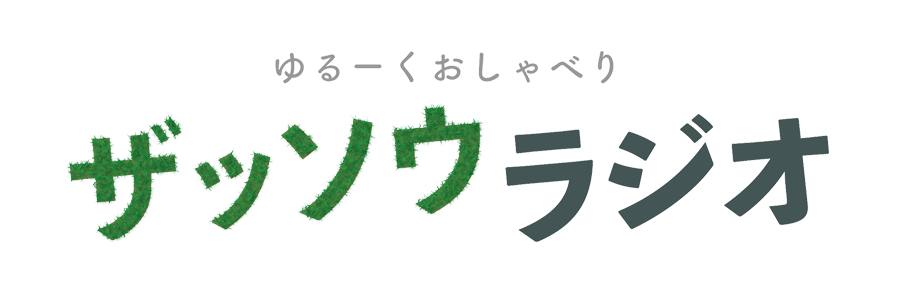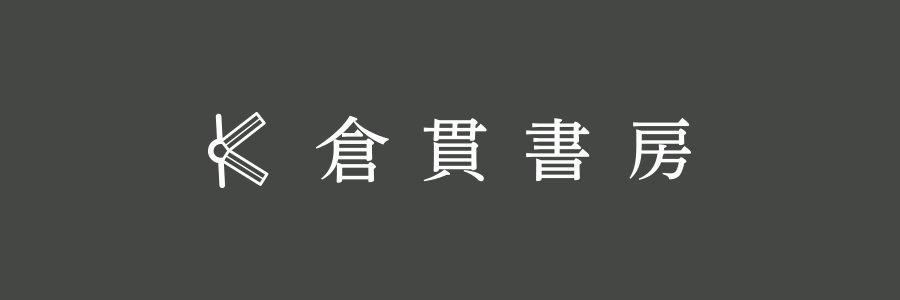新しい手法や考え方を勉強することは大事だと思うけど、それを続けてるだけでは、横並びから飛び出ることなど出来ない。置かれた中で自分の頭で、どれだけ考えるかの方がよほど大事。誰かの手法や考え方はヒントに過ぎない。
投稿
49
新しいことに取り組むときは、義務感で取り組んでもうまくいかない。アイデアは出ない。アイデアは面白くなければ楽しめない。アイデアを出すことを楽しむためには、やりたいからやる気持ちが大事。だから「新しいことをしなさい」という指示のもとで取り組む新規事業なんてものは大抵うまくいかない。
81
プレゼンスを高める活動のうち、長期的な観点で見ると、やはりブログが最も費用対効果が高かったように思う。ブログがあれば、自分が休んでいる時も休まず代わりに発信し続けてくれる。主義主張を入れたブログを書くのは勇気がいるが、その分ポジショニングがはっきりするので、外から見てわかり易い。
60
ソフトウェアの会社を経営するなら、ソフトウェアの特性を知り尽くしていた方がうまくいくのではないか。ソフトウェアの特性を知り尽くすためには、自らプログラミングをしてソフトウェアの全ての工程をひとりで作るという経験が必要だ。そんなソフトウェアのことを知り尽くした経営者が増えてほしい。
92
本当の責任感というのは、ただやみくもに頑張ることでも、ただガムシャラに時間をかけることでもなくて、出来ないことは出来ないとちゃんと言うことではないだろうか。
39
プログラマだけで構成される私たちの会社の経営で最も大事なことは、その経営の決断に筋が通っていることと、納得感があること。ロジカルに詰められていれば気持ち良く納得できる。そんな会社での社長の仕事のひとつは、自分たちの事業を抽象化・モデリングして、納得できるよう解きほぐしていくこと。
71
ふりかえり事例。意図してやっているのか、天然でやっているのか、その違いは大きい。意図せずやっていることは改善できない。例えば、「まだ慣れてない」というのは問題として適切ではなく、トライを出すことができない。意図して取り組むことで、それが良かったのか悪かったのか、後から判断できる。
103
ソフトウェアを作れるだけでは世界は変えられないけれど、ソフトウェアを作れないと世界は変えられないような世界になってきつつあるように感じるし、だからこそ、世界を変えたい人の力になれるソフトウェア開発のエンジニアはとても尊いと思うし、そこがソフトウェア開発ビジネスの醍醐味だと思う。
50
経営には終わりがない。忙しさも暇もなく終わりがなく続く。会社があってその立場にいる限り、やることも考えることもなくなるということはない。誰かが代わりにやってくれることも、ゴールを誰かが決めてくれることもない。ただひたすら前に進むしかない。それに耐えられる人だけが経営を続けられる。
82
「タスクばらし」はセルフマネジメントで仕事をしていく上での基礎スキルの一つ。適切に分割したタスクがあれば、進捗状況が他から見えやすく、自分の状況も把握しやすく、優先順位も意識することができる。タスクをこなすことよりも、その前にばらすことの方が大事。
29
事業は一度でうまくいくことはない。失敗をしても続けていくことで、少しずつうまくなっていく。「うまくいく」というのは急にうまくなるということではなく、徐々にうまくなっていくということだ。一度の失敗で全てを失うような賭けをすることは、潔くてカッコいいかもしれないが、スマートではない。
61
ソフトウェアは使ってみるまで本当の使い勝手は見えてこない。本気で使い始めると必ず新しい要望は出てくる。ソフトウェアは最初に考えたアイデアをそのまま作ってもうまくいかない。作るときに直したくなるし、使ってみたら直したくなるし、誰かに使ってもらおうとすると直したくなるのは間違いない。
93
ベンチャーでの採用の場合、入社してゴールだと思ってる人を採用する余裕はない。入社してからがスタートで、一緒にビジョン達成に貢献しようという人しか採用できない。
40
企業でのプログラマ教育で「Javaできるようになる」みたいな目標設定はいまいち。サッカーならドリブルの練習だけして、練習試合せずに公式試合にでるようなものだ。チュートリアルは良くて、何度もアプリを作って壊して、また作るという経験に軸足を置いた方がいい。作ったほうが楽しさがわかる。
72
キャリアを積めば、部下を持って管理職になるのが一般的かもしれないが、職人の世界で考えると、自分自身の腕を磨くことこそが一番で、部下を育てるより自分を育てたい。ならば、部下を持たずにキャリアを積む程、余計な仕事から解放されていく仕組みを組織としては用意するのが良いのではなかろうか。
104
「忙しくて出来ない」ってのはね、そのことがその人にとって優先度低いんですよって言ってるようなものなので、忙しくてって良い訳は使わない方が良いよって話を聞いたことある。
51
経営の話。小さく舵を切るには短い時間で良いが、大きな舵を切るには長い時間が必要だ。常に舵を切り続けることがうまくいく秘訣だが、時に大きな舵切りをしなければ、遠い将来に生き残ることさえ難しくなることもある。大きな舵を切るためにかかる時間を忘れずに、時間をかけて船の向きを変えていく。
83
少し未来の話。再現性のある作業は全てコンピュータとロボットに置き換えられ、人に残された仕事は知的生産だけとなり、あらゆる仕事がリモートワークで実現できる社会。生産効率は高まり長時間労働はなくなる。好きな場所に住み、移動や物理的に会うことは趣味や嗜好であり、とても贅沢なことになる。