リモートワークの4つの失敗パターンと対処法
「働き方改革」という言葉が注目される中で、リモートワークにも取り組もうとする企業も増えてきているように感じる。 しかし、これまでオフィスで働くことが普通だった会社の人たちが、いきなりリモートワークに…
「働き方改革」という言葉が注目される中で、リモートワークにも取り組もうとする企業も増えてきているように感じる。 しかし、これまでオフィスで働くことが普通だった会社の人たちが、いきなりリモートワークに…
仕事におけるチームのマネジメントをしていて、サッカーの監督がとる戦術が参考になるな、と昔から感じていた。 サッカーの世界で有名な「トータルフットボール」すなわち「ポジションが流動的で、且つ全員攻撃全…
プログラミングには、論理的に考える力と抽象化して本質を捉える力が求められる。これらは、なにもプログラミングに限らず、あらゆる仕事の場面で役に立つ。むしろナレッジワーカーにとっては基礎力といっても良い…

長くなったので先に三行でまとめておこう。 コピペするプログラマが生まれるのは教育の問題ではないか(仮説) 文法は学んでも処理の流れから考えることは教わっていない(根拠) ロジックを訓練するには…
最近、こちらのブログよりも高い更新頻度で書いているのが、"Medium"だ。私のMediumのページはここだ。 https://medium.com/@kuranuki Mediumは、ブログのプラットフォームで、2012年にTwitterの共同創業者だった…

今や、あらゆる場面においてソフトウェアが重要になってきた社会の中で、プログラミングを学ぼうと考える人も多いだろう。プログラミングを身につける方法は、インターネットにはたくさん情報があるし、本も多くあ…
社員一人ひとりが会社で本来の自分を曝け出すことができること、そして、それを受け入れるための「心理的安全性」、つまり他者への心遣いや共感、理解力を醸成することが、間接的にではあるが、チームの生産性を高…
非合理な常識よりも、非常識な合理を採る。それが自由への道である。 前回の記事で「経営はもっと自由で良い」と書いた。そう、一般的な会社経営で常識と考えられていることよりも、私たちは自分たちらしい会社のあ…
2016年のソニックガーデンの経営を振り返ると、新規事業の創出、オフィスの本質、人が増えた組織のマネジメントに取り組んできた。それらの取り組みは、一般的にイメージされる「会社」とは違う、新しい会社を作る…
ちゃんと日の目を見られて、楽しんで使ってもらえて、意図した人びとに広く普及するものをデザインし、作り上げること。それが喜びである。 翻訳レビューに協力したので頂いた本を読んだ。本書は、メンロー・イノベ…
先週は1週間の休暇を頂いて旅行に行ってきた。休暇と言いつつも、少しずつ仕事をしていた。私は経営者なので、仕事も休みも関係ないと言えば関係ないし、インターネットとパソコンさえあれば、いや最近だとスマホ…
世の企業の多くは、既存事業で稼ぎながら、次の商売のネタを探して新規事業の立ち上げを画策している。優秀な経営者なら、いつまでも市場が変化しないとは考えていない。変化に対応するためには新規事業が必要だ。 …

先日、山口県萩市でもリモートワークジャーニーが開催されました。そこで、未来を想像して日記を書いてシェアをする「リモートワーク未来日記」というワークショップが行われました。本記事では、私の考えた未来日…
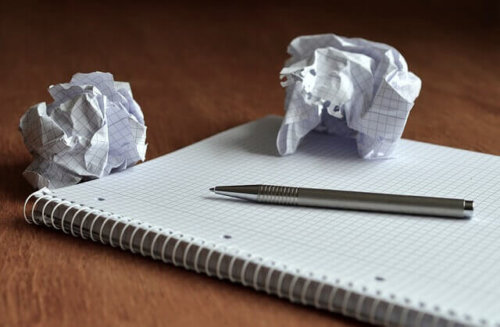
「仕事」と「作業」は違う(参考:「仕事」と「作業」の違いは何か)。学生時代のアルバイトなら「作業」が殆どだろう。しかし社会人になってするのは「仕事」だ。任された仕事は自分でマネジメントする必要がある…
私たちソニックガーデンには「部活」という制度があります。テニスやフットサルのような部活なら、どこの会社にもあるでしょう。しかし、私たちは仕事中におこなう創作活動や新規事業のことを「部活」と呼んでいま…
私たちソニックガーデンでは、「納品のない受託開発」という受託事業の一方で、リモートワーク支援ツールRemottyなど自社サービスの提供を行なっています。 そうした自社サービスの新しい企画や開発をする活動を、…
起業でも独立でも何かに挑戦するとき、裸一貫から自分の力だけで成し遂げる方が立派だと思われがちだ。いや確かに立派だが、もっと苦労やリスクを減らして、うまくやっても良いのではないだろうか。 今はサラリー…
多くの企業が新規事業に取り組んでは失敗している。新規事業はそもそも難しく、企業の中で始める新規事業もスタートアップも成功するケースはわずかしかない。中でも既存事業をもった企業の中で新規事業を立ち上げ…