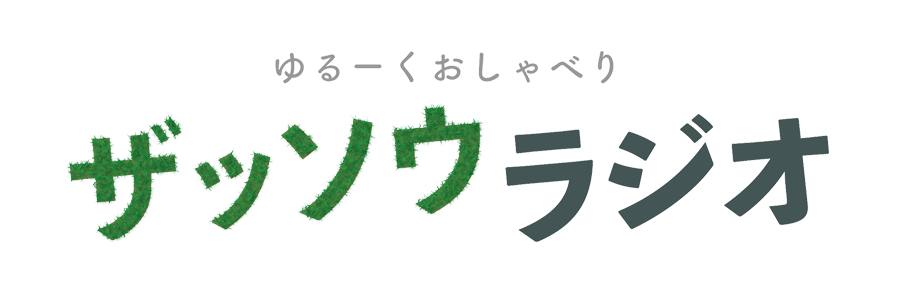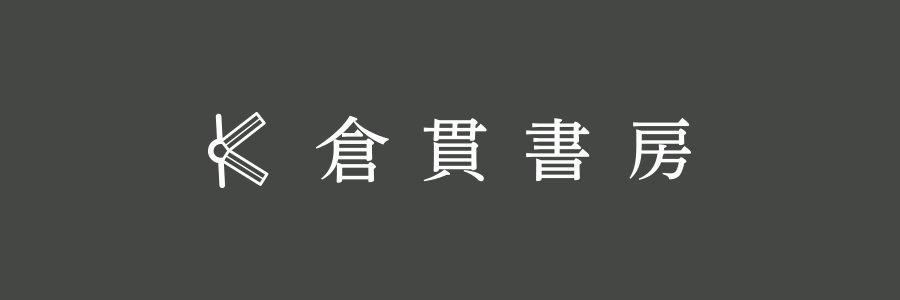ビジネスモデルのマネタイズを考えるとき、企業向けサービスで企業から回収したいときは、それがあることでどれだけ得するか、という観点が有効で、一方、コンシューマ向けで個人から回収したいときは、それがなければどれだけ損するか、という観点が有効ではないだろうか。
投稿
401
プロフェッショナルでいるというのは、その道を追求し続けられるかどうか。今の時代、インターネットさえあれば、ある程度のことは出来るようになる。だけど、技術であれば、ずっと新しいことを追求し続けるのは大変なことで、それが出来る人というのがプロであるための条件のひとつではないか。
348
どんな方法論も、最初は知って試してみる時期があり、自分の現場でうまくいかないことにヘコみ、それを一旦は忘れて、自分の頭で問題の本質から考えるようになって、そうして少しずつ理想に近づいていくうちに、そのうちに外からは、その方法論を実践しているように見えるようになる。それが守破離か。
380
スタートアップの人たちとの仕事はスピード感も熱意もあって、とても楽しい。応援したいと思えるスタートアップを応援できて、それを仕事としてもお付き合いできるのは嬉しい。インキュベーターの新しい形が見えてきた感じがする。
412
現場で苦労しなくてもアジャイル開発が自然と出来るようなビジネスモデルまで含めたやり方を「究極のアジャイル開発」と呼び、昔ながらのビジネスの中でも組織になんとかアジャイルを導入しようと工夫し努力するやり方を「至高のアジャイル開発」と呼ぶのはどうだろう。どちらが正しいではなく、違う。
359
ふりかえりをすると気付くことが沢山ある。気付きメモを社内で共有してるけど、これを文脈を共有してない人も読むブログにするとなると、読者視点に書き換えるのが大変なんだよな。
391
自分の戦略を持つということは、日々よりも少し大きな視点で考えること。戦略とは、その時点での仮説であるが、その時点ではベストだと思えること。戦略という仮説がなければ、成長を確認できない。日々を過ごして浪費しないための目印が戦略。戦略があれば、目の前の果実を捨てて大きな未来を選べる。
370
売り切らないビジネスモデルが多くの業界に広がっていて、その方がお客様にとっても提供側にとっても長い関係を続けることが出来て、メリットも多い。技術的な問題で出来なかった業界も多かったけれど、ITによって、かなり解消してきた。ソフトウェア開発の業界で実現したのが、納品のない受託開発。
402
自分のマネジメントが出来ない人にチームのマネジメントは出来ないし、自分の戦略を考えられない人にチームの戦略は考えられない。いわんや経営をや、ということ。まずは、自分のマネジメントと戦略を。
349
実行しないアイデアに価値はない。少なくとも実行しなければ、学びはない。アイデアを実行するまでに必要な熱量の正体は何だろうか。アイデアを実行に移すまでにかかる熱量が少なくて済むような、沸点の低い企業カルチャーを作りたい。承認・規則・組織といったキーワードは、その真逆だろうと思う。
381
新しい事業が立ち上がるまでには、本当に自分のやろうとしていることが正しいことなのか、という付きまとう不安を振り払って続けていけるだけの、心の強さみたいなものが必要で、方法論なんてのは、そこで無駄に消耗しないようにするためのものなんじゃないか。
413
ソニックガーデンで働くことは、毎日が勉強会やコミュニティに参加してるようでもあり、毎日が開発合宿に行ってるようでもあり、毎日がリーンスタートアップマシーンに参加してるようでもある。そんな感じで働けますが、実は、それはそれで大変なんだと思う。
360
事業の方向性や戦略を検討したり、決断をしたりするときには、一人よりも二人で話し合う方が、精神的にも思考の観点としても良い。会社の創業も一人よりも二人の方がうまくいきそうだ。ただ意思決定に二人以上いると、スピード感がなくなりそうだ。
392
プログラミングが好きで、ずっとプログラミングしてきて、ある時、会社の悪い仕組みを変えようとして社内SNSを作った。以来、プログラミングは大事な手段で目的は仕組みを変えることになった。今はプログラミングしないけど、社会の仕組みをハックしたいと思って、スタートアップの経営をしている。
371
尊敬する女性経営者の話。とても意義のある、だけど困難なことをやろうとする社会起業家だ。あるとき「もしうまくいかなかったらどうする?失敗したら?」と誰かが聞いた。彼女は「大丈夫。うまくいくまでやめないからww」と笑顔でこたえた。その笑顔が本当に素敵で、これが本物の起業家だと思った。
403
色々な人たちと話をしていて気付くのは、やはり自分が本当にやりたいことを話してる時に人は目を輝かせてる。話の中で、そんな瞬間を引き出せたら、嬉しい。
350
企業の風土改革について。風土改革は、一度きりの革命のように成し遂げるものではなくて、風土改革し続ける風土を作ることが肝要なのだと考えている。変わることを恐れず、継続的に変わり続けようとするカルチャーを持ちたい。
382
今の状態が良いからといって、もしくは忙しいからといって、新しいことに挑戦しなかったり、変化しないで済ませようとしたり、現状をキープする気持ちになってしまったとしたら、それでは結局は現状維持すら出来なくなってしまうのではないか。これは会社の話で書いたけれど、他のことでも言えそうだ。