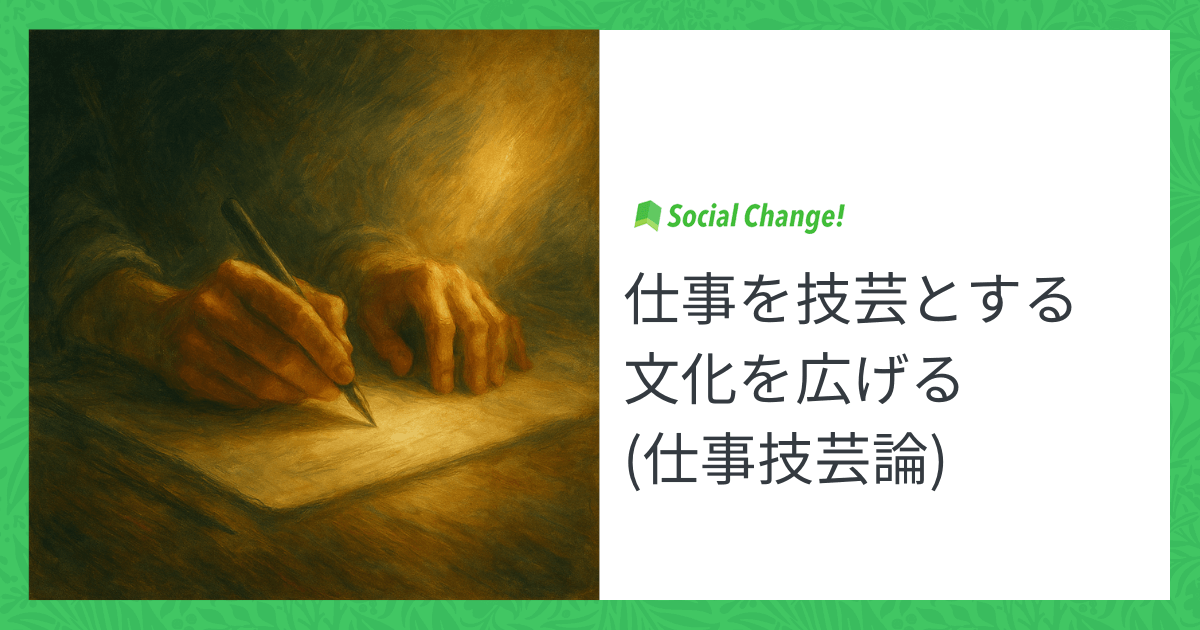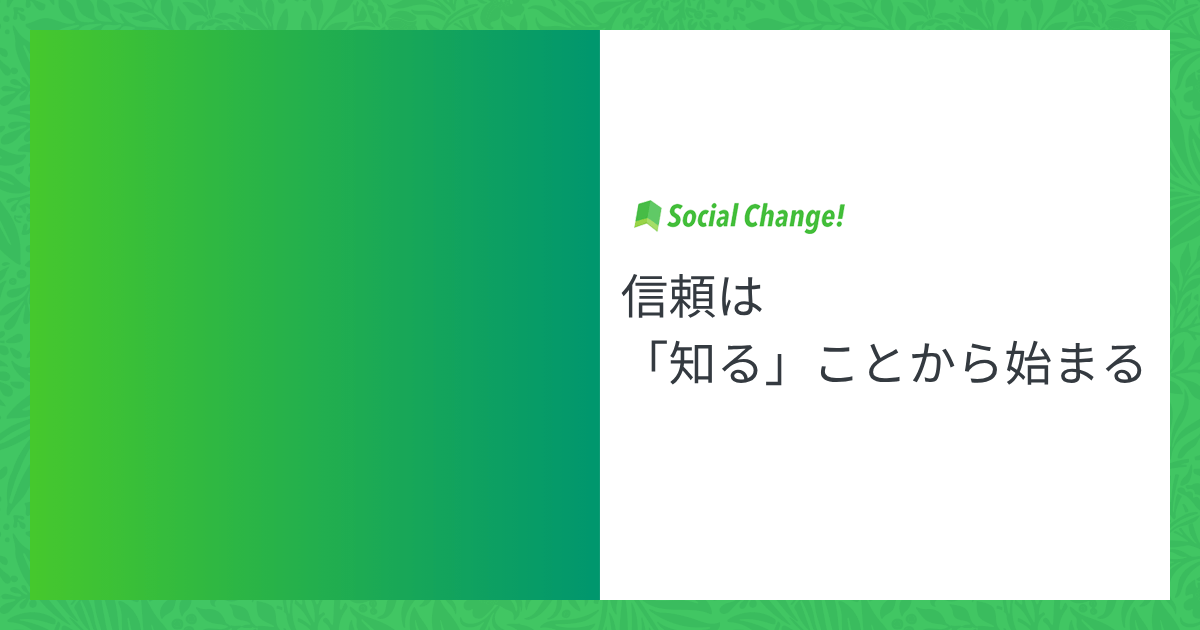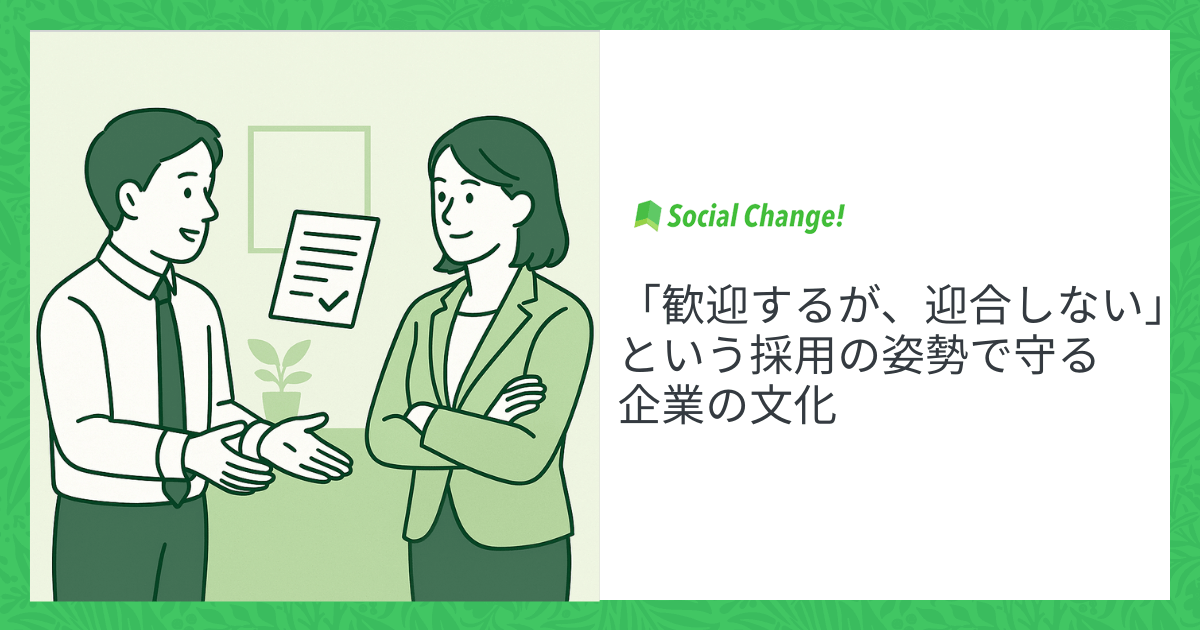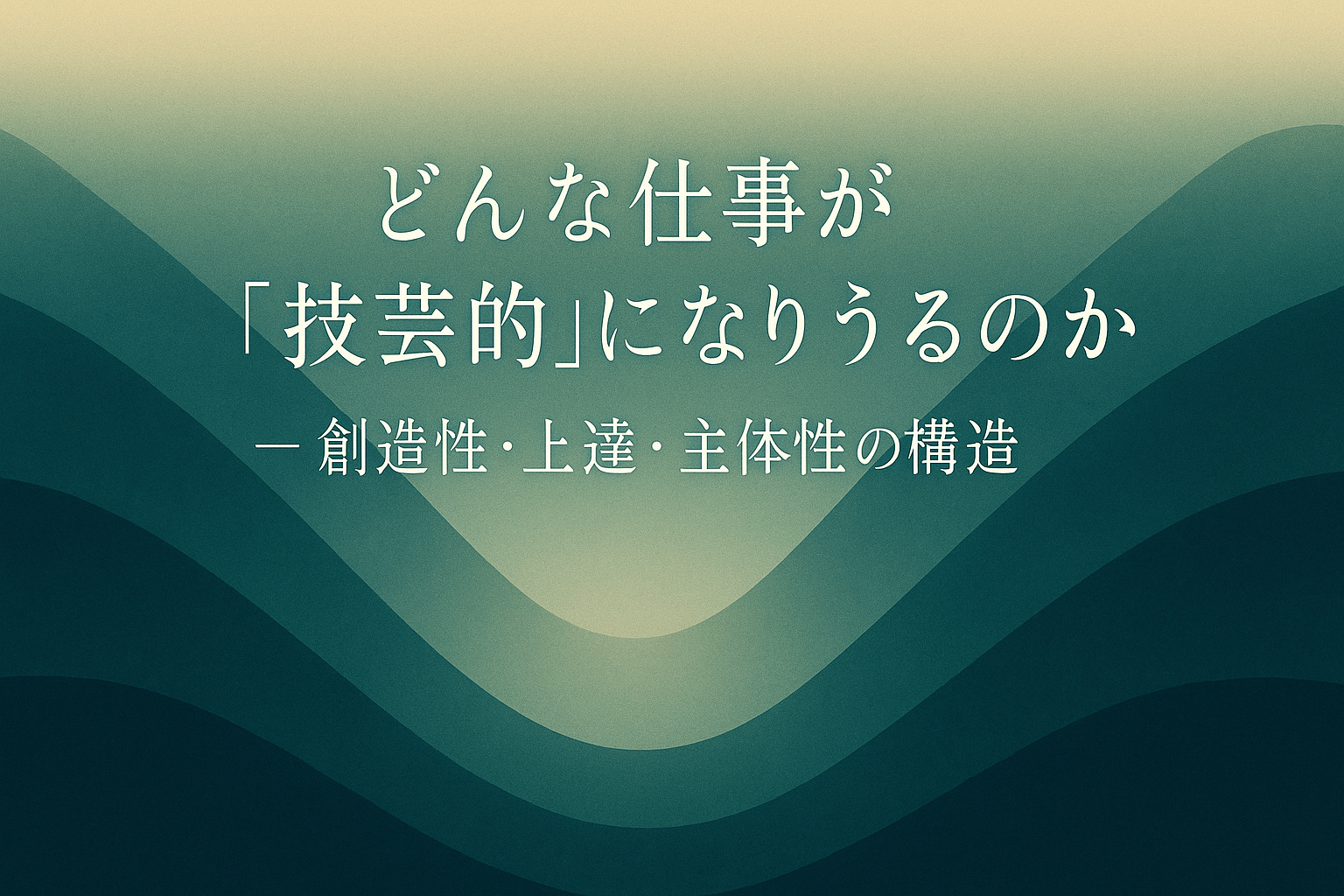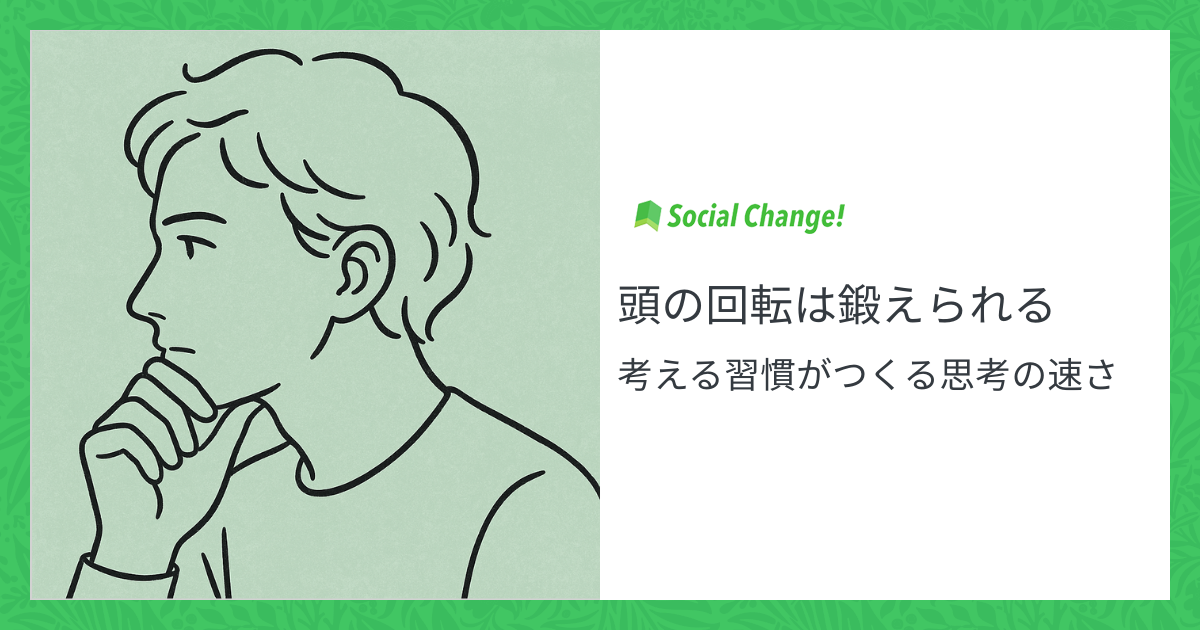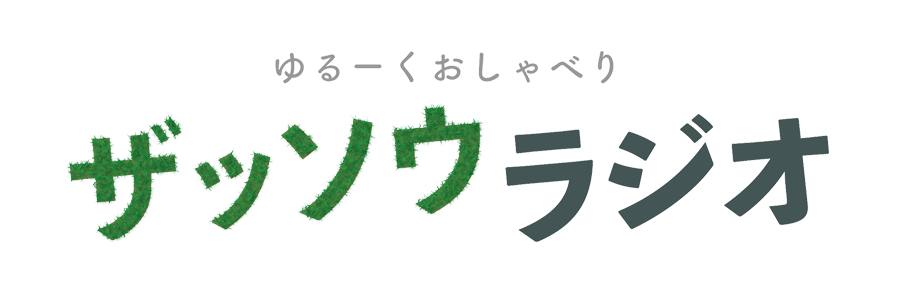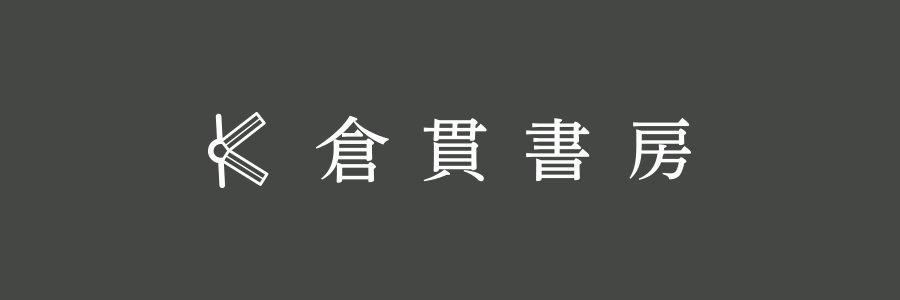運動や読書などの良い習慣は忙しくなると疎かになりがちだけど、そうなると自分で良いと思ってる習慣をやってないことに罪悪感を覚えてストレスが溜まる。忙しいときこそ時間を作って、あえて取り組むようにする位がちょうど良いのかもしれない。
ホラクラシーはスケールできるのか 〜 小さな会社から自律型の会社へ
私たちの会社、ソニックガーデンでは「管理のない会社経営」として、セルフマネジメントができる人材で構成されたフラットなチームの在り方を模索してきました。これは最近だと「ホラクラシー」と呼ばれる経営スタ…
ワーク+バケーション=ワーケーションの実験 〜 八丈島を満喫しながら仕事をやってみた
私は今、この原稿を八丈島で書いています。八丈島は、東京から飛行機で45分ほどで行ける島で、離れてはいますが東京都の一部です。といっても温泉やマリンスポーツで有名なリゾートです。 そんなリゾートを訪れな…
「頭の回転」は才能ではなく努力で鍛えられる 〜 打ち合わせのアドリブ力を上げる4つの要素
一方通行の報告だけの会議は生産的ではありません。生産的な会議とは、その場でディスカッションをしてアイデアを出し合って、その打ち合わせの時間内に結論や成果を出すような会議です。そのためには、打ち合わせ…
PMシンポジウム2015にて「優秀講演賞」を頂きました 〜 ホラクラシーがPMで認められた!?
日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)が主催している「PMシンポジウム2015」において、「優秀講演賞」という賞を頂きました。ありがとうございました。 いつも「プロジェクトマネジメント」からは少し離れた…
tweet
毎週それなりの文章量でブログを書いてきて、ふりかえって読んでみると、なかなかのボリュームになっている。もっとたくさん書きたいと思ったりもするけれど、気力と時間を考えると今のペースがギリギリくらいな感じ。塵も積もれば山となるの精神で少しずつでも続けていけば、それなりになるんだよね。
上司をなくせばうまくいく「ホラクラシー」採用と育成の仕組み 〜 ギルドを2年やって得た学び
先日、私たちの会社ソニックガーデンのウェブサイトを少しリニューアルしました。会社を始めて5期目になって、少しずつ人も増えて組織も変化してきました。会社の顔であるウェブサイトもあわせて変化させたいと考…
tweet
ウェブ技術を経営に活かせる時代になって経営者が身に付けておくと良さそうなリテラシーの一つが文章力じゃないだろうか。自分の言葉で伝えるのが一番伝わるし、想いを伝えることが経営者の大事な仕事の一つだとしたら、社内外に向けてブログやメッセージを書くことは、とても効率的で合理的だと思う。
管理をなくせばなくすほど生産性が高まる新しい組織の形「ホラクラシー」その背景とメリット
私たちソニックガーデンのマネジメントを説明するとき、セルフマネジメントでフラットな組織、メンバーそれぞれが自己判断して仕事を進める組織、と話していますが、最近ではそんな組織のあり方を「ホラクラシー」…
tweet
毎日が同じことを繰り返すことのない仕事は、毎日が成長の機会に溢れていて、どれだけやってもまだまだ成長の余地は残されていて、とても大変だけど、同時にやりがいもある。私たちの考えるソフトウェア開発とはそういう仕事で、飽きたり極めたと思って、もうやることなどないなんて思うことなどない。
銀座久兵衛に学ぶ一流の職人の育てかた 〜 スケールだけではない文化を広める一つのスタイル
「参考にしている会社はありますか?」と、ある取材の中で聞かれて、ふと考えた後に出てきたのは「銀座久兵衛」という言葉でした。銀座久兵衛とは、説明するまでもないですが、老舗の寿司屋です。 なぜソフトウェ…
生産的なチームの会議は報告じゃなく生産をする 〜 会議を協働作業にするパラダイムシフト
会議というのは、仕事をする上で必要不可欠なものですが、会議が多くなりすぎると生産する時間がとれなくなってしまいます。その結果、会議ばかりで仕事をした気にはなっても何も生み出していない・・・なんてこと…
「受託脳」から「提案脳」へ 〜 目線を変えて問題解決のプロフェッショナルになるためには
不特定多数に物を売るのではなく、特定の誰かの問題を解決する仕事をするときには、相手のことを考えるだけではうまくいかない場合があります。どうすれば顧客の本当の満足を得ることができるのでしょうか。 これ…
ふりかえりで初心者が陥りやすい落とし穴 〜 性格も実力も急に変えられないが行動は改善できる
私たちソニックガーデンでは、現場での人材育成の手段として個人の「ふりかえり」と、そのレビューを行っています。それを「ワークレビュー」と呼んでいますが、仕事の進めかたや、仕事に対する姿勢についてふりか…
tweet
ソフトウェアは作って動かしてみないとわからないことが沢山ある。どれだけ経験を積んだプロダクトマネージャーであっても、頭だけでうまくいくか想像しきることなど出来ない。良いプロダクトのためには、作って捨ててを繰り返すしかない。プログラミングを製造ではなく設計だと考えればそれが出来る。
tweet
「費用対効果」をいつも意識しているけれど、ここでいう「費用」はお金のことだけでなく時間や体力も含まれているし、ここでの「効果」も金銭的なインセンティブという訳ではなく、経験や選択肢を広げることも含まれている。むしろ、お金をかけても手に入らないものの方が世の中には多いことに気付く。
tweet
ふりかえりをレビューする目的の一つが、チームの価値観を伝えること。問題を見つけた後に改善案を考えるとき、アイデアだけなら幾らでも出せる。このときにどのアイデアを採用するのか、そこにチームの価値観が求められる。師匠は価値観を伝えるだけで改善案は自分で考えさせる。価値観が共有される。
tweet
ふりかえりの最初にすることは、自分の実力を認めること。実力を身に付けて成長するには時間をかけて経験を積むしかない。だから、ふりかえりでは出来ないことは問題にしても仕方ないし、改善することも出来ない。例えば、速く走るというトライは無理でも、フォームを改善するというトライなら出来る。