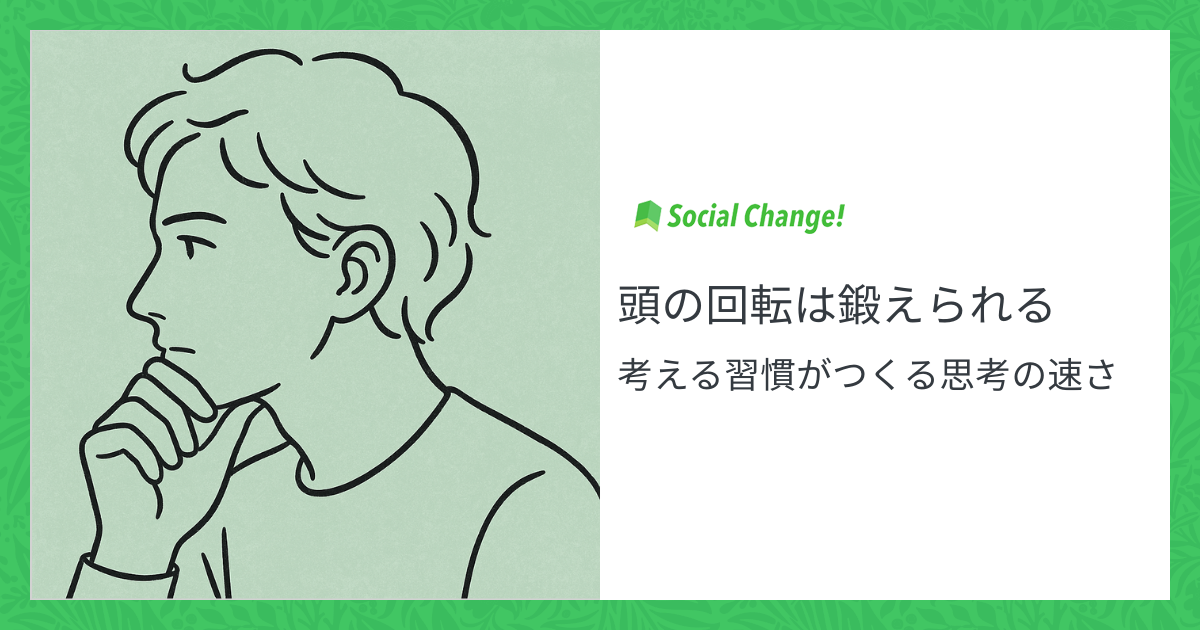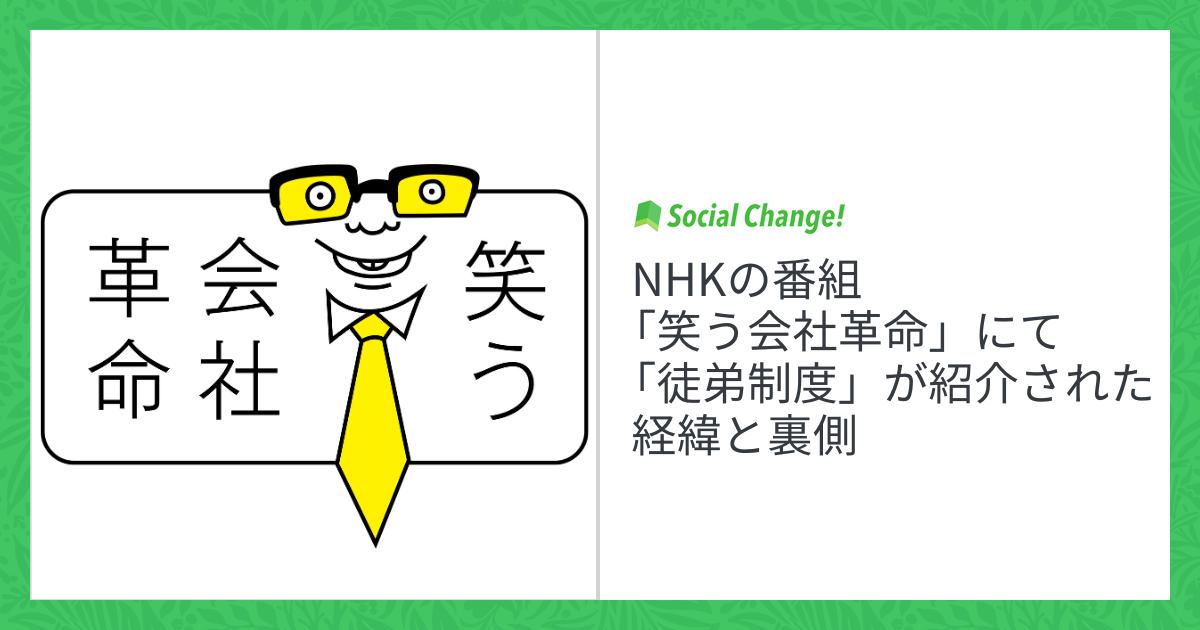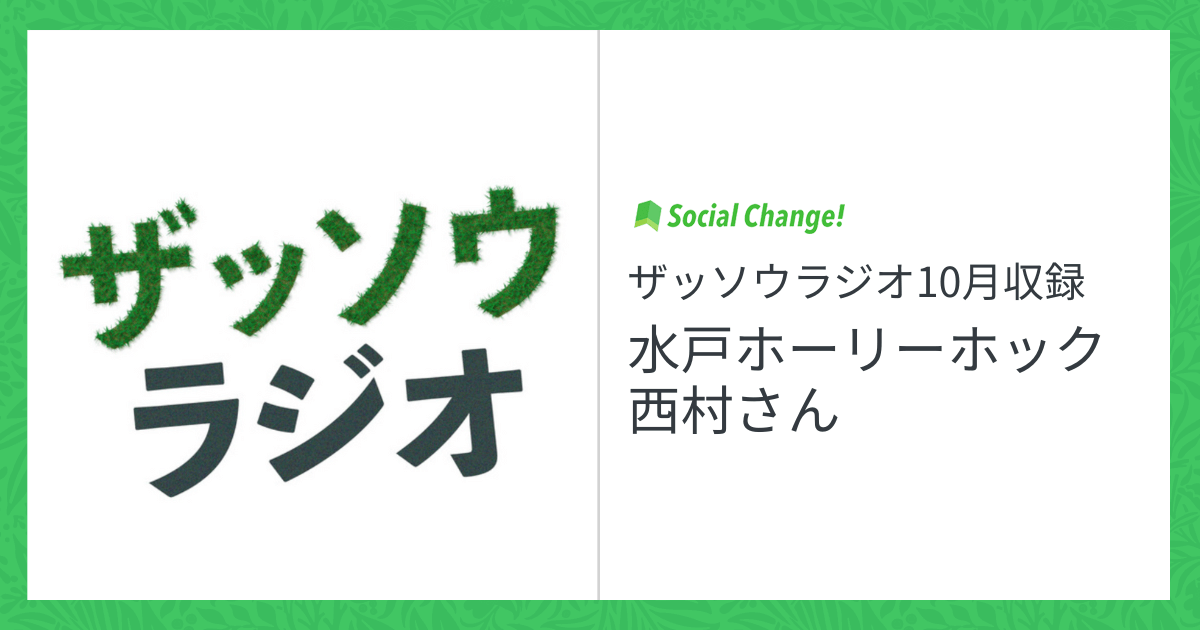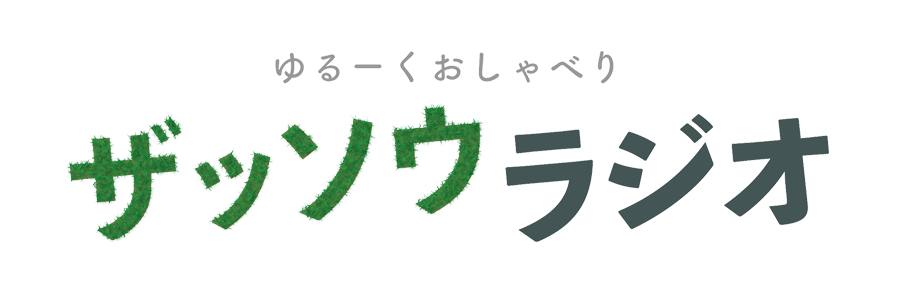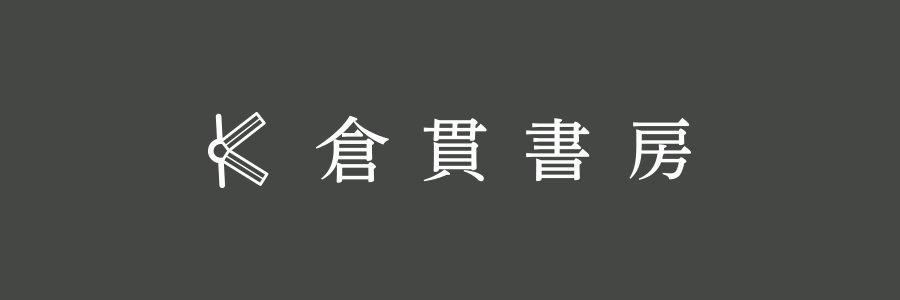コスト削減目的のシステム開発請負の中でUX重視は難しいだろうなぁ。プロダクト開発だと当たり前に重要性は認識されてる。でもプロダクト開発は内製化の流れ。
投稿
tweet
先入観は百害あって一利なし!自分の中でモンスターを育てない!
tweet
まずはベータ版でシンプルに作り、ユーザからのフィードバックを受け、ソーシャルでのコミュニケーションでマーコムしていく。機能を作らない判断も、人の意見を聞き入れることも、自分を出していくことも、勇気と敬意が求められる。なんだ、目指すソフトウェア開発は、最初から変わってなかったんだ。
tweet
案外、積み重ねて他と差別化になるのは、機能ではなくて、ユーザ体験。使い勝手のユーザビリティー、体感速度のためのパフォーマンス、見た目も含めたUIデザイン、のどれかではなく、それらの含んだ”user experience”が差別化のポイントではないか。
tweet
“User Experience”を高めるには、普段から使って、少しずつ、岩を削って角をとって丸くして、ひっかかるところなく滑らかにしていくしかないように思う。気になるところがなくなるまで、少しずつ。徐々に。
tweet
“user experience”って、短期的に評価出来ないことや、正解がないことが、どこまでリソースを割くか判断しづらいし、モチベーションを上げにくいところだろうか。そういう意味ではマーケティングも似てるか。
tweet
マーケティングは、本当にうまくはまるターゲットを見つけることが大事だと思う。どれだけ集中させるか。細く鋭く。顧客を選ぶ位に。
tweet
ツール自体は、なるべく広く浅く、どこでも使えるように、ユーザによって応用が効くように作りたい。ユーザによる新たな用途の発見と活用がなければ、広がらない。
tweet
ユーザは最初に明らかな用途か、物珍しさのいずれかでないと使い始めない。まずは第一段階。次に使って便利さにハマると使い続ける。これで第二段階。最終的に、自分なりの新しい使いかたを発見し、自ら広めるようになる第三段階。それぞれで求められる機能とマーケティングは異なる。
tweet
人に知ってもらうには、コンテンツが重要。まずは自分たちの持っているコンテンツとフィールドはどこか、そこをベースにして築いていかないと始まらないよな。
tweet
プログラマがプログラマだけで集まるのでなく、デザイナがデザイナだけで集まるのでなく、ビジネスも然りで、ソフトウェアとして作ったプロダクトを中心に垣根なく集まれるのがあると良いと思う。
tweet
アイデアひとつというけれど、プログラミングの世界は本当にそうで、だからこそ、とてもワクワクできる。ソフトウェアはすごい。
tweet
企業の場合に、担当者が自社用のツールを選定する際には、機能一覧のマルバツ表で判断されることが多いように思う。おそらく、組織の沢山のユーザを考えると最大公約数の多い方が無難、また、特に思いをもっていなければ、機能の多寡で選ぶしかない、のだろうと思う。
tweet
機能を付ければ複雑になる。複雑になれば、初心者にはわかりにくくなる。ユーザの習熟にあわせて、機能も拡充できれば良いのだが。ほかのユーザを見て学べるような仕組みと。
tweet
あったら良いとか、やった方が良い、という程度のことに割いている時間も資源も本当はない。どれだけゆとりがあったとしても。本当にやるべきことだけをやる。
tweet
言葉を選んで、なるべく上手な文章に、と推敲して考え抜いたとしても、結局は、今の自分が出せる以上のものは出せないことに気づき、時間も限られているので、なるべく飾り立てず今書ける素直な文章を書くようになる。執筆は何度やっても、このプロセスを経てる。最初から素直に書けばいいのにね。
tweet
マーケティングで顧客のターゲッティングが重要なのは、集中すべきターゲットが決まれば、打てる手はおのずと決まるほど限られるからだと思う。手段の新発明はあまりない。だから、焦点をあてることの議論が重要。
tweet
ITの選定と投資がうまくいかない場合がある。パッケージでも選定の際のプレゼンの巧さやトップセールスで、製品が決まってしまった場合、初期に投資する額が大きくなると、実際に導入しようとした段階でうまくいかなかったとしても、もう後戻りできない。どうして企業はスモールスタートしないのか。