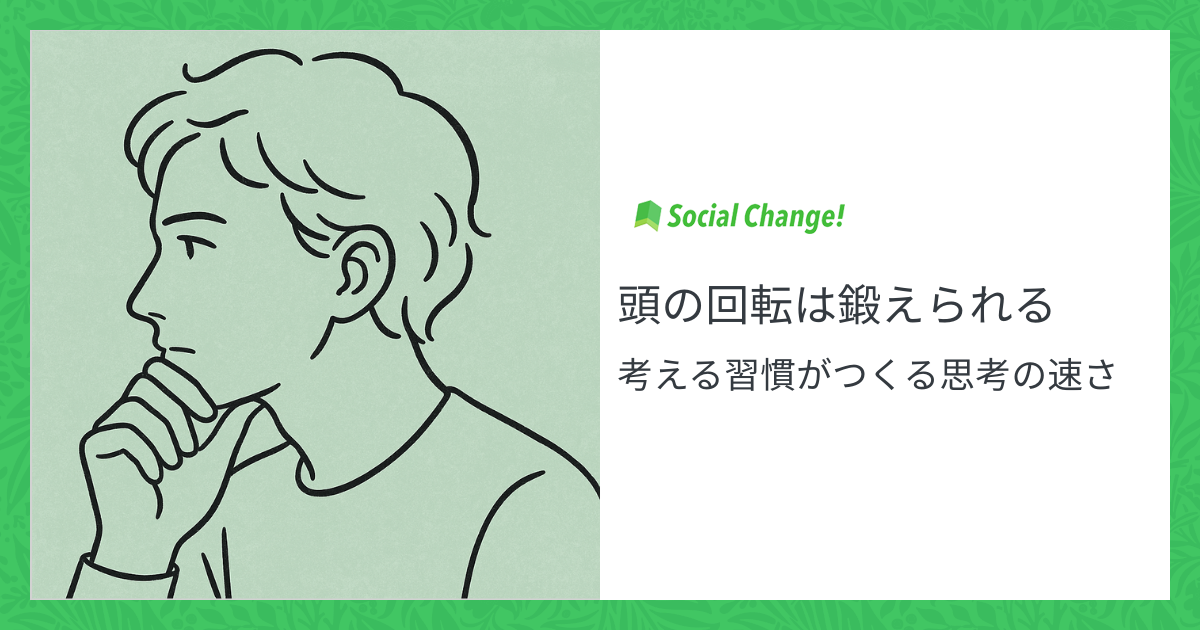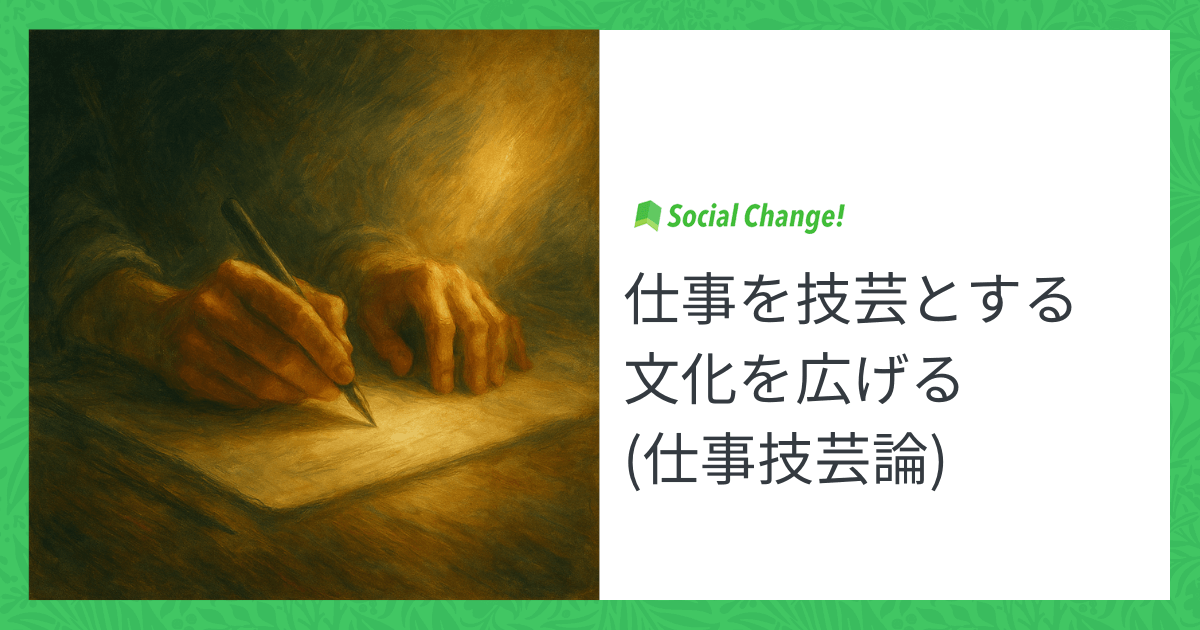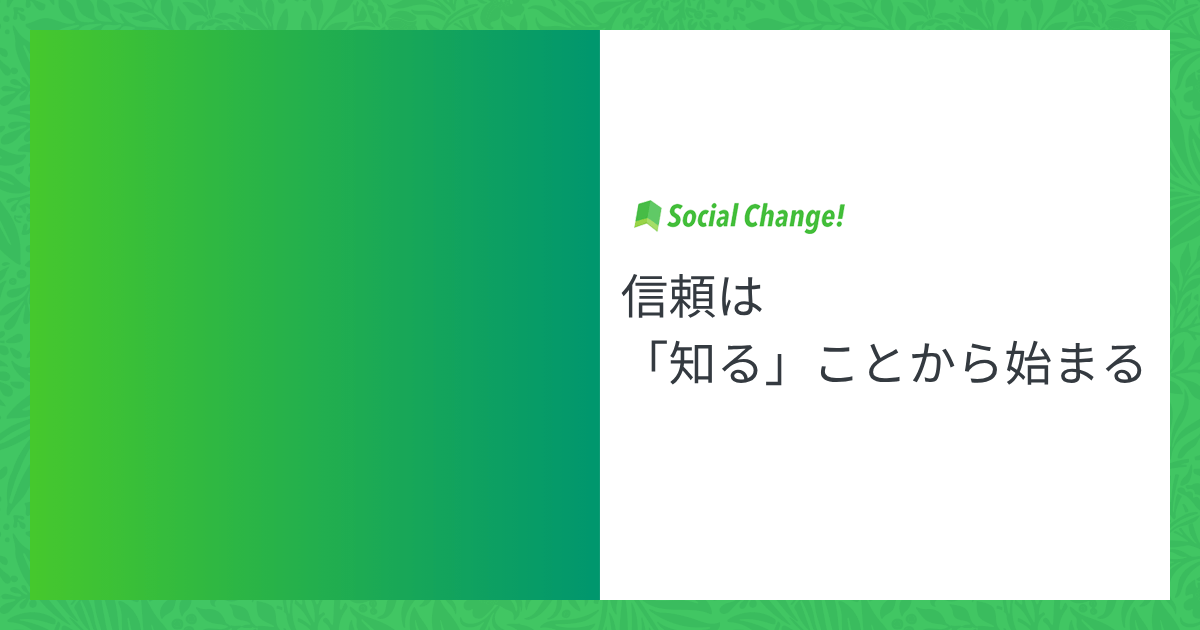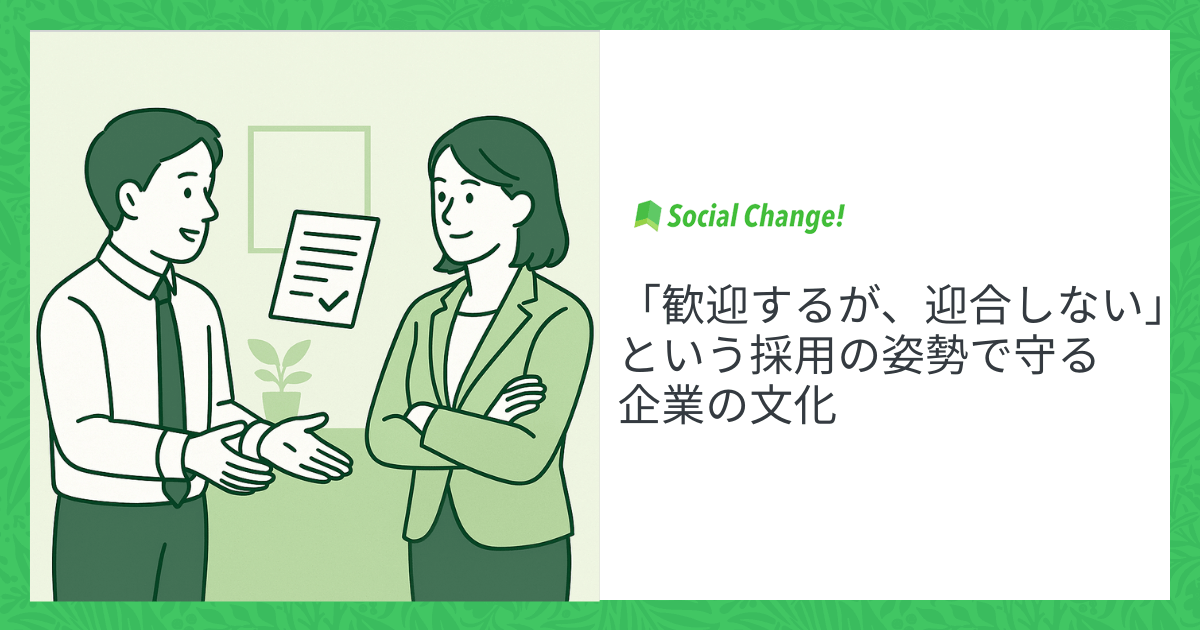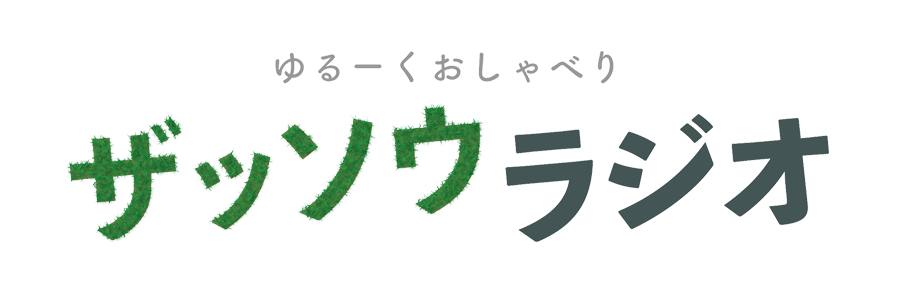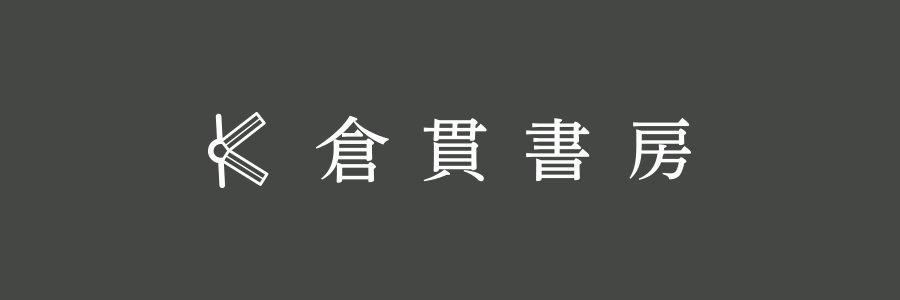ブログとソーシャルメディアによって、誰と働くかを事前に知れるようになった。あとは、企業の看板で仕事を取る習慣をなくし、属人的に人をアサインし続けることをコミットしたビジネスモデルを採用するかどうか、だ。
投稿
tweet
すごく頭のいい人たちが、メールというツールに縛られてるのを見て、個人のスキルにもイノベーションのジレンマが存在してるんだな、と実感している。出来すぎるからメール中心の仕事のスタイルを捨てられないんだろうな。でもきっと効率のいい方法を選択できる若者に負けてしまうよ。
tweet
議事録をまとめて送る、ということ自体が、まだオフラインとオンラインがつながっていない感じをうける。もっとシームレスにオンライン上のツールを使って、オフラインミーティングのメモをとることで、続きをオンラインでしやすくすれば良いのに、と思う。この込み入った話は140文字では出来ない。
tweet
共感できる文章を書くスキルって、ソーシャルメディア時代にとっても大事な要素なんだな。共感してもらえるのは、多少崩れた文章でも、いや、多少崩れてるくらいがむしろ良いのかもしれない。
tweet
ブログが目立つと色々な意見が出てくるよね。真摯な姿勢での反論や批判、疑問ならちゃんと正面から議論したいなーと思うけど、いわれなき貶めの言葉が含まれてると、そんな気も失せる。もし実際に目の前に相手の人が居ても、そう言えるかってことは、ソーシャルメディアの時代に重要な判断だと思う。
tweet
ブレストで大事なことは、自分の意見なんて・・と、諦めたりしないこと。そして着地点が見えなくても、妥協しないこと。今日は全員が発言した良いブレストができた。
tweet
何か投資する際に、ギャンブルでなく、お互いに信頼関係を少しずつ醸成していく方法はないものか。結婚前なら同棲するとか、就職ならインターンとかあるけど、共同事業ならどうするか。
tweet
ブログの執筆は、やはり一人の場所でするのが自分には向いてる。ブログのアイデアは、自分との対話から出るし、目の前にいない人に伝えたい思いが原動力になるから。あと誰かが近くにいると、コミュニケーション欲求が満たされてしまう。
tweet
誰かの何かを始めたきっかけの話を聞くのって良いね。みんなのきっかけを聞いていくと、誰かに影響を受けたということが多い。人が何かをするきっかけは人なんだな。始めたなら、次のきっかけを与えられる人になりたい。
tweet
仕事をドライブしていく源泉はあくまで情熱だと信じてるが、会社である限りは、ビジネスモデルもオペレーションもロジカルでなければならないし、そうでなければ続かないと思う。
tweet
プログラマとしてモノづくりをしてきた人間としては、経営という自分で手を動かさない仕事をしていると、日々学ぶことは多いけれど、本当は自分一人の市場価値は何だろうかと思う時が時折ある。
tweet
ソフトウェアの「わかりやすさ」とは何か。マニュアルがあれば良いものではない。提供する相手によって変わってくるはず。わかりやすさを左右するパラメータは、デザインか機能の数か。
tweet
何かを始めるということは、さほど覚悟のいることではなく、本当に覚悟のいることは、何かをやめるということだと思う。そういえば、30歳になった時、自分に偽ってまで周りにあわせることをやめたと思い出した。
tweet
昔から今もいるけど、エンジニアやベンダーがお客様と直接メールや話をするのを嫌がって伝言役をする営業がいるけど、何故なのか理解できない。間に入ることしか自分の価値がないと思っているのか。
tweet
プログラマを目指そうというときに、勉強するのにどうすれば良いかを最初に相談する相手で、その人のプログラマとしての道筋がほぼ決まる気がした。学ぶ言語は何でも良いとは思うけど「初心者だから」という理由でRubyよりPHPを勧めるのは違うんじゃないか。
tweet
お客様やパートナーとのSkypeミーティングの良いところは、本当に移動しなくて良いところ。移動して会議だったらと思うと前後の時間で出来たことが出来なくてぞっとしてる。あと、会議の直前まで、ちゃんと仕事できるので、開始が遅れてもボーッと待つことがない。移動と会議は本当に無駄が多い。
tweet
これまでのSIビジネスの本質は保険屋だ。リスクを抱えてもらえるだけの体力のあるベンダに、リスクを渡したい企業担当者が発注する構造。安心のために高いフィーを払う。これまでのデータセンタービジネスも保険屋だったと知った。絶対に落ちない止まらないという保証を売っていた。どちらも幻想だ。
tweet
新規事業を考えるとき、競合がいる時点で諦める人がいるが、それは違う。競合のいない市場はそもそも市場が無い可能性が大きい。競合に勝てる算段がないならやめれば良いが、競合にどうすれば勝てるかを考えるかを放棄しては、そこでおしまい。