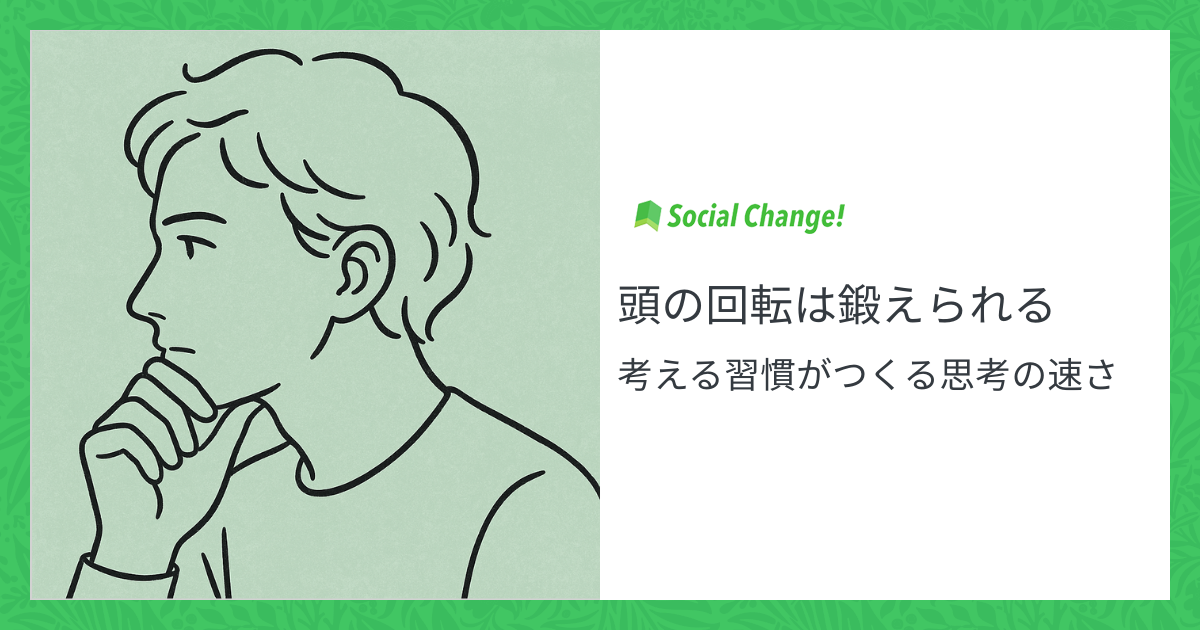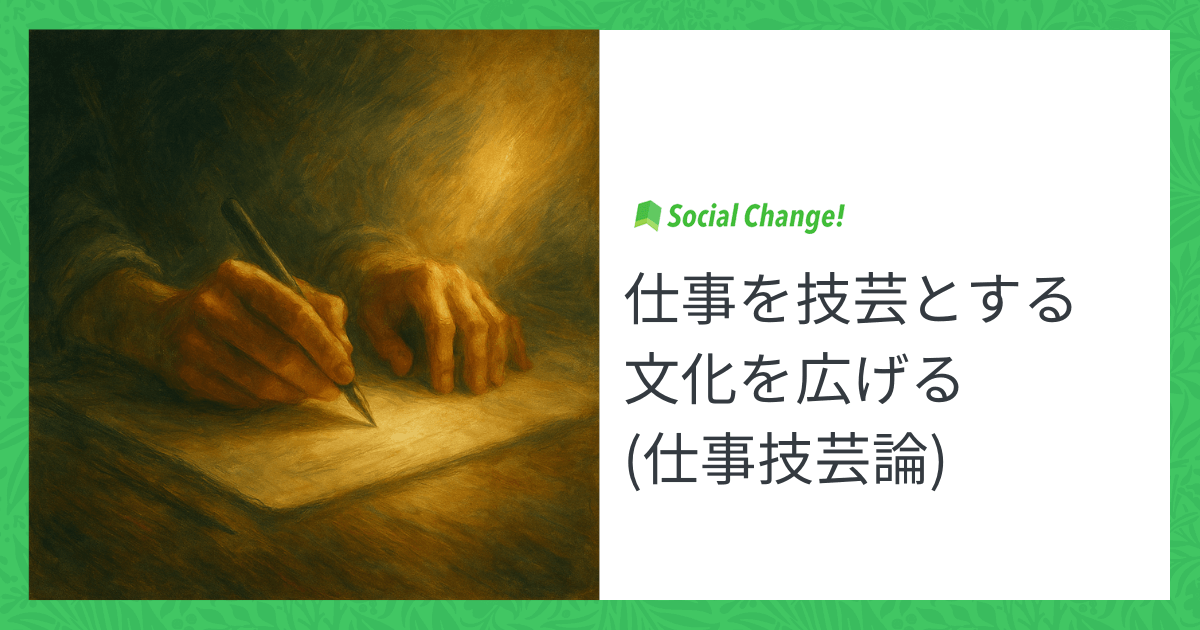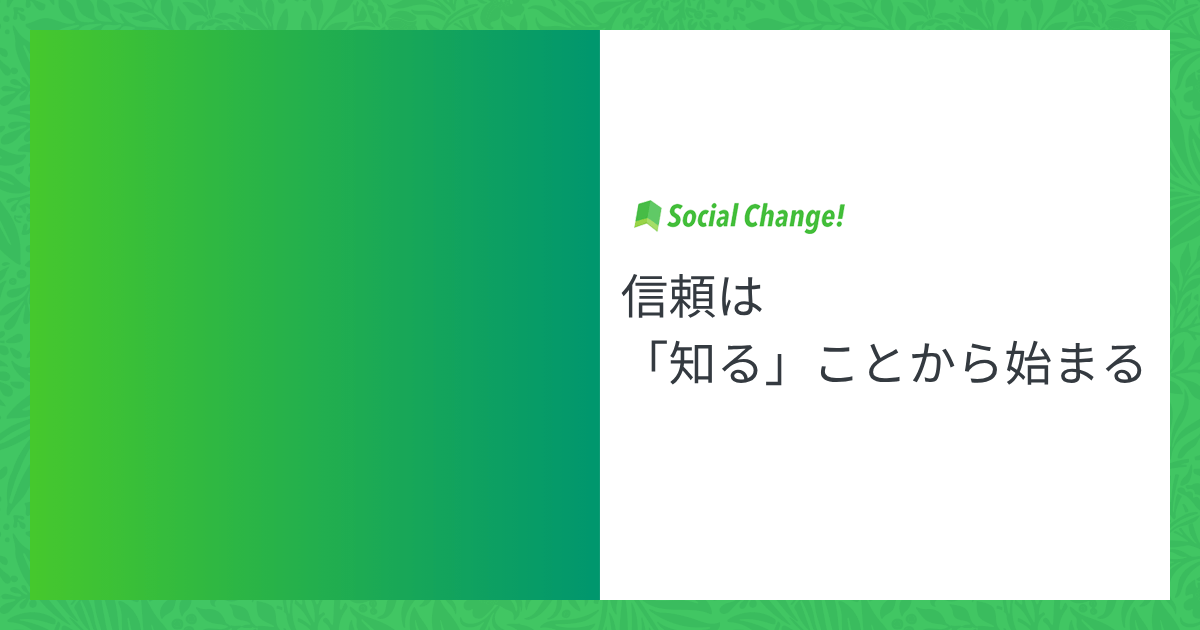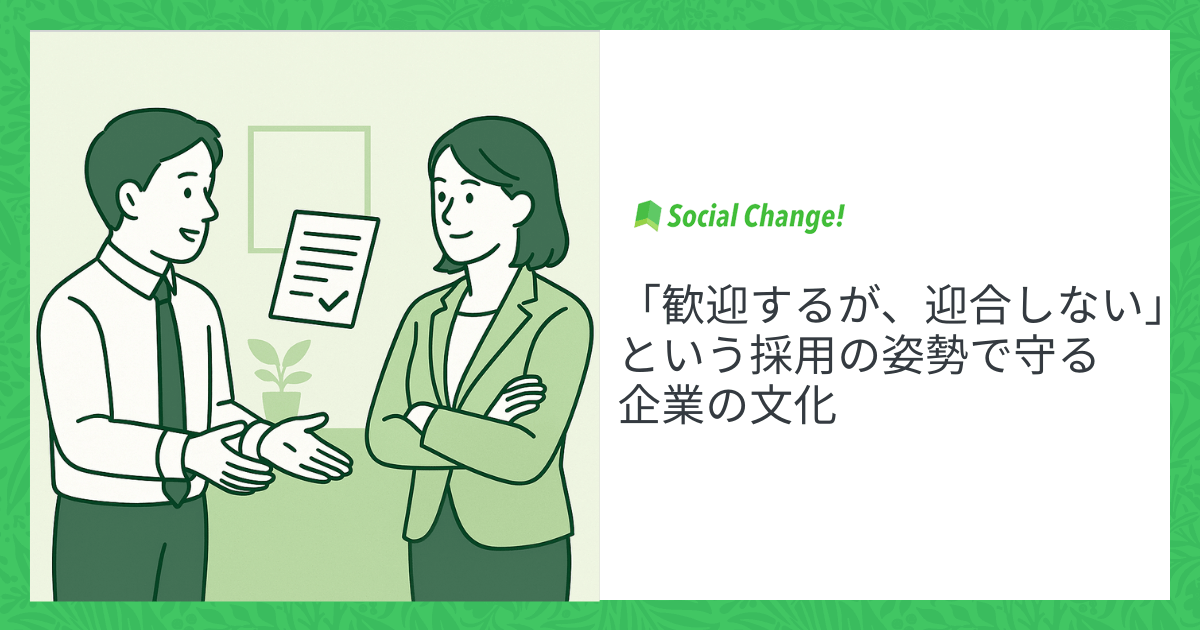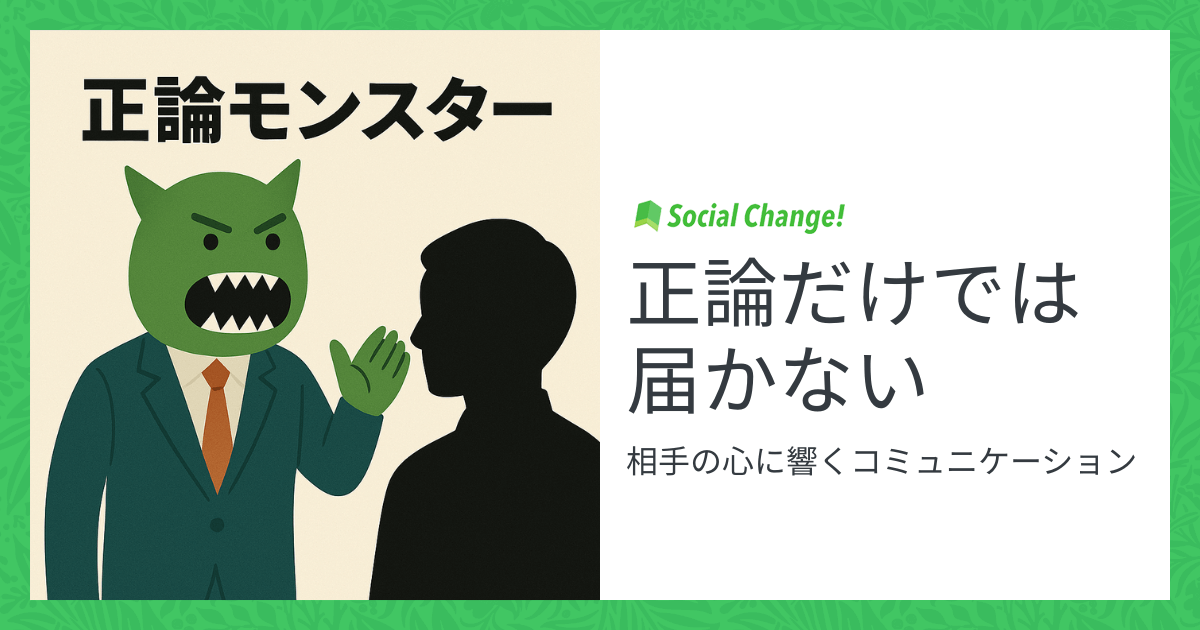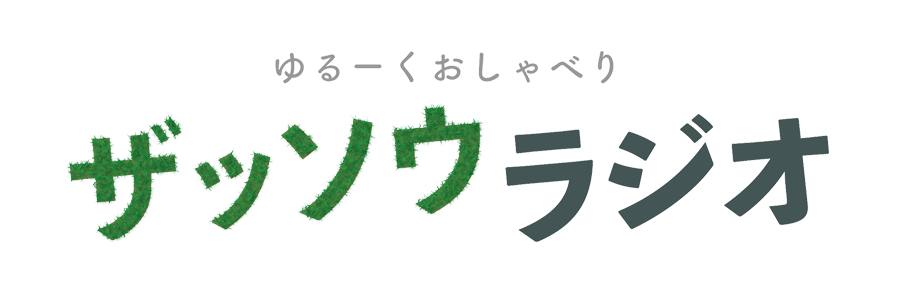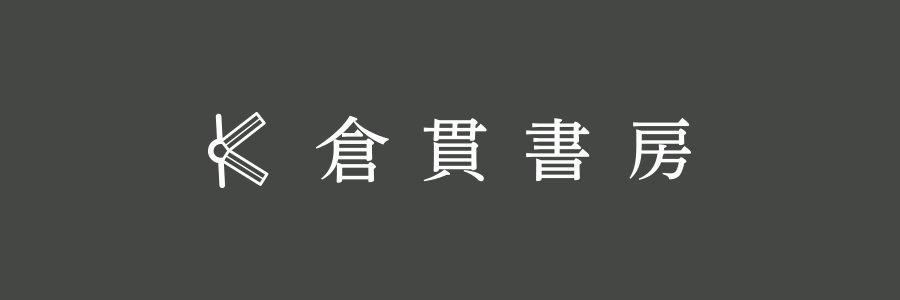組織が大きくなればなるほど、意思決定に時間がかかるようになる。特にトップが強権でなく、役員の合議で決めようとする場合には。失点をしないように守るタイミングならそれで良いが、得点は決められない。大きいだけの組織からはイノベーションは産まれない。
投稿
tweet
アジャイル開発を「速い安い旨い」みたいな表現されるのに、いつも違和感を感じる。何を犠牲にしてるから安くて、その速さは何の価値を産むためか、というところを伝えていない。
tweet
企業組織の大きさを小さくすれば、ぶら下がる余裕も逃げ切る時間もない。今後、生き残れる企業は、資産で安定した巨大な企業よりも、フローを重視した小回りの効く企業ではないかな。時代的にも技術的にも、小さいことが不利になることが減ってきてるように思う。
tweet
大企業にとって、若手の「ぶら下がり社員」も大変な課題だけど、従来からある、ある一定の立場になって守りに入ったベテランの「逃げ切り社員」も大きな課題。特に中途半端に権力を握った「逃げ切り役員」最悪だ。
tweet
ソーシャルを本当に理解してるのは、リアルな世界を普通に生活してる人たちなんだと思う。ソーシャルがウェブの世界で普及して普遍的に広まれば広まるほど、それがあることが当たり前に感じるから、ソーシャルは元々あるものなんだろう。
tweet
ソフトウェアのアイデアなら、考え過ぎずに、思いついたシンプルなままのアイデアを素直に実装してみる方が良いと思うな。だからプログラマが最も成功に近い。
tweet
人材育成について学んだこと。失敗の経験も活かすことは重要だけど、人がより成長できるのは、成功体験からの自信。小さな成功で良いので、コツコツと目標を達成していくことは大事。そう思えるようにすること。
tweet
外部環境の変化は良い悪い含めて何をもたらすかリスクがある。自分の意思やチーム、目指すビジョンがあるなら、外部環境になるべく影響されないように、変化する前に自分から動くこと。それが、この数年で学んだことのひとつ。
tweet
ソフトウェア産業においては、イノベーションを担う役割は部署で分けて持つのではなく、個人やチームの中で、その為の時間を持つ方が有効だと考えている。現場には改善の意識だけでなく、改革の意識が必要。
tweet
数字のないビジョンはただの希望だけど、数字だけのビジョンはただのノルマだ。その未来の状態をどれだけ具体的にイメージ出来るか。言葉と数字、両方必要だと。
tweet
今まで見てきたビジョンやゴールで、売上高いくら、とか、業界何位とかというものには、全く心が動かされなかった。そんなのを提示する経営者はそんなビジョンで社員が奮い立つと本気で思っているのか。
tweet
海外のウェブサービスが凄いのはわかる。そのままでは勝てないことを認める。国際的な人材にならないと将来価値がないのもわかる。その上で、日本ならではの良さみたいなものも考えられないのかな。
tweet
多くの人が就職や転職の時には、どんな会社か色々と調べたり、自分のキャリアとあうか悩んで選ぶのに、いったん会社に入ってしまったら、人事異動とか組織編成とかに無頓着だったり受け身だったりするのが理解出来ない。「誰と」が重要なら自分でハンドル握るしかない。
tweet
どんな仕事をしたいか、も重要だが、誰と仕事をしたいか、も重要な価値観な筈だ。私はそのコントロールを自分で持てるようになりたかったんだと思う。組織に従い現場にいる限り、そこには不可抗力が働くから。
tweet
10年後20年後にどんな仕事をしていたいか、から逆算すれば、今どんな経験をすべきか、自ずと見えてくるのか。
tweet
プログラマの仕事をしてても、そのキャリアが袋小路に見えて、将来に不安を感じるようなら、極めようと努力する気持ちも萎えると思う。プログラマで生涯働けて給与があがっていく仕組み、年功序列でなく弁護士のように腕によって格差がつく仕組みがあれば良いか。
tweet
子供の頃は簡単に言えてた、将来は何になりたいか?って質問に、大人になってからも答えられる人は強いと感じた。自分のビジョンを持ってる。
tweet
経営と現場でわかりあえない訳ではなくて、そもそも人と人がわかり合うには時間がかかるものなのだ。そうなると、有限の時間を有効に使うのに適したピラミッド構造になってしまったんだろう。