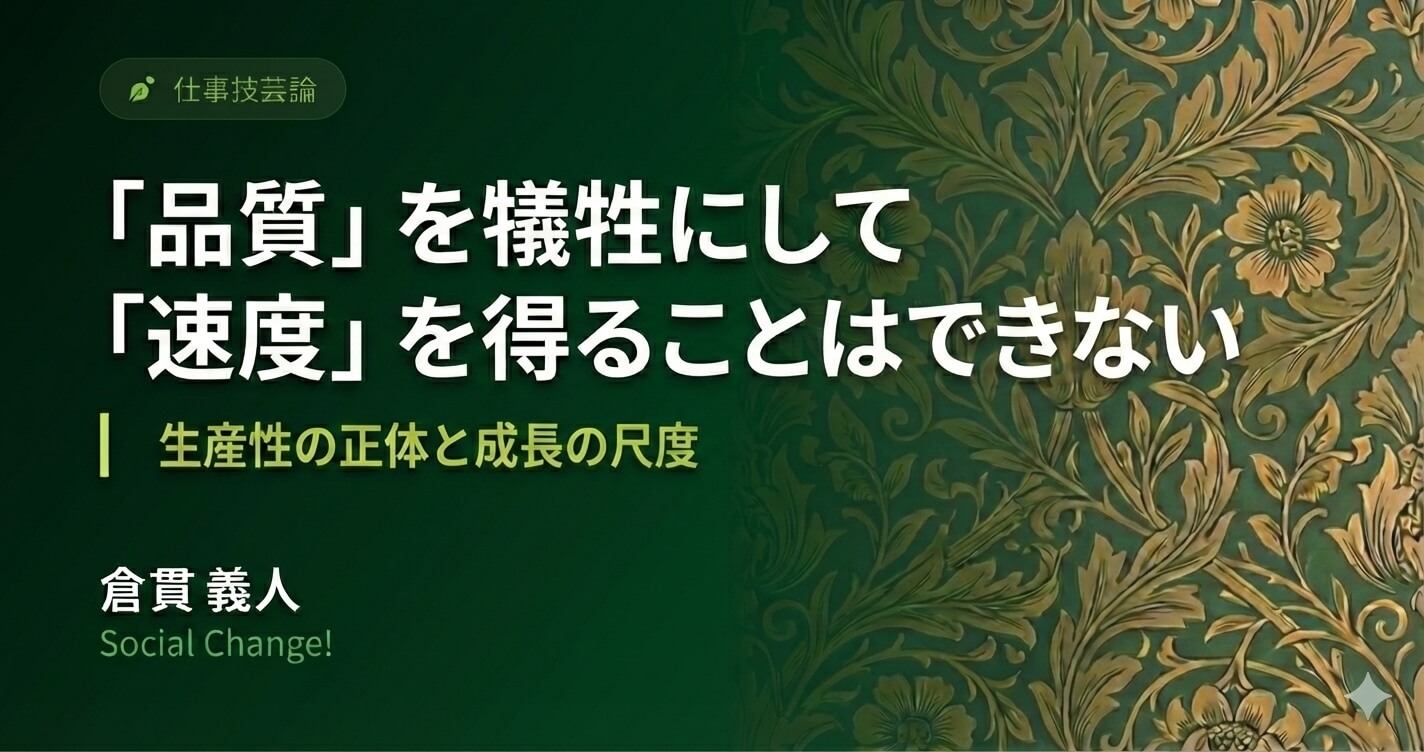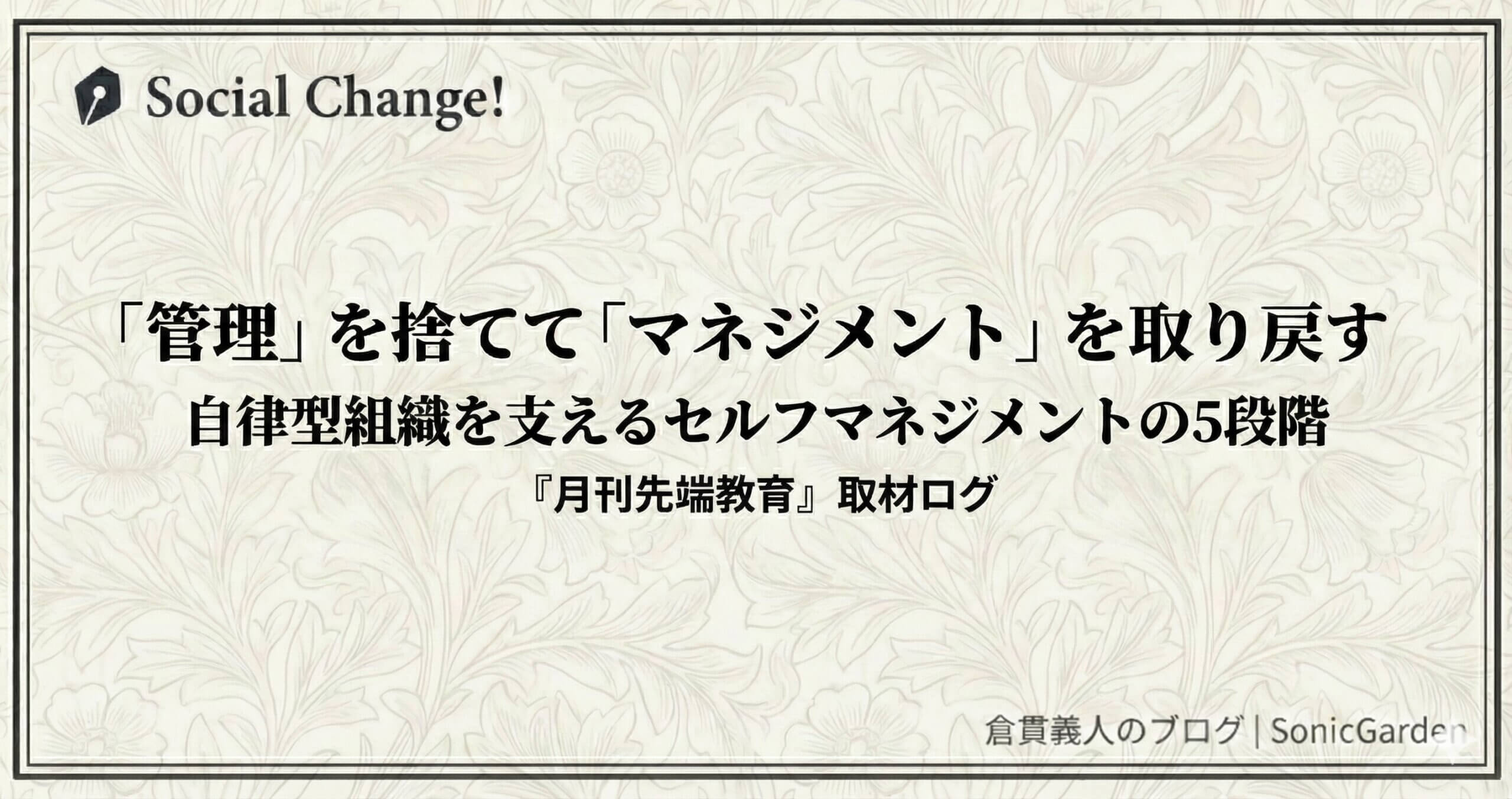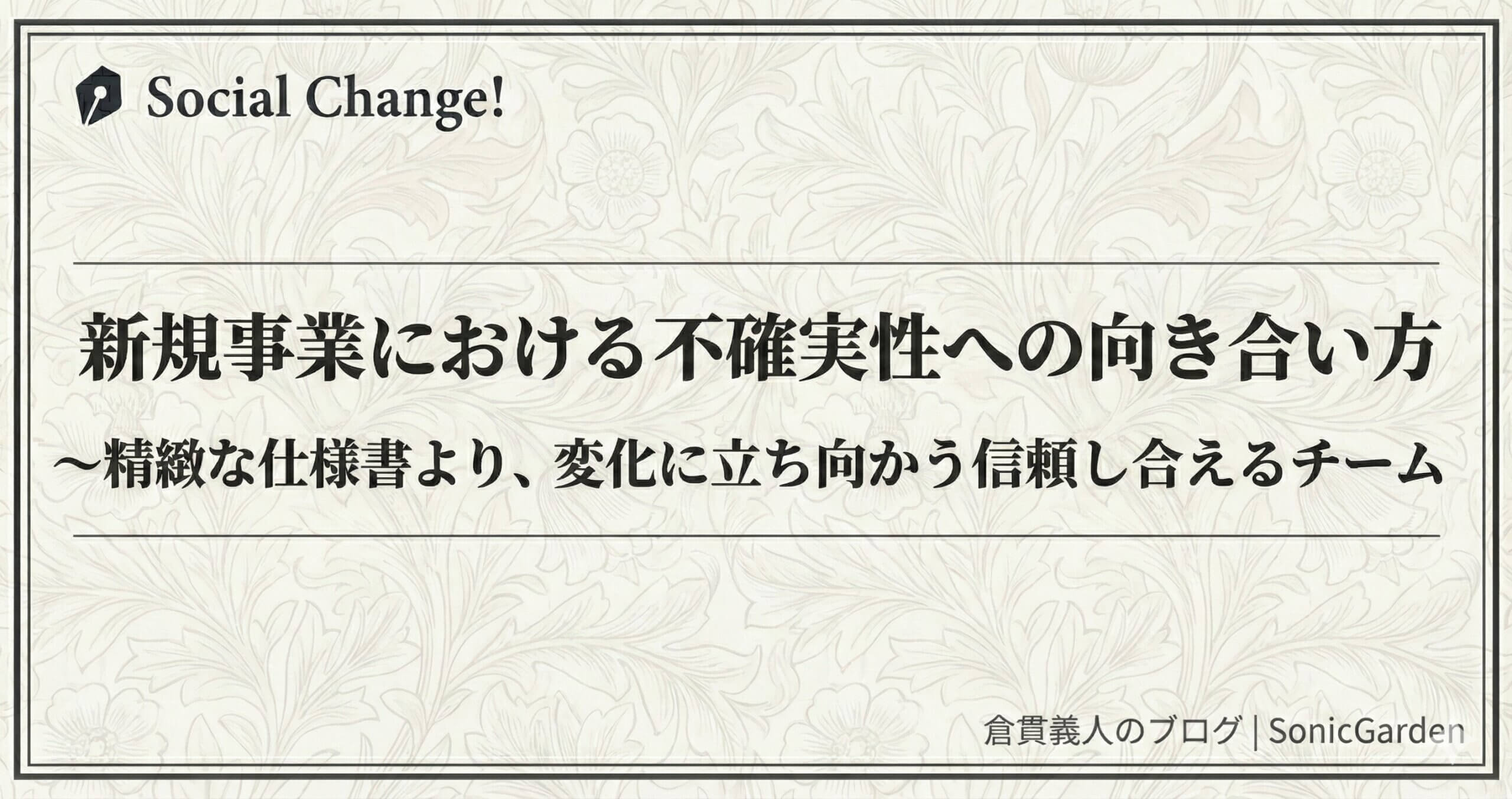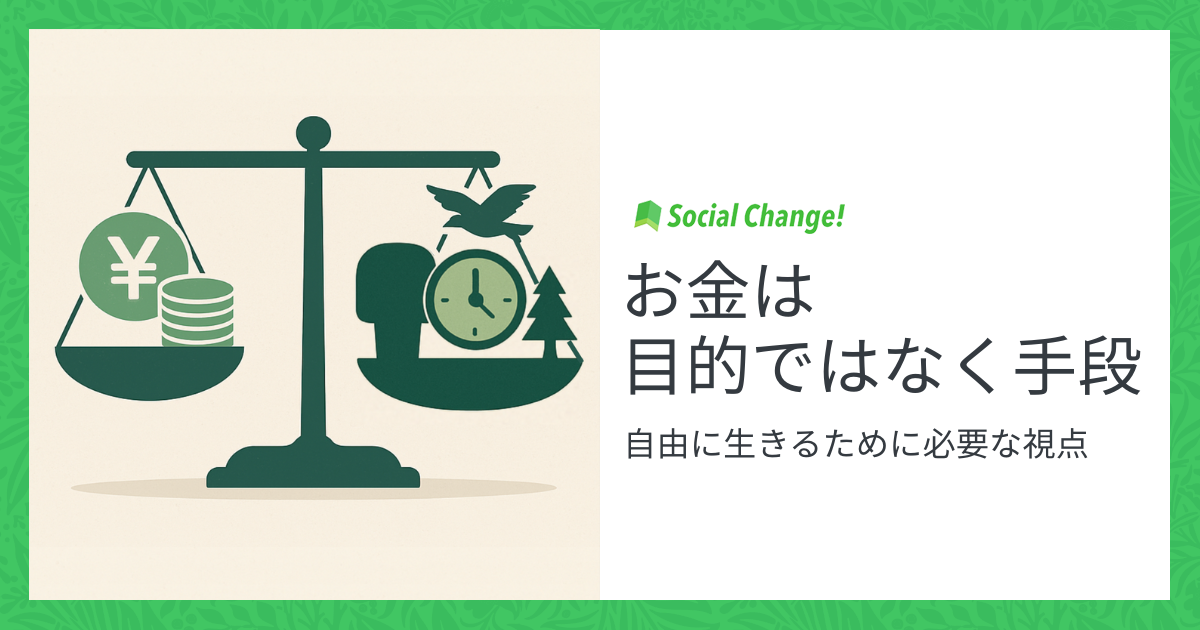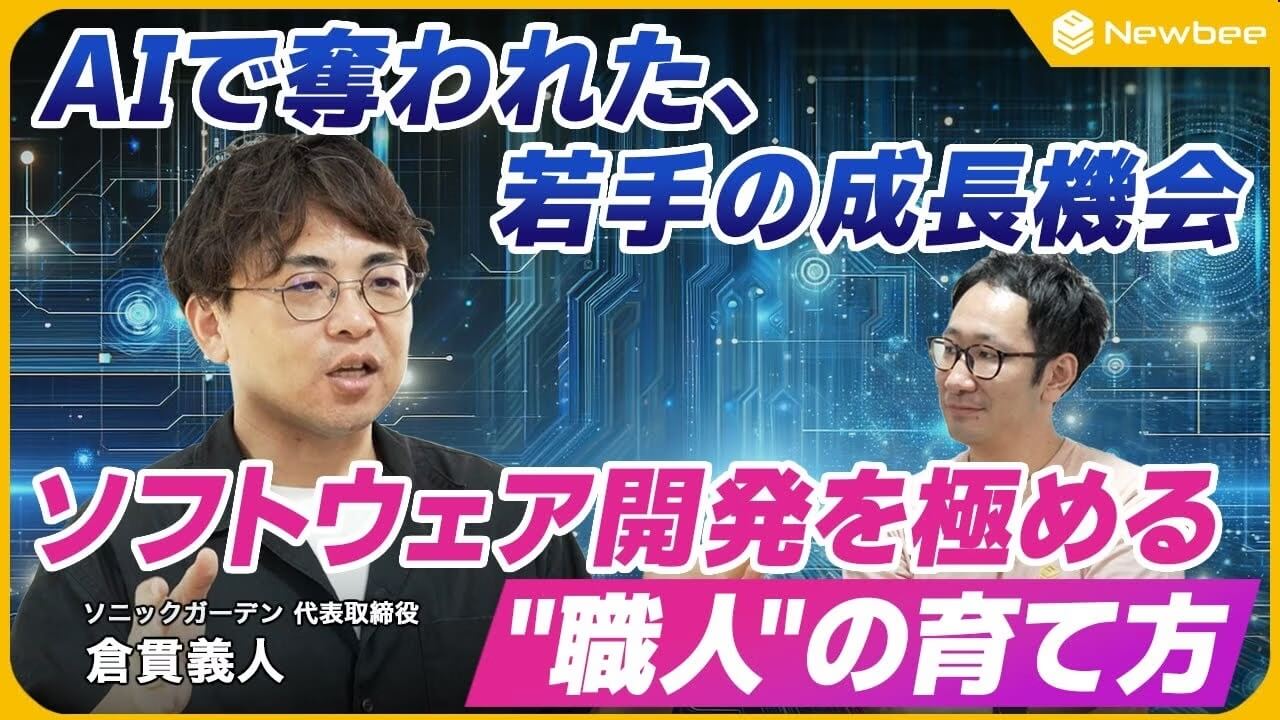人を育てる仕組みから、組織を育てる仕組みへ〜現代に再発明した徒弟制度3年の学び
倉貫 義人
人を育てることは、どんな組織にとっても大きな課題の一つです。
評価や業績を意識する関係の中では、どうしても短期的な成果に引っ張られ、長期的な育成が後回しになってしまうことも少なくありません。また、昨今の上司に求められる傾聴を重視するあまり、言うべきことを言えないなんてことも。
人材育成については、私たちソニックガーデンでは3年前から「徒弟制度」という形で取り組んできました。上司と部下ではなく、親方と弟子という関係性を軸に据え、実践を通じた育成の仕組みです。
本稿では、徒弟制度に取り組んだ3年間を振り返り、そこで得た育成や制度、企業文化などに関する学びについて書き留めておきます。
なぜ今「徒弟制度」を始めたのか
徒弟制度という取り組みを始めた背景にあったのは、従来の上司と部下の関係では、人材育成がうまくいかないと感じたからです。
上司というマネージャ像では、育成よりも成果に着目してしまったり、指導するにも遠慮が入ってしまうなどのバイアスが働いてしまいます。ベテランのプログラマにしても、人のマネジメントをしたい訳ではないし、ましてヤル気を引き出すことまでして教えたくはありません。
また、それまで管理ゼロのフラットな組織を志向していたこともあり、まだ経験の浅い人に対しても、ベテランと同じように扱おうとしてしまいがちでした。ただそれでは人は育たなかったのです。なぜなら、そこには「指導する・指導される」という前提がなかったからです。
そこで、上司と部下ではなく、師匠と弟子という形に捉え直したのです。ちなみに社内では、宮大工の世界観をモチーフに師匠のことを「親方」と呼んでいます。親方と弟子の双方に「指導する・指導される」関係であると認識を揃えることで、動きやすくすることが狙いでした。
そして、研修ではなく徒弟制度としたのは、そもそもソフトウェア開発は「技芸」に近いと考えているからです。スポーツやアートのように、知識だけでなく訓練を積む必要があるものであり、その上達のために効果的なのは熟練者からのフィードバックです。それを、育成の仕組みに取り入れたいとも考えました。
「徒弟制度」で何をしているのか
徒弟制度と聞くと、何か古めかしく、人によっては良いイメージを持たれないかもしれません。しかし、そうしたことはなくて現代に合わせてアップデートして導入しています。
私たちの徒弟制度で重要なのは、この親方と弟子の関係性にあって、あくまで若い人の成長を支援することが目的にあります。なので、古くからある徒弟制度にイメージされるような雑用ばかりだったり、師匠からの理不尽な要求があったりなどは、一切ありません。
では実際に、どのようなことをしているのか。それは以下の記事に詳しく書かれています。読んで頂ければ、弟子たちも大変だけど楽しく過ごしている様子がわかると思います。
参考リンク:「徒弟制度」って実際は何をしているの?——モダンな育成の場で成長する弟子たちのリアル

このように古くからある徒弟制度を、育成のためにフォーカスして、今の社会に合わせて再発明したので、「モダン徒弟制度」とでも呼んだ方が良いのではないかと思っています。
型を身につけた先にある責任と自由
徒弟制度では、いわゆる守破離でいう「守」の段階からスタートします。ソニックガーデンには、より成果を出すためのソフトウェア開発の型があります。その型を身につけることから始めるため、まずは親方の言うことを正解として取り組みます。最初は自己流のアレンジをしない方が良いとしています。
一方で、成長していくことを想定しているので、ずっと型を守らせることもありません。段階に応じて、自ら考えて動く部分を増やしていきます。徐々にできる仕事の幅が広がっていくほどに、大きな責任を担うことができます。
また、最初のうちはセルフマネジメントができない代わりに、親方がマネジメントすることになります。これも、徐々にセルフマネジメントを身につけていくことで親方の負担は減ると同時に、本人もリモートワークやフレックスなど自由を得ていくことになり、いずれ大きな自由を得て働くことができます。
究極的には、誰もが自律して行動ができ、自立することができる人同士が、それでも、それぞれの得意を活かし、背中を預け合うような、そんなフラットな組織が理想です。徒弟制度は、そこに至るための階段として位置付けています。
育成で最も大事なことは「観察」
3年間取り組んで強く実感したのは、「育成は再現性がない」ということです。一人ひとり成長の仕方もペースも違う。ただし共通して同じようなところでつまずくし、そこで伝えることも同じことだったりします。再現性はないが「型」はあるのです。
一人ひとりが違っている中で、親方が最も力を入れるべきは「観察」でした。
弟子たちの足並みを揃えるのではなく、それぞれの弟子にとって、楽勝ではないけれど、絶望するほど難しくもない、ちょうど良いストレッチな課題を出し続けるには観察は欠かせません。
しかも、結果だけを見るのではなく、プロセスを見る必要があります。プロセスを見ないでフィードバックするのは、アスリートのトレーニングで結果だけ見て「もっと良い結果を出せ」と言ってるのと同じようなものです。これがリモートでの育成が難しい理由です。
一緒に働いて、そのプロセスを観察するからこそ、適切なフィードバックができるのです。そこで、徒弟制度では親方と一緒に働けるような環境も整備しました。
親方は弟子の振る舞いで違和感を逃さないようにするためにも、観察し続けないといけません。気になった振る舞いを見つけたら、その瞬間に確認して、必要ならばフィードバックや指導をするのが効果的です。
モダン徒弟制度では、厳しく指導する必要はありませんが、型や姿勢についての厳密さは欠かすことができません。
育てるのではなく、自ら育っていく
徒弟制度を始めて3年が過ぎたことで、一番最初に弟子として働き始めた1期生たちは、人によって成長のばらつきはあるものの、誰もが今や立派にプロジェクトの中で成果を発揮できるようになりました。それに続く後輩たちも、育っていってます。
結果として徒弟制度としては、一定の成果を出せたと思いますし、その再現性もありそうです。一方で、少数かつ弟子入り半年以内ですが、途中でリタイアして辞めてしまう若者もいたのも事実です。
育つ人との大きな違いは、やはり自ら決めて、自ら動けるかどうかです。そもそも、徒弟制度という育つための環境に、自ら決めて参加している時点で、非常に主体性があります。なので、ほとんどの人が続けてくれてます。
続けるというのは、上達のための重要な要素です。やる気を出して頑張ることも大事ですが、頑張り過ぎた後にしばらく休んでしまう位ならば、淡々と休まず続けていった人の方が伸びています。「継続は力なり」とはよく言ったものです。
育成の本質は、自ら育とうとする人に機会を与え、見守り、大きく横道に逸れる時だけフィードバックしていくことだと思うようになりました。車が進もうとしていない時に、フィードバックが存在しないのと同じです。車を走らせるのは自分です。
残念ですが強制的に人を育てるなんてことは、できない。育つ人は育つし、育たない人は育たない。結局は、本人次第なのです。組織としてできることは、より育つように支援することだけなのだと実感しています。
タテ・ヨコ・ナナメの関係性で支える
徒弟制度にしたことで良かったことは、親方と弟子の関係性が、上司と部下のそれよりも強固なものになったことです。弟子からすると、親方の言うことは絶対で、仕事の実力において何も敵うことのない相手です。
だから、尊敬や畏怖の対象ではあるのですが、一方で、長い時間を一緒に過ごすと、親方の様々な側面にも触れることにもなります。そうすると、親方でさえ同じ人間なんだと思えるようになります。
それが進むと、弟子なのに親方のことを冗談まじりにイジったりすることもしたりして、とても良い雰囲気になっていきます。逆に言えば、そうした関係にまでならないと続けられないでしょう。
また、弟子同士の横の繋がりも大きな支えになりました。熟達への遠い道のりを、ただ独りで進んでいると思うと、不安にもなるし、諦めてしまいやすくなります。しかし、同じように歩む仲間がいれば、頑張る気持ちも湧いてきます。
あるとき、落ち込んでいる弟子がいると聞き、別の拠点の同期の弟子たちがわざわざ休みの日に励ましに行った、ということもあったと聞きました。
リモートワークではなく、親方ハウスで一緒に働くということも、この横の関係性を築く事に効果を発揮したと思います。
そして、親方と弟子の縦の関係、弟子同士の横の関係に加えて、人事とのナナメの関係もありました。どうしても親方には言えないし、弟子同士でも難しい相談の場合、人事が受け止められる形を作ったのも、大事な取り組みでした。
徒弟制度で最も育ったのは親方だった
若者の人材育成のために始めた徒弟制度ではありましたが、良い意味で想定外だったのは、親方の役割を担った人材が大きく成長したことです。
弟子を育てることは、型はあれど一人ずつ違うし、それぞれの抱えている悩みや課題もバラバラ。それまでプログラマとして取り組んできた技術的な問題解決とは違って、まさに正解のない仕事が育成でした。
その経験は、人間として大きく育つ機会にもなったのです。これも弟子と同じで、親方を育てた訳ではなく、難しい仕事に取り組んだことで親方が勝手に育った感じです。
成長した観点の一つが、経営と近い視座を持つようになったことです。
弟子の育成は親方に丸投げするのではなく、定期的に行われる私と親方たちとのふりかえりの中で、一緒に悩むことを大事にしてきました。最終的な現場での判断と責任は親方にありますが、その前提となる認識については、十分なすり合わせをしてきました。
その結果、親方たちは私と同じような視座で考えてくれるようになったのです。私自身も、複数の親方たち、その先にいるさらに多くの弟子たちの具体的な様子を知ることで、それを抽象化・言語化することから育成について学ぶことができました。
人が育つ環境をつくれば組織も育った
これまでのフラットな組織から、徒弟制度で伸び代のある若者の採用で必要になったのが、評価や等級などといった人事制度をはじめ、住宅手当や寮の検討といった福利厚生につながるような様々な制度です。
特に、人事制度は非常に難しく、3年経った今もなお完全な制度とはなっていませんが、大枠の方針は作ることができました。それが、目標管理とは違ったキャリブレーションという仕組みです。
また、弟子たちが育つための機会を作っていくために始めたのが、弟子ハッカソンです。月に1日は、弟子たちがテーマに沿ったアプリを作って発表会をするイベントですが、毎月やっていくことで、弟子たちの良い経験の場となりました。
このハッカソンを続けてきたことで、もはや月1の当たり前のものとなってきて、後から入ってきた弟子たちも、何の疑問もなく取り組むようになっています。つまり、私たちの文化になったのです。
「当たり前」が文化になる。つまり繰り返すことで習慣になり、習慣が文化になる。これは制度を超えた大きな力です。同様に、若い人を育成することも、何も特別なことではなく、日常の風景となりつつあり、これも文化として根付き始めているように感じます。
親方というミドルマネジメントが機能するようになったことも、会社としての様々な制度が整ったことも、より良い文化が形成されたことも、副次的ではありますが、徒弟制度で得られた効果といえます。
思想を伝え、文化を育てるための徒弟制度
徒弟制度を続けて実感したのは、育成の制度とは単なる仕組みではなく、文化を育てる装置だということです。人を育てているつもりが、いつの間にか組織を育てていたのです。
だからこそ制度を作って終わりではなく、関係性や文化の中でこそ制度が生きる。これこそが3年間の大きな学びでした。
そんな徒弟制度には、私たちソニックガーデンの思想が詰まっています。ただ人を育成するだけで良ければ、別の手段もあったかもしれません。会社の経済性だけを考えたら、そもそも育成をしない方が手っ取り早かったかもしれません。
それでも、徒弟制度を続けてきたのは私たちにとって大事なことは、自分たちの思想と、その有効性を示すことでもあったのです。この3年間という期間での学びで、それが少しでも示せたとしたら幸いです。
徒弟制度という言葉は古く聞こえるかもしれませんが、人を育て、組織を育てる営みは、どんな時代のどんな組織にも共通する課題であり、可能性なのだと思います。
【お知らせ】
ソニックガーデンの「徒弟制度」が、NHK総合のテレビ番組で紹介されます。
実際に親方と弟子が働いている様子が、ドキュメンタリー形式で放映される予定です。
ぜひご覧ください。
放送日:9/10(水)23:00〜23:30
NHK総合「コント×ドキュメンタリー 笑う会社革命」