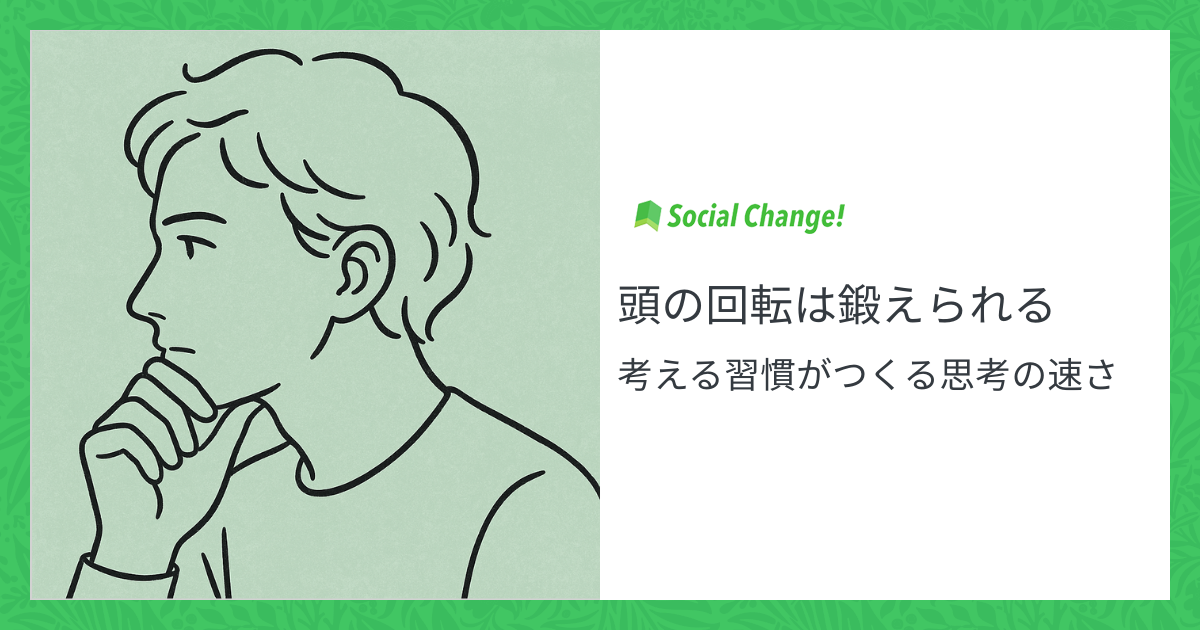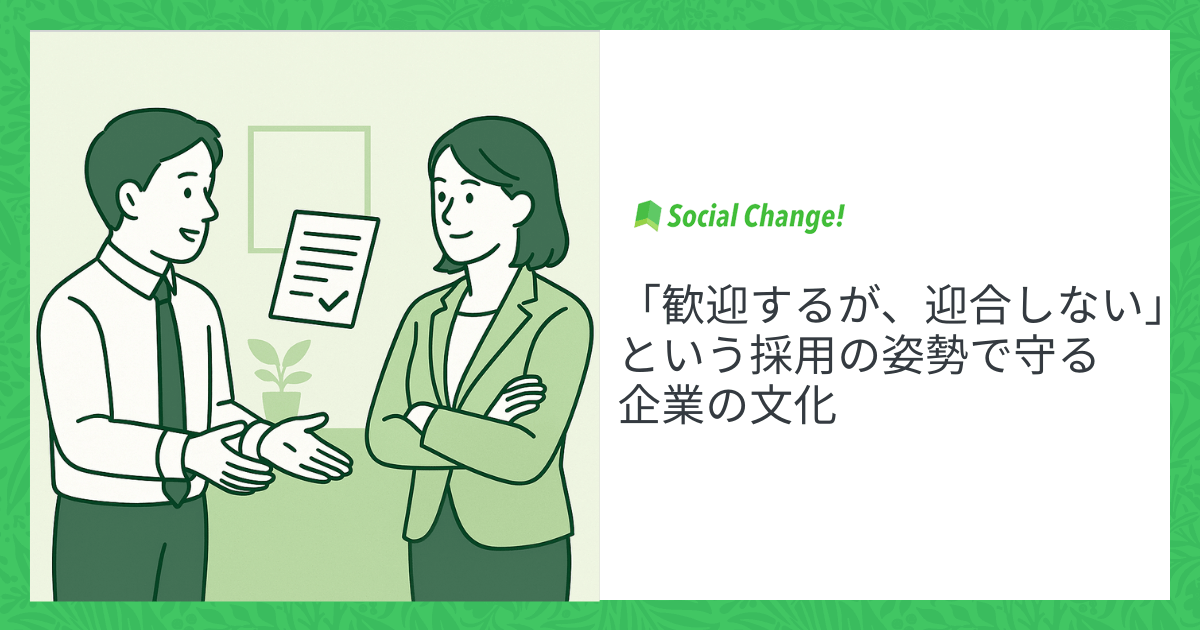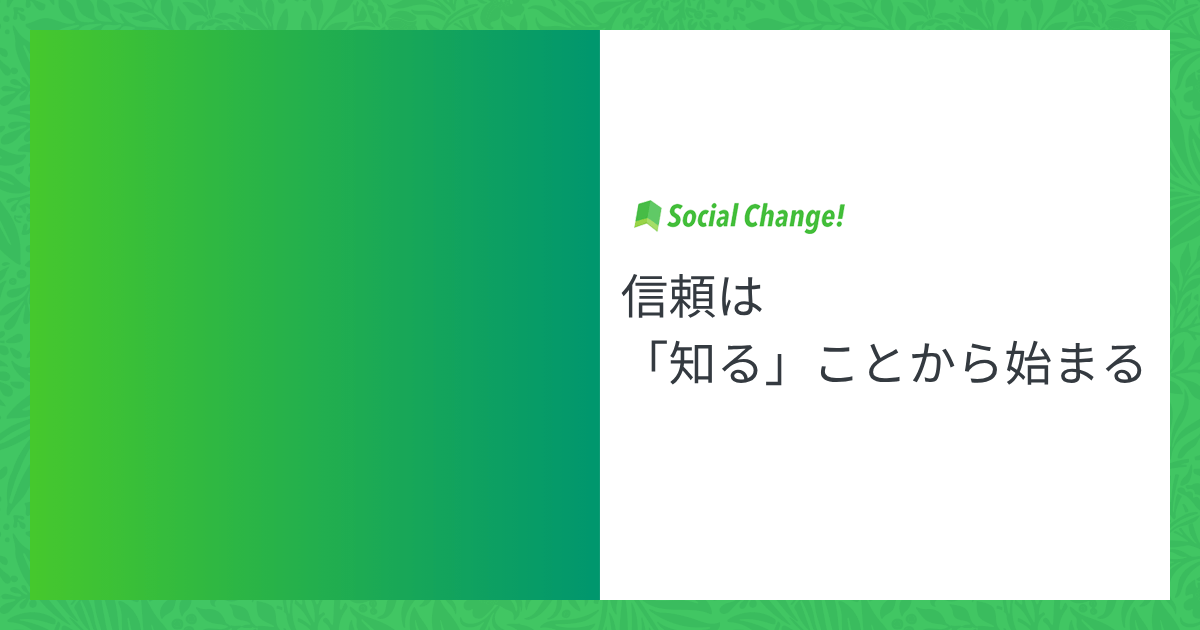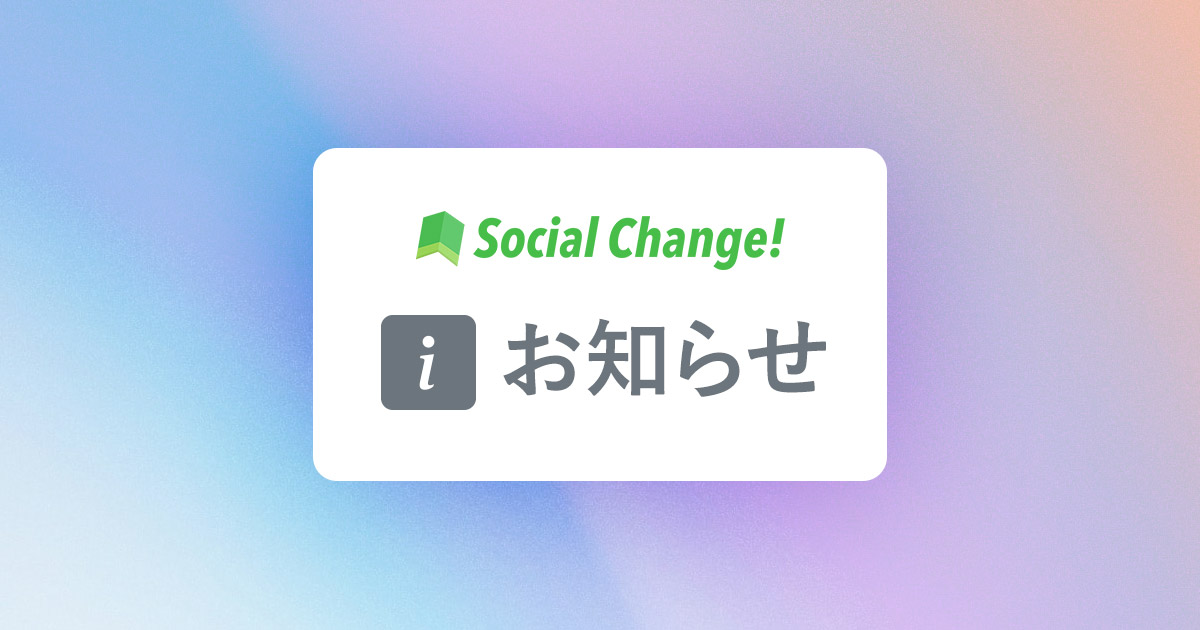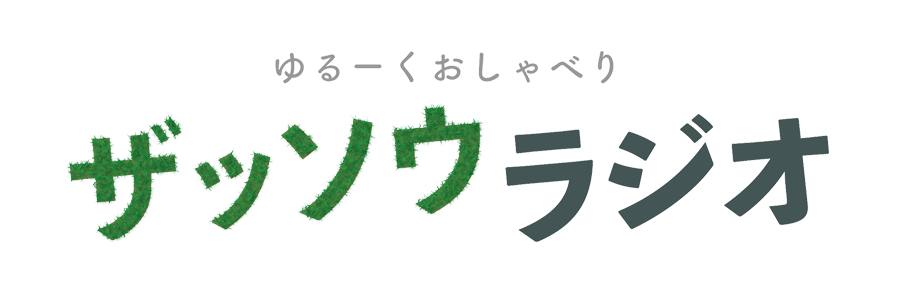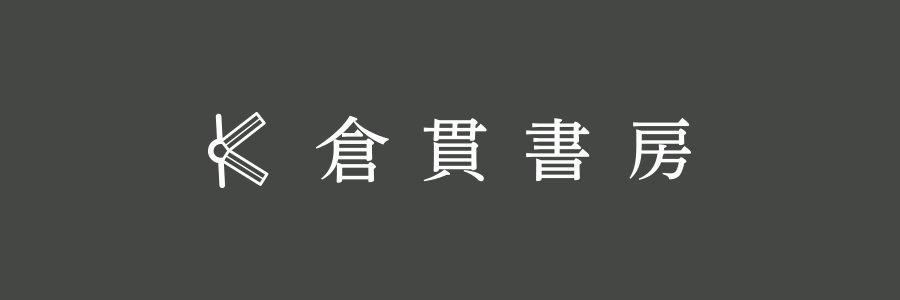リテラシーの有無は、ただ知識があるかないかだけではなく、何か問題が起きたり、未知の状況に遭遇した際に、過去の経験から類推して考えて、一人で解決できるかどうか、ということ。もし、ITの世界で事業を興そうと考えるなら、ITと事業開発に関するリテラシーと、それを支える経験が必要だろう。
投稿
tweet
なんのために破壊的イノベーションを起こそうとするのか。それまでの常識だった世界をひっくり返すためで、それまで弱者だったものが、ゲームのルールを変えることで一気に強者になるためだ。トランプの大富豪で言えば革命を起こすのだ。だから強者であったものからはイノベーションは産まれないのだ。
tweet
自分だけが出来ていた仕事を、他の誰かが出来るようにすることは、自分の仕事を失うという恐れを産むかもしれない。しかし、チームの理想が高ければ、やるべき仕事なんて幾らでもあるし、仕事を譲っていくことで、新しいことにも挑戦できる余裕ができる筈だ。それこそ上司やベテランの務めではないか。
tweet
セルフマネジメントのチームを目指すならば、すぐに結果が出ないが未来をつくる大事な仕事に、経営者だけが取り組むのではなく、社員たちも取り組む意識を持つようにしていきたいところ。そのために、時間のゆとりを作り、会社のことを考え、遊びも許容するよう、評価の基準を変える必要があるだろう。
tweet
経営者の仕事には、新規事業や新しい社内制度、ブランディングなど、すぐに結果は出ないが長期的に見て意味が出てくるものが多い。目の前のすぐに結果の出る仕事をするのは気持ちは楽だが、たとえ仕事をしていないように見えるようなことにも取り組むことが、その会社の未来を作ることに繋がっている。
tweet
チャレンジをした人は、それがうまくいっても駄目であったとしても、同じくチャレンジする人のことを尊敬できるようになる。それだけでも、チャレンジすることの価値はある。チャレンジした人は、これからチャレンジする人を止めたりせずに、むしろ応援するはずだ。それもチャレンジすることの価値だ。
tweet
考え過ぎて堂々巡りになる人もいるが、そういうときは文章にしてアウトプットしてみると良い。考えているより簡単なことだったりする。考える力のパラメータの一つには、コンピュータのメモリのようなものがある。余裕がなければすぐに飽和してしまう。アウトプットしてからクリアすれば、また使える。
tweet
リーダーは、リーダーに任じられるから、リーダーになれるのではない。己からリーダーたる振る舞いをし、皆からリーダーと認められたとき、リーダーとなれるのである。リーダーたる振る舞いをするのに、許可も指示も必要はない。名実ともにリーダーであるには、まず実質的にリーダーである必要がある。
tweet
時間を大事にする習慣の一つは、無駄に迷う時間をなくすことだ。くだらない選択で時間を失うのは勿体無い。迷いたくないもの、毎日の繰り返しは事前に決めておけばいい。例えば、毎日の運動だったら、やるかやらないか迷う時間は勿体無い。決めたことはやる。迷うのは贅沢な時間だ。趣味だったら良い。
tweet
習慣を変えたければ、まず時間の使い方を変えること。大きな目標も立派な決意も効果は薄い。大袈裟にせず、小口化して時間をとること。例えば、走ることで言えば、距離より時間。時間さえかけていけば、距離はいずれ伸びる。その逆はない。コントロールできるものを変える。時間はコントロールできる。
tweet
10分あったら何をするか、を考えるだけで、人生が大きく変わりそうな気がする。10分ほどあっても何もできないから、ダラダラするのか、それとも、10分もあれば出来ることがあると考えるのか。10分あるときにすることを事前に決めておけば、良さそうだ。10分あったら、1キロ歩ける。大きい。
tweet
良い議論をするためにも、良い対話にするためにも、「質問力」はとても重要なスキルだ。良い質問をするには、視点の広さと沢山の観点を持っていなければ出来ない。視点を広げるには、広い視点の人と話すことが、観点を増やすには体験の伴う経験が必要だ。それが良い会話のための「切り口」となるのだ。
tweet
失敗から学ぶと言うが、成功からしか本当の学びは得られないのではないか。失敗から学べるのは、同じ失敗を繰り返さない方法で、成功ではない。それも学びだが、失敗は一種類ではなくキリがない。最初から大成功でなくても、小さな成功体験を積むので良い。ただ失敗を恐れて何もしないことは良くない。
tweet
ナレッジワーカーのチームでは、中間管理職のいらないセルフマネジメント、数値目標から逆算しないシステム志向、自分のことは自分でするハックカルチャー、案件ありきでない採用、規模を追求しない価値観、会社の目的は利益でなくビジョンなど、様々に関連する要素が組み合わされば、うまくいきそう。
tweet
マーケティングは、ナレッジワーカーである社員全員が担うチームにしたい。新しい市場を作る、市場のシェアを広げる、見込み顧客に見つけてもらう、今の顧客に満足してもらう、市場や顧客に向きあう行為はすべてマーケティング。その実現のためには、各々が指示を待つのでなく自分で考える必要がある。
tweet
「システム志向」の経営者は、私もそうだけど、そんな派手なことを言ったりしないのでメディア受けはしない為、あまり多くの人に知られず技術者が経営者を目指すことが少なくなっているのかも。特に日本だと営業出身の経営者が多いように見えるし、そうした派手で豪快な方が社長っぽいイメージがある。
tweet
高めの目標を設定し、ゴールから逆算して考える「ゴール志向」の経営者には、営業出身の人が多い印象で、一つずつ積み上げて、着実に進めていこうと考える「システム志向」の経営者には、プログラマ出身の人が多い印象。どちらが良いかはさておき、会社に入る前にはどちらなのか知っておいた方が良い。
tweet
最近、何にどれだけ時間をかけたか記録し続けている。記録することで、時間の使い方を気をつけるようになる。カロリーを記録するダイエットに似てる。やはり見えるようになると気をつける。ドラッカーさんも曰く「知識労働者が成果をあげるための第一歩は、実際の時間の使い方を記録することである。」