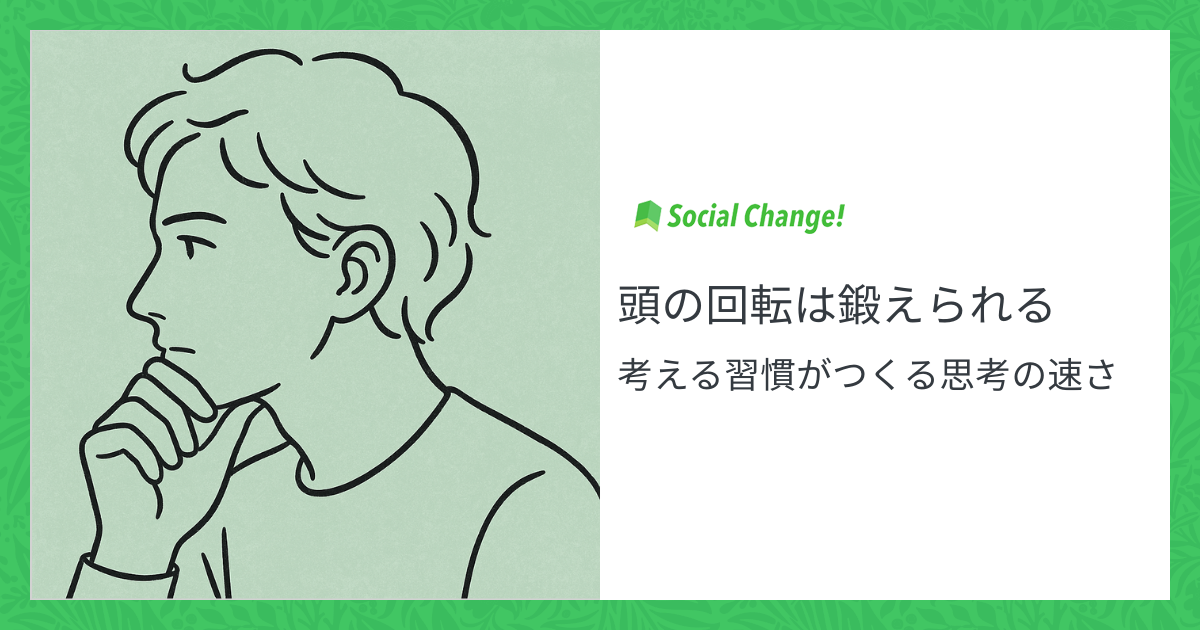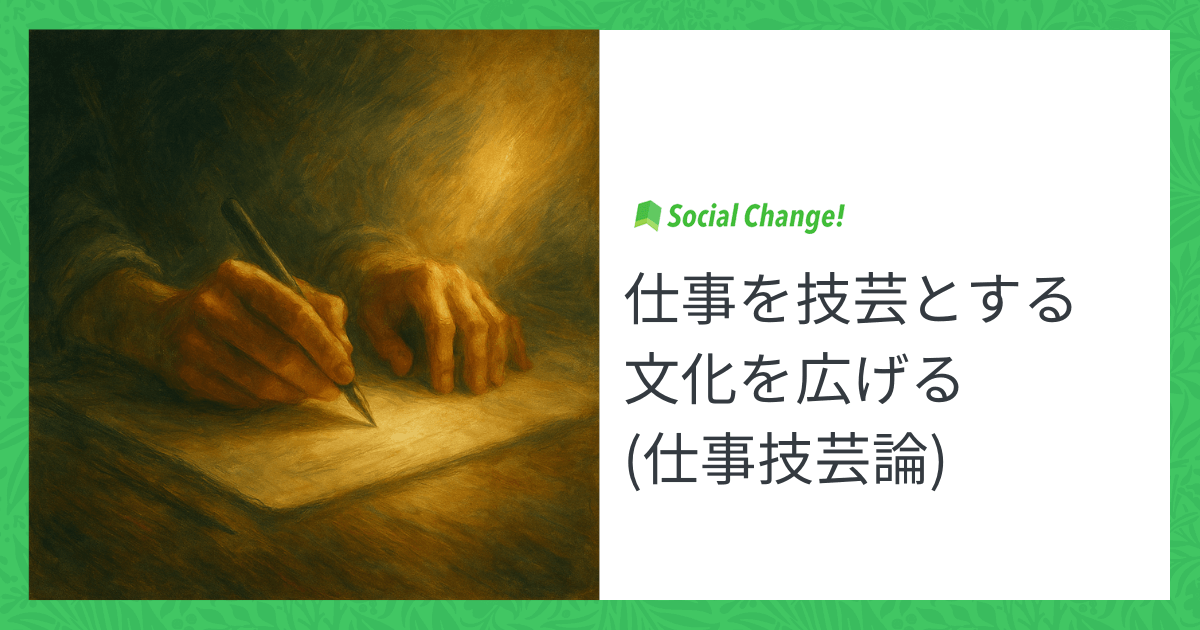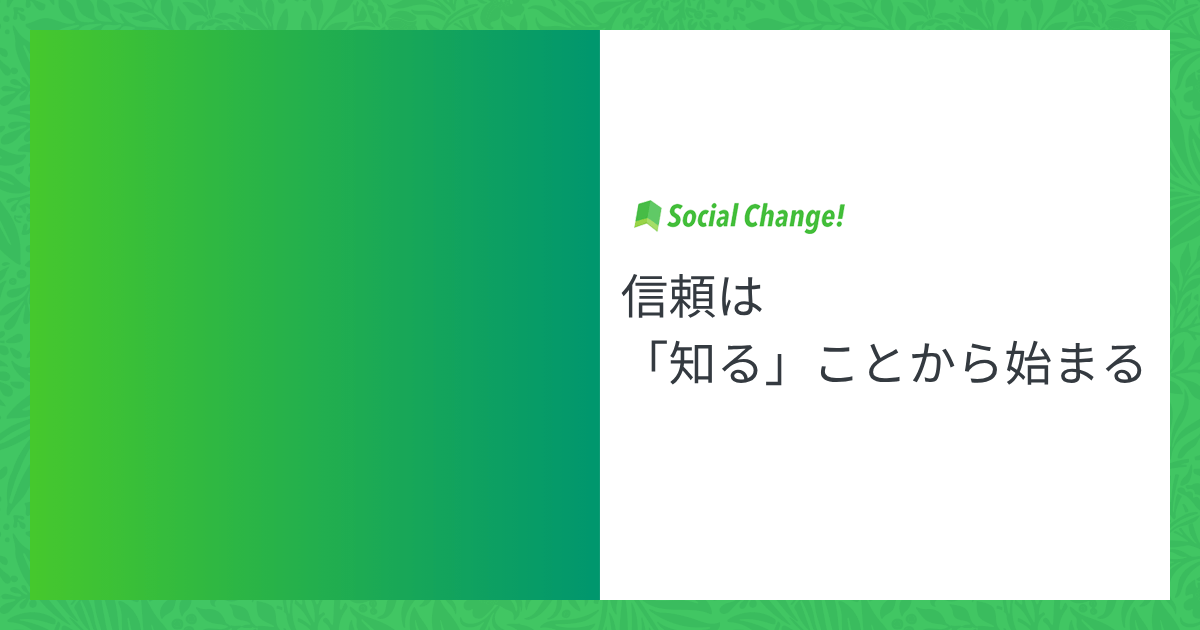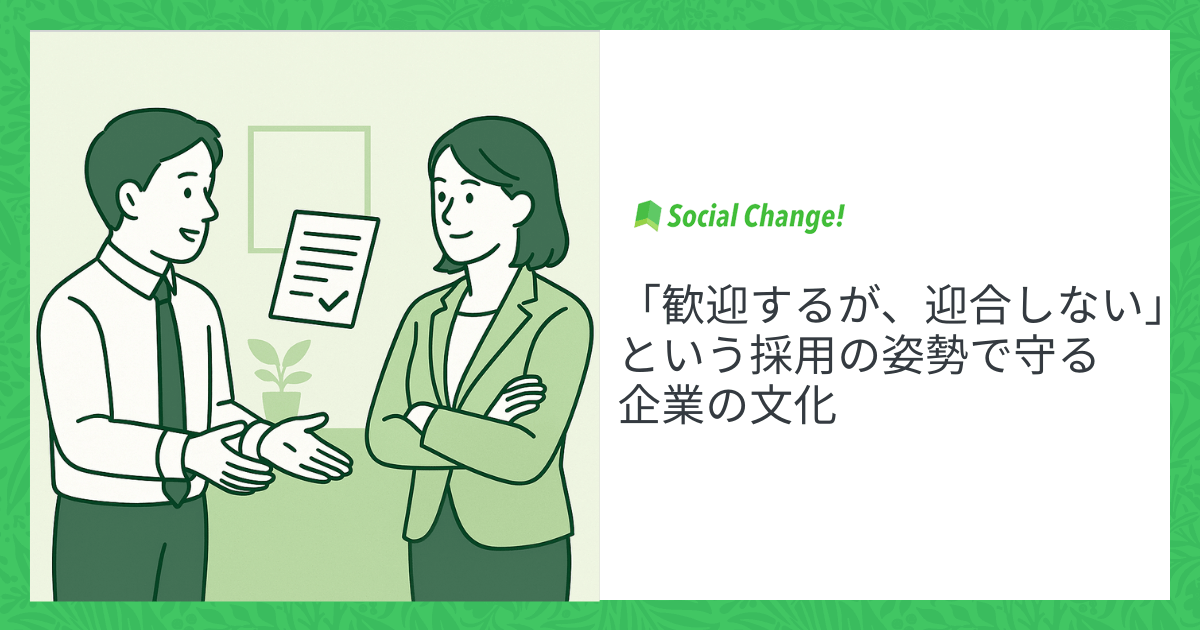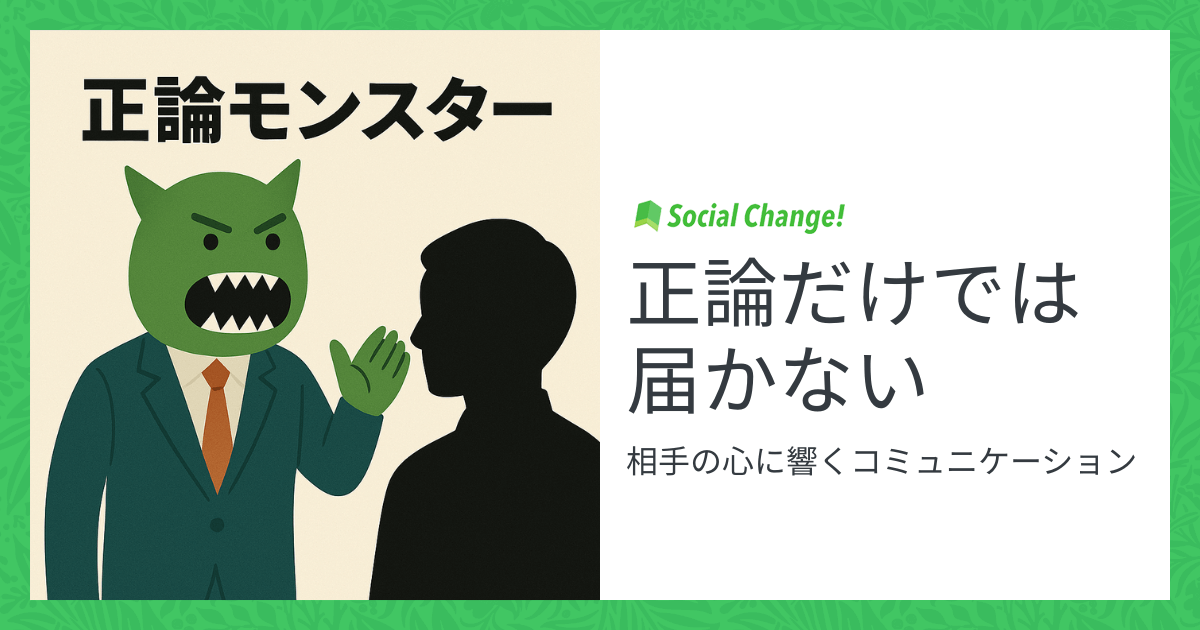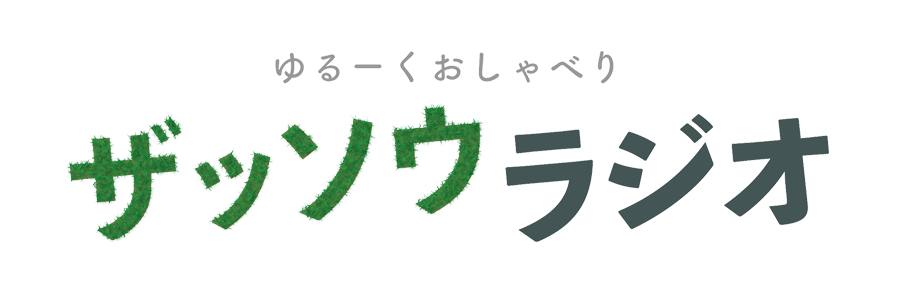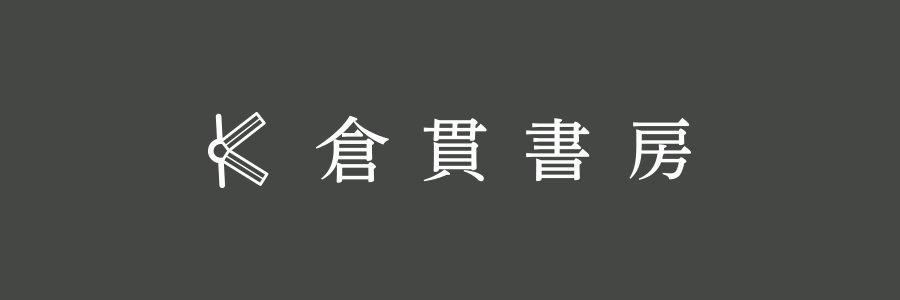私の考えるコミュニティの価値。会社の中にだけずっといると、知らないうちに会社の常識が自分の常識になってしまう。コミュニティには自分の常識を覆してくれる人たちとの出会いがある。脳のブレーキを壊してくれる人との出会いは、自分の人生の進める距離を伸ばしてくれる。 #xpjug
投稿
tweet
プログラムを始めた頃に、インデントの揃え方や、タブキーは使ってもタブ文字は使ってはいけないとか、その辺りを何故かも含めて教えて貰えるかどうかで、案外良いプログラマかそうでないかの分かれ目になるのかもしれない。
tweet
今まで自分は無駄なことが嫌いだと思っていたけど、そうではなくて、何も考えずに昔からの習慣や商習慣に従うことが嫌いなんだとわかった。
tweet
カタチやルールから入るのではなくて、本質にあわせて形を決めていくのが大事。それには、見栄や体裁を捨てないと出来ない。そう出来るのはスタートアップのうちだけかもしれない。
tweet
コンサル屋さんと仕事して学んだプレゼンのフレームワーク。1.問題に至る背景の共有と共感。2.対象とする問題の提示。3.解決につながる仮説(プロダクト)。4.それが正しい解決であるというプルーフ。この順番が重要。
tweet
大企業の情報システム部と現場で起きてる矛盾。システム部は統制をしようとするので、現場はシステム部に必要なシステムの依頼をするが、システム部は全体最適を重視するので対応してくれない。現場は不満を持つが、統制されて勝手なことは出来ない。そんなことが起きてる印象。
tweet
プログラマと漫画家の対比で考えたら、今のウェブスタートアップは、全て自費出版みたいな状態で、漫画家自身が直接読者を集めようとしてるに等しい。いくらインフラが低コストになったとして、プログラマ自身がマネジメントやマーケティングのすべてをするのは無理があるね。出版社が必要か。
tweet
プログラマには「何を作る」のか考えられるプログラマと「どう作る」を追求するプログラマの2種類いる。どっちが優劣ではなく違いがある。漫画家で言うと、独りで全て出来る人と、原作と作画が分かれて作画を追求する人。そう考えてプログラマは漫画家に似てると思った。
tweet
ネットワークの向こう側だろうがこちら側だろうが、顧客との対話なくして良いプロダクトなんて作れる訳がない。ブログやソーシャルメディアは、今の時代にあった、その対話のためのツールなんだよね。
tweet
サラリーマンのゴールは、その会社の社長だと考えてるような人が、長い時間かけて定年間際に社長になるのやめよう。目指すのは、トップに立つ人のビジョンであって、トップに立つことをゴールに設定した人事制度や人生設計してる時点で、ビジョンの実現など到底無理だ。
tweet
人間、歳を経ると「諦め」に対する抵抗が薄くなるように思う。だけど、諦めたからこそそれに覚悟を決めて取り組む、とか、諦めたからこそ別のことは精一杯やる、とか思えるようにもなってくる。そうでないと、ただのくたびれた大人になってしまいそう。
tweet
戦略では「しないこと」を決めるのが重要。しかし、しないことを決めるのが難しいのは、何かをしないってのは諦めることなので野望に燃える若いうちは難しいんだと思う。誰にでも刺さるようにシェアのマジョリティをとりたいと思うと総花的になってやめれない。
tweet
起業する人にとってビジョンとは自分の信じる仮説であって、起業とはその仮説の証明を自らしようとする実験なのではないか。私はそんな感じ。
tweet
プログラマの採用で、良いプログラマかどうか判断できるのは、良いプログラマだけと考えて、人事もプログラマがするようにしてる。
tweet
ソフトウェア開発は属人的なので、それを認めてしまった上で、属人的なビジネスモデルにしてしまった方がちゃんと儲かる。
tweet
それを言うと、スーパープログラマがいないと出来ないと言われるけれど、別にスーパーでなくて、それこそがプログラマだと思っている。つまり、プログラマは誰でも出来る仕事ではない、と。
tweet
ソフトウェア開発をプロセスからメタファを考えると、建築とか製造業とかにいってしまっておかしくなる。プログラマとは一体、どんな職業に似ているか、と考えた方が良い。勿論、ここで言うプログラマはコーダーのことではない。
tweet
戦略なきビジョンはただの夢になってしまう。だから一生懸命にビジネスモデルやマーケティングを考えるんだよね。